Pythonのcontinue文は、ループ処理中に特定の条件で処理をスキップし次の繰り返しに進む制御文です。この記事では、for文・while文での具体的な使用例、break文やpass文との違い、無限ループの回避方法、ネストされたループの最適化など実践的な活用法を解説。データ処理やエラーハンドリングでの応用例も紹介し、初心者がつまずきやすい注意点とコーディングのベストプラクティスが習得できます。
目次
Pythonのcontinue文とは?基本概念を理解しよう

Pythonのプログラミングにおいて、ループ処理を柔軟に制御することは非常に重要です。continue文は、ループ内で特定の条件に該当する場合に、残りの処理をスキップして次の繰り返しに進むための制御構文です。この機能を適切に活用することで、コードの効率性と可読性を大きく向上させることができます。ここでは、continue文の基本的な概念と、他の制御文との違いについて詳しく解説していきます。
continue文の定義と役割
continue文は、ループ処理の途中で現在の繰り返しを中断し、即座に次の繰り返しに移行させるための制御文です。forループやwhileループの中で使用され、特定の条件を満たした場合に、その後のコードブロックをスキップして、ループの先頭に戻ります。
continue文の主な役割は以下の通りです:
- 条件に合わない要素の処理をスキップする:リストやデータセットから特定の条件に該当しない要素を飛ばして処理を続けられます
- 不要な処理を回避する:エラーが発生しそうな状況や処理が不要なケースで、余計な実行を防ぎます
- ネストの深さを減らす:if-else文を多用する代わりにcontinue文を使うことで、コードのネスト階層を浅く保てます
- ループの効率化:条件に該当しない処理を早期にスキップすることで、実行時間を短縮できます
# continue文の基本的な使用例
for i in range(10):
if i % 2 == 0:
continue # 偶数の場合はスキップ
print(i) # 奇数のみ出力される
# 出力: 1 3 5 7 9
この例では、偶数に該当する場合にcontinue文が実行され、print文がスキップされます。結果として、奇数のみが出力される仕組みです。
continue文とpass文の違い
continue文とpass文は、どちらもPythonの制御文ですが、その動作と目的は大きく異なります。初心者にとって混同しやすいポイントですので、明確に理解しておくことが重要です。
continue文はループの次の繰り返しに進むのに対し、pass文は何も実行せずに次の行に進むという違いがあります。
| 項目 | continue文 | pass文 |
|---|---|---|
| 動作 | ループの先頭に戻って次の繰り返しを開始 | 何もせずに次の行に進む |
| 使用場所 | ループ内でのみ使用可能 | どこでも使用可能 |
| 後続コード | スキップされる | 実行される |
| 主な目的 | 特定条件での処理のスキップ | 構文上の空白を埋めるプレースホルダー |
# continue文の例
for i in range(5):
if i == 2:
continue
print(f"continue: {i}")
# 出力: 0 1 3 4 (2はスキップされる)
# pass文の例
for i in range(5):
if i == 2:
pass
print(f"pass: {i}")
# 出力: 0 1 2 3 4 (すべて出力される)
pass文は主に、まだ実装していない関数やクラス、条件分岐の空のブロックなど、構文上何かを記述する必要があるが処理内容が未定の場合に使用されます。一方、continue文は実際に処理フローを変更する能動的な制御文です。
continue文とbreak文の違い
continue文とbreak文は、どちらもループ制御に使用されますが、ループに与える影響が根本的に異なります。この違いを正確に理解することで、適切な場面で適切な制御文を選択できるようになります。
continue文は現在の繰り返しをスキップしてループを継続するのに対し、break文はループ自体を完全に終了させます。
| 項目 | continue文 | break文 |
|---|---|---|
| ループへの影響 | 次の繰り返しに進む(ループは継続) | ループを完全に終了する |
| 実行される回数 | 条件に合致するたびに複数回実行可能 | 通常は1回のみ実行される |
| ループ後のコード | ループが正常終了後に実行される | break直後に実行される |
| 使用シーン | 特定要素をスキップしたい場合 | 目的の要素を見つけた場合など |
# continue文の例:ループは最後まで継続
print("continue文の例:")
for i in range(5):
if i == 2:
continue
print(i)
# 出力: 0 1 3 4
# break文の例:ループが途中で終了
print("break文の例:")
for i in range(5):
if i == 2:
break
print(i)
# 出力: 0 1
実際の開発では、データのフィルタリングや条件に合わない要素のスキップにはcontinue文を使用し、検索処理で目的のデータを見つけたときや、エラー発生時の早期終了にはbreak文を使用するのが一般的です。両者を適切に使い分けることで、より効率的で理解しやすいコードを書くことができます。
continue文の基本的な使い方

Pythonのcontinue文は、ループ処理において特定の条件を満たした場合に、それ以降の処理をスキップして次の反復に進むための制御文です。この章では、for文とwhile文それぞれにおけるcontinue文の具体的な実装方法と、その動作フローについて詳しく解説します。continue文を正しく理解することで、より効率的で読みやすいコードを書けるようになります。
for文でのcontinue文の実装方法
for文でcontinue文を使用すると、ループ内の残りの処理をスキップして次のイテレーションに移行できます。特定の条件に該当する要素だけを処理対象から除外したい場合に非常に便利です。
以下は、for文でcontinue文を使用した基本的な例です。
for i in range(1, 6):
if i == 3:
continue
print(f"数値: {i}")
このコードの実行結果は以下のようになります。
数値: 1
数値: 2
数値: 4
数値: 5
上記の例では、変数iが3のときにcontinue文が実行され、print文がスキップされます。そのため、3だけが出力されず、他の数値は正常に表示されます。
より実用的な例として、リストから偶数のみを出力する処理を見てみましょう。
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for num in numbers:
if num % 2 != 0: # 奇数の場合
continue
print(f"偶数: {num}")
このコードでは、奇数の場合にcontinue文で処理をスキップし、偶数のみが出力されます。条件文とcontinue文を組み合わせることで、不要な処理を効率的に回避できます。
while文でのcontinue文の実装方法
while文でもcontinue文を使用できますが、for文と比べてカウンタ変数の更新を忘れると無限ループに陥る危険性があるため、注意が必要です。
while文でのcontinue文の基本的な使用例を見てみましょう。
count = 0
while count 5:
count += 1
if count == 3:
continue
print(f"カウント: {count}")
実行結果は以下の通りです。
カウント: 1
カウント: 2
カウント: 4
カウント: 5
この例では、countが3のときにcontinue文が実行され、print文がスキップされています。重要なポイントは、continue文の前にカウンタ変数の更新(count += 1)を配置していることです。
もし、カウンタの更新をcontinue文の後に配置してしまうと、以下のような問題が発生します。
# 【危険な例】無限ループになるコード
count = 0
while count 5:
if count == 2:
continue # count += 1が実行されないため無限ループに
count += 1
print(f"カウント: {count}")
上記のコードでは、countが2になった時点でcontinue文が実行され、count += 1に到達しないため、永遠にループから抜け出せなくなります。while文でcontinue文を使用する際は、必ずカウンタ変数の更新タイミングを適切に配置してください。
continue文の動作フロー
continue文の動作フローを正確に理解することで、より複雑な処理でも確実に意図した動作を実現できます。ここでは、continue文が実行されたときの処理の流れを詳しく解説します。
continue文の動作は以下のステップで進行します。
- ループ内でcontinue文に到達する
- continue文以降の処理がすべてスキップされる
- ループの条件判定部分に処理が戻る
- 次のイテレーションが開始される(または条件を満たさずループを終了)
具体的なフローを視覚的に理解するため、以下のコード例で確認しましょう。
for i in range(1, 4):
print(f"ループ開始: i = {i}")
if i == 2:
print("continue文を実行します")
continue
print(f"continue後の処理: i = {i}")
print(f"ループ終了: i = {i}")
print("---")
このコードの実行結果は以下のようになります。
ループ開始: i = 1
continue後の処理: i = 1
ループ終了: i = 1
---
ループ開始: i = 2
continue文を実行します
ループ開始: i = 3
continue後の処理: i = 3
ループ終了: i = 3
---
i = 2のときにcontinue文が実行され、「continue後の処理」と「ループ終了」の表示がスキップされていることが確認できます。continue文はループそのものを終了させるのではなく、現在の反復だけをスキップするという点が重要です。
ネストされたループ内でcontinue文を使用する場合、continue文は最も内側のループにのみ影響します。
for i in range(1, 4):
print(f"外側ループ: i = {i}")
for j in range(1, 4):
if j == 2:
continue
print(f" 内側ループ: j = {j}")
print("---")
実行結果:
外側ループ: i = 1
内側ループ: j = 1
内側ループ: j = 3
---
外側ループ: i = 2
内側ループ: j = 1
内側ループ: j = 3
---
外側ループ: i = 3
内側ループ: j = 1
内側ループ: j = 3
---
この例では、内側のループでcontinue文が実行されても、外側のループには影響を与えず、j = 2のときのみ内側のループの処理がスキップされます。複数のループを扱う際は、どのループに対してcontinue文が作用するのかを意識することが大切です。
“`html
continue文を使用する際の注意点

Pythonのcontinue文は便利な制御構文ですが、使い方を誤るとプログラムの動作に予期せぬ問題が生じる可能性があります。ここでは、continue文を安全かつ効果的に使用するために知っておくべき重要な注意点について解説します。適切な理解と実装により、バグを防ぎ、保守性の高いコードを書くことができます。
無限ループを防ぐための対策
continue文を使用する際に最も注意すべき点は、無限ループの発生リスクです。特にwhile文でcontinue文を使用する場合、ループカウンターやフラグの更新処理をスキップしてしまうと、ループが永遠に終了しない状態に陥る可能性があります。
# 悪い例:無限ループになってしまう
i = 0
while i 10:
if i % 2 == 0:
continue # i が更新されないため無限ループ
i += 1
print(i)このコードでは、i が偶数の場合にcontinue文が実行され、i のインクリメント処理がスキップされてしまいます。結果として、i は0のまま変わらず、無限ループに陥ります。
# 良い例:ループカウンターを適切に更新
i = 0
while i 10:
i += 1 # continue前にカウンターを更新
if i % 2 == 0:
continue
print(i)ループ変数の更新処理は、continue文よりも前に配置することで、この問題を回避できます。また、for文を使用できる場合は、イテレータが自動的に進むため、このような問題は起こりにくくなります。
コードの可読性を保つための工夫
continue文を多用すると、コードの流れが追いにくくなり、可読性が低下する恐れがあります。特に複数のcontinue文が異なる条件で使用されている場合や、ネストが深い場合には注意が必要です。
可読性を保つためには、以下のような工夫が有効です:
- 条件を明確にする:continue文を実行する条件には、わかりやすい変数名や適切なコメントを付けることで、処理の意図を明確にします。
- 早期リターンパターンを活用:複雑な条件分岐がある場合は、肯定条件ではなく除外条件を先に記述し、continue文で早期にスキップする方が読みやすくなります。
- ネストを浅く保つ:多重ループ内でcontinue文を使う場合は、どのループに対するcontinueなのかが明確になるようにコードを構造化します。
# 可読性の高い例
for user in users:
# 無効なユーザーはスキップ
if not user.is_active:
continue
# 権限のないユーザーはスキップ
if not user.has_permission:
continue
# 有効かつ権限のあるユーザーのみ処理
process_user(user)このように、処理したくない条件を先に列挙してcontinueでスキップすることで、メインの処理ロジックが明確になり、コードの意図が伝わりやすくなります。
ループ内でのみ使用可能な制限事項
continue文には重要な制限があります。それは、ループ構文(for文やwhile文)の内部でのみ使用可能という点です。ループの外でcontinue文を記述すると、SyntaxErrorが発生してプログラムが実行できません。
# エラーになる例
def process_data(data):
if data is None:
continue # SyntaxError: 'continue' not properly in loop
return data * 2この例では、関数内でcontinue文を使用していますが、ループの中ではないためエラーになります。このような場合は、returnやraiseなど、適切な制御文を使用する必要があります。
また、continue文は最も内側のループに対してのみ作用します。ネストされたループ構造では、continue文が実行されると、その文が含まれているループの次のイテレーションに進み、外側のループには影響を与えません。
# ネストされたループでの動作
for i in range(3):
for j in range(3):
if j == 1:
continue # 内側のループのみスキップ
print(f"i={i}, j={j}")
# 出力: i=0,j=0 i=0,j=2 i=1,j=0 i=1,j=2 i=2,j=0 i=2,j=2外側のループをスキップしたい場合は、フラグ変数を使用するか、関数に分割してreturnを使うなどの工夫が必要です。この制限を理解しておくことで、意図しない動作を防ぐことができます。
“`
continue文の実践的な活用シーン
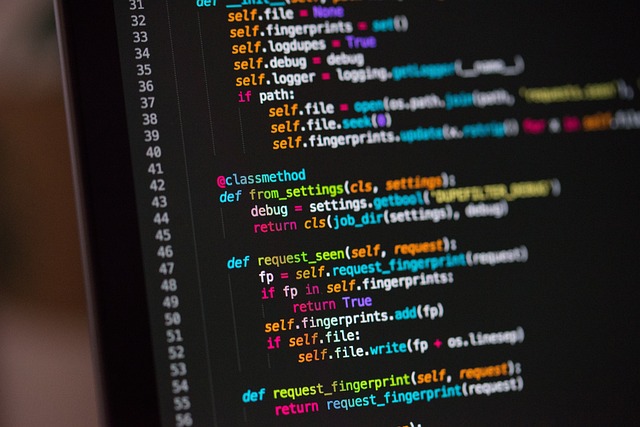
Pythonのcontinue文は基本概念を理解するだけでなく、実際の開発現場でどのように活用できるかを知ることが重要です。ここでは、continue文を使った実践的なテクニックを具体的なコード例とともに紹介します。これらの活用シーンを理解することで、より効率的で読みやすいコードを書けるようになります。
リストから特定要素をスキップする処理
データ処理において、リストやタプルから特定の条件に合致する要素だけをスキップして処理を続けたい場面は頻繁に発生します。continue文を使うことで、不要な要素を簡潔に除外できます。
以下は、数値リストから負の数をスキップして正の数だけを処理する例です。
numbers = [10, -5, 20, -3, 15, 0, 8]
positive_sum = 0
for num in numbers:
if num = 0:
continue # 0以下の数値はスキップ
positive_sum += num
print(f"追加: {num}, 合計: {positive_sum}")
print(f"正の数の合計: {positive_sum}")
このコードでは、continue文を使うことでネストを浅く保ち、可読性を向上させています。if文で条件を満たさない場合の処理を深くネストする代わりに、早期にスキップすることでメインの処理ロジックが明確になります。
文字列リストから空白や特定の文字列を除外する場合も同様に活用できます。
words = ["hello", "", "world", " ", "python", "continue"]
for word in words:
# 空白または空文字列をスキップ
if not word.strip():
continue
# 特定の単語をスキップ
if word == "continue":
continue
print(f"処理中: {word}")
ネストされたループでの最適化テクニック
複数のループが入れ子になっている場合、continue文を効果的に使うことで不要な処理をスキップし、パフォーマンスを向上させることができます。ただし、continue文は直近の(最も内側の)ループにのみ作用する点に注意が必要です。
二次元リストから特定の条件に合う要素だけを処理する例を見てみましょう。
matrix = [
[1, 2, 3, 4],
[5, 6, 7, 8],
[9, 10, 11, 12]
]
# 偶数のみを処理
for row in matrix:
for num in row:
if num % 2 != 0: # 奇数はスキップ
continue
print(f"偶数を検出: {num}")
# ここで偶数に対する処理を実行
さらに複雑な例として、座標系のデータ処理でも活用できます。
for x in range(10):
for y in range(10):
# 原点をスキップ
if x == 0 and y == 0:
continue
# 対角線上の点をスキップ
if x == y:
continue
# 境界線上の点をスキップ
if x == 0 or y == 0 or x == 9 or y == 9:
continue
# 条件を満たす座標のみ処理
print(f"処理対象の座標: ({x}, {y})")
このように、複数の条件でスキップすることで、実際に処理したい要素だけに絞り込むことができます。
データ処理での条件分岐の効率化
大量のデータを処理する際、continue文を使うことで条件分岐を効率化し、コードの見通しを良くすることができます。特に、複数の除外条件がある場合に威力を発揮します。
ユーザーデータのバリデーション処理を例に見てみましょう。
users = [
{"name": "Alice", "age": 25, "email": "alice@example.com"},
{"name": "", "age": 30, "email": "bob@example.com"},
{"name": "Charlie", "age": 17, "email": ""},
{"name": "Diana", "age": 28, "email": "diana@example.com"},
]
valid_users = []
for user in users:
# 名前が空の場合はスキップ
if not user.get("name"):
print(f"スキップ: 名前が空です")
continue
# 年齢が18歳未満の場合はスキップ
if user.get("age", 0) 18:
print(f"スキップ: {user['name']}は18歳未満です")
continue
# メールアドレスが空の場合はスキップ
if not user.get("email"):
print(f"スキップ: {user['name']}のメールアドレスが空です")
continue
# すべての条件をクリアしたユーザーのみ追加
valid_users.append(user)
print(f"追加: {user['name']}")
print(f"\n有効なユーザー数: {len(valid_users)}")
この手法は「ガード節パターン」とも呼ばれ、早期リターン(Early Return)の考え方をループに応用したものです。条件を満たさない場合に早期にスキップすることで、メインの処理ロジックのネストを浅く保つことができます。
CSVやJSONなどのデータファイルを処理する際にも同様のパターンが活用できます。
data_rows = [
"100,Product A,1500",
"101,Product B,", # 価格が空
"102,,2000", # 商品名が空
"103,Product C,2500",
"invalid_data", # フォーマットエラー
]
for row in data_rows:
# カンマで分割
parts = row.split(",")
# フォーマットが正しくない場合はスキップ
if len(parts) != 3:
print(f"フォーマットエラー: {row}")
continue
product_id, name, price = parts
# 商品名が空の場合はスキップ
if not name.strip():
print(f"商品名が空: ID {product_id}")
continue
# 価格が空または数値でない場合はスキップ
if not price.strip() or not price.isdigit():
print(f"価格が無効: {name}")
continue
# 正常なデータのみ処理
print(f"処理成功: {name} - ¥{price}")
エラーハンドリングでの活用方法
continue文は例外処理と組み合わせることで、一部のデータでエラーが発生しても処理全体を継続させることができます。これは大量のデータを扱うバッチ処理やETL処理で特に有用です。
try-except文とcontinue文を組み合わせた基本的なパターンを見てみましょう。
numbers_str = ["10", "20", "abc", "30", "40.5", "50"]
processed_numbers = []
for num_str in numbers_str:
try:
# 整数への変換を試みる
num = int(num_str)
processed_numbers.append(num)
print(f"変換成功: {num}")
except ValueError:
print(f"変換失敗: '{num_str}' は整数ではありません")
continue # エラーが発生したらスキップして次へ
print(f"\n処理された数値: {processed_numbers}")
ファイル処理での実践的な例も見てみましょう。
file_paths = [
"data1.txt",
"data2.txt",
"missing_file.txt",
"data3.txt"
]
results = []
for file_path in file_paths:
try:
# ファイルを開いて処理
with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
content = f.read()
results.append({
'file': file_path,
'size': len(content),
'status': 'success'
})
print(f"処理完了: {file_path}")
except FileNotFoundError:
print(f"ファイルが見つかりません: {file_path}")
continue # 次のファイルへ
except PermissionError:
print(f"アクセス権限がありません: {file_path}")
continue # 次のファイルへ
except Exception as e:
print(f"予期しないエラー ({file_path}): {e}")
continue # 次のファイルへ
print(f"\n成功したファイル数: {len(results)}")
API呼び出しやデータベースクエリなど、外部リソースへのアクセスでも同様のパターンが有効です。
user_ids = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
successful_updates = 0
failed_updates = 0
for user_id in user_ids:
try:
# データベース更新処理を想定
# update_user(user_id) # 実際のDB処理
# デモ用: IDが5の倍数でエラーを想定
if user_id % 5 == 0:
raise Exception("データベース接続エラー")
successful_updates += 1
print(f"ユーザー {user_id} の更新完了")
except Exception as e:
failed_updates += 1
print(f"ユーザー {user_id} の更新失敗: {e}")
continue # エラーが発生しても次のユーザーへ
print(f"\n成功: {successful_updates}件, 失敗: {failed_updates}件")
ただし、エラーを無視しすぎると問題の原因が特定しにくくなるため、ログ出力やエラーカウントの記録など、適切なエラー管理を行うことが重要です。
continue文のよくある間違いと解決策
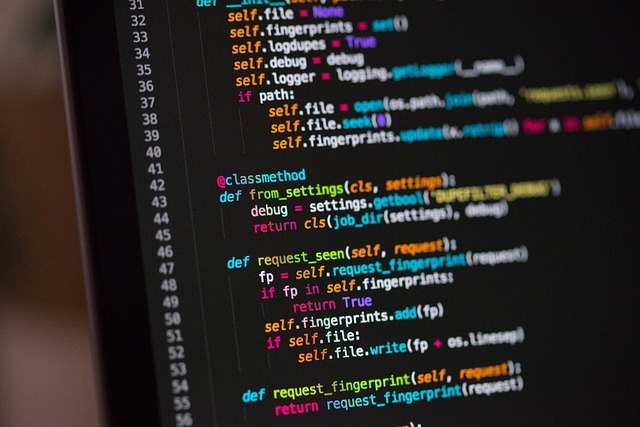
Pythonのcontinue文は便利な制御構文ですが、初心者から中級者まで多くの開発者が様々な場面でミスを犯しやすい要素でもあります。このセクションでは、実際のコーディングでよく発生するエラーパターンと、それらを効率的に解決する方法について詳しく解説します。これらのポイントを押さえることで、より堅牢で保守性の高いコードを書けるようになります。
初心者が陥りやすいミスパターン
continue文を使用する際、初心者がよく遭遇するミスにはいくつかの典型的なパターンがあります。これらを理解しておくことで、同じ間違いを避けることができます。
最も多いミスの一つが、ループの外でcontinue文を使用してしまうケースです。continue文はループ構造(for文やwhile文)の中でのみ使用可能で、ループ外で使用するとSyntaxErrorが発生します。
# 間違った例
x = 10
if x > 5:
continue # SyntaxError: 'continue' not properly in loop
# 正しい例
for x in range(10):
if x > 5:
continue
print(x)
次に多いのが、continue文の後にコードを書いてしまい、そのコードが実行されないことに気づかないミスです。continue文が実行されると、その後の処理はスキップされて次のイテレーションに進むため、continue以降のコードは到達不能になります。
# 非効率な例(到達不能なコード)
for i in range(5):
if i % 2 == 0:
continue
print(f"{i}は偶数です") # この行は実行されない
print(f"{i}は奇数です")
# 改善例
for i in range(5):
if i % 2 == 0:
print(f"{i}は偶数です")
continue
print(f"{i}は奇数です")
また、ネストされたループでcontinue文の影響範囲を誤解するミスも頻繁に見られます。continue文は最も内側のループにのみ影響し、外側のループには影響しません。
# 誤解されやすい例
for i in range(3):
for j in range(3):
if j == 1:
continue # 内側のループのみスキップ
print(f"i={i}, j={j}")
# 外側のループは通常通り継続
# 結果: i=0,j=0 / i=0,j=2 / i=1,j=0 / i=1,j=2 / i=2,j=0 / i=2,j=2
さらに、条件式の論理エラーにより、意図しない動作をするパターンもよくあります。特にnotやandなどの論理演算子を使った複雑な条件では注意が必要です。
# 論理エラーの例
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
for num in numbers:
if not num > 3: # 3以下をスキップしたいが、論理が逆
continue
print(num) # 実際には4と5のみ出力される
# 意図を明確にした例
for num in numbers:
if num = 3: # 3以下をスキップ
continue
print(num)
デバッグのポイント
continue文が関与するコードのデバッグは、処理がスキップされるという性質上、通常のデバッグよりも難しくなることがあります。効果的なデバッグ手法を身につけることで、問題を迅速に特定できます。
最も基本的で効果的な手法は、print文を使ったログ出力です。continue文の前後にprint文を配置することで、どの条件でスキップが発生しているかを明確に把握できます。
# デバッグ用のprint文を挿入
data = [10, -5, 20, -3, 15]
for value in data:
print(f"処理中: {value}") # 全ての値を確認
if value 0:
print(f" → {value}は負の数のためスキップ") # スキップ理由を明示
continue
print(f" → {value}を処理します")
result = value * 2
print(f" → 結果: {result}")
Python標準ライブラリのloggingモジュールを使用すると、より本格的なデバッグが可能です。ログレベルを調整することで、本番環境と開発環境で異なる詳細度の情報を出力できます。
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
logger = logging.getLogger(__name__)
for i in range(5):
logger.debug(f"イテレーション開始: i={i}")
if i % 2 == 0:
logger.info(f"i={i}は偶数のためスキップ")
continue
logger.debug(f"i={i}の処理を実行")
カウンター変数を使用してスキップ回数を追跡する手法も、データ処理の妥当性を検証する際に有効です。
# スキップ回数を追跡
processed_count = 0
skipped_count = 0
error_count = 0
data_list = [1, 2, None, 4, "invalid", 6]
for item in data_list:
if item is None:
skipped_count += 1
continue
if not isinstance(item, int):
error_count += 1
continue
processed_count += 1
# 実際の処理
print(f"処理済み: {processed_count}, スキップ: {skipped_count}, エラー: {error_count}")
IDEのデバッガ機能やPythonのpdbモジュールを使用したブレークポイント設定も、複雑な条件分岐をデバッグする際に非常に有効です。
import pdb
for i in range(10):
if i == 5:
pdb.set_trace() # ここで実行を一時停止
if i % 3 == 0:
continue
print(i)
効率的なコーディング手法
continue文を使用する際、コードの可読性と保守性を高めるための効率的な手法があります。これらの手法を実践することで、プロフェッショナルなコード品質を実現できます。
早期リターン(早期スキップ)パターンを採用することで、ネストを減らし可読性を向上させることができます。複数の条件をネストさせるのではなく、除外条件を先に処理します。
# ネストが深い例(非推奨)
for user in users:
if user.is_active:
if user.age >= 18:
if user.email_verified:
process_user(user)
# 早期スキップパターン(推奨)
for user in users:
if not user.is_active:
continue
if user.age 18:
continue
if not user.email_verified:
continue
process_user(user)
条件式を明確かつシンプルに保つことも重要です。複雑な条件式は別の変数に抽出することで、コードの意図が明確になります。
# 複雑な条件式
for data in dataset:
if not (data['status'] == 'active' and data['score'] > 50 and len(data['tags']) > 0):
continue
# 処理
# 意図が明確な例
for data in dataset:
is_valid = data['status'] == 'active' and data['score'] > 50 and len(data['tags']) > 0
if not is_valid:
continue
# 処理
関数化によってロジックを分離する手法も、continue文を含むコードの保守性を大幅に向上させます。
# 関数化前
for item in items:
if item['price'] 0 or item['quantity'] == 0:
continue
if item['category'] not in ['A', 'B', 'C']:
continue
# 複雑な処理...
# 関数化後
def should_skip_item(item):
"""アイテムをスキップすべきか判定"""
if item['price'] 0 or item['quantity'] == 0:
return True
if item['category'] not in ['A', 'B', 'C']:
return True
return False
for item in items:
if should_skip_item(item):
continue
# 複雑な処理...
リスト内包表記やfilter関数など、Pythonicな代替手法を検討することも効率的なコーディングには欠かせません。状況によってはcontinue文よりも簡潔で読みやすいコードになります。
# continue文を使用
result = []
for num in range(20):
if num % 2 == 0:
continue
if num % 3 == 0:
continue
result.append(num)
# リスト内包表記(より簡潔)
result = [num for num in range(20) if num % 2 != 0 and num % 3 != 0]
# filter関数(条件が複雑な場合)
def is_valid(num):
return num % 2 != 0 and num % 3 != 0
result = list(filter(is_valid, range(20)))
コメントを適切に配置して、なぜその条件でスキップするのかを明示することも重要です。特にビジネスロジックに関わる条件では、理由を明記することで将来のメンテナンスが容易になります。
for order in orders:
# キャンセルされた注文は集計から除外
if order.status == 'cancelled':
continue
# テスト注文(金額が0円)は統計に含めない
if order.total_amount == 0:
continue
# 実際の集計処理
calculate_statistics(order)
“`html
continue文を使った実用的なコード例

continue文の基本的な使い方を理解したら、次は実際の開発現場で役立つ実践的なコード例を見ていきましょう。ここでは業務でよく遭遇するデータ処理やフィルタリングの場面で、continue文を効果的に活用する方法を具体的なコードとともに解説します。これらの例を参考にすることで、より洗練されたコードが書けるようになります。
データフィルタリング処理の実装例
データ処理において、特定の条件に合わないデータをスキップする処理は頻繁に発生します。continue文を使うことで、こうしたフィルタリング処理を直感的かつ効率的に実装できます。以下は、顧客データから有効なレコードのみを処理する実例です。
# 顧客データから有効なメールアドレスのみを処理
customers = [
{'name': '田中太郎', 'email': 'tanaka@example.com', 'age': 30},
{'name': '佐藤花子', 'email': '', 'age': 25},
{'name': '鈴木一郎', 'email': 'suzuki@example.com', 'age': -5},
{'name': '高橋美咲', 'email': 'takahashi@example.com', 'age': 28},
]
valid_customers = []
for customer in customers:
# メールアドレスが空の場合はスキップ
if not customer['email']:
print(f"{customer['name']}:メールアドレスなし(スキップ)")
continue
# 年齢が不正な場合はスキップ
if customer['age'] 0 or customer['age'] > 120:
print(f"{customer['name']}:不正な年齢(スキップ)")
continue
# 有効なデータのみ処理
valid_customers.append(customer)
print(f"{customer['name']}:データ登録完了")
print(f"\n有効な顧客数:{len(valid_customers)}件")
このコードでは、メールアドレスの欠落や年齢の異常値といった無効なデータを検出した時点でcontinueを使ってスキップしています。これにより、ネストを深くせずに複数の検証条件を記述できるため、コードの可読性が大幅に向上します。
さらに、CSVファイルから数値データを読み込む際のエラー処理にも応用できます。
# 数値データの読み込みと不正値のスキップ
sales_data = ['1000', '2500', 'N/A', '3200', '', '4100', 'error']
total_sales = 0
valid_count = 0
for data in sales_data:
# 空文字列はスキップ
if not data:
continue
# 数値に変換できない場合はスキップ
try:
sales = int(data)
except ValueError:
print(f"'{data}'は数値ではありません(スキップ)")
continue
# 負の値はスキップ
if sales 0:
continue
total_sales += sales
valid_count += 1
print(f"合計売上:{total_sales}円(有効データ数:{valid_count}件)")
業務で使える応用パターン
実際の業務では、より複雑なデータ処理が求められます。ここでは、ログ分析、レポート生成、バッチ処理など、実務で頻出する応用パターンを紹介します。
まず、ログファイル分析でエラーログのみを抽出する例を見てみましょう。
# アクセスログから特定条件のログを抽出
access_logs = [
{'status': 200, 'path': '/index.html', 'response_time': 50},
{'status': 404, 'path': '/missing.html', 'response_time': 10},
{'status': 200, 'path': '/api/data', 'response_time': 200},
{'status': 500, 'path': '/api/error', 'response_time': 1000},
{'status': 200, 'path': '/about.html', 'response_time': 30},
]
error_logs = []
slow_requests = []
for log in access_logs:
# 正常なステータスコードはスキップ
if log['status'] == 200:
# ただし、レスポンスタイムが遅い場合は記録
if log['response_time'] > 100:
slow_requests.append(log)
continue
# エラーログを記録
error_logs.append(log)
print(f"エラー検出:{log['status']} - {log['path']}")
print(f"\nエラー件数:{len(error_logs)}件")
print(f"低速リクエスト:{len(slow_requests)}件")
次に、バッチ処理でファイルを一括処理する際の実装例です。
# ファイル一括処理での応用
import os
files = ['document.txt', 'image.jpg', 'data.csv', '.hidden', 'report.pdf', 'backup~']
processed_files = []
for filename in files:
# 隠しファイルはスキップ
if filename.startswith('.'):
print(f"{filename}:隠しファイル(スキップ)")
continue
# バックアップファイルはスキップ
if filename.endswith('~'):
print(f"{filename}:バックアップファイル(スキップ)")
continue
# 特定の拡張子のみ処理
if not (filename.endswith('.txt') or filename.endswith('.csv')):
print(f"{filename}:対象外の形式(スキップ)")
continue
# ファイル処理を実行
processed_files.append(filename)
print(f"{filename}:処理完了")
print(f"\n処理済みファイル数:{len(processed_files)}件")
これらのパターンは、早期リターンの原則に基づいており、処理すべきでないケースを先に除外することで、メインロジックを明確にしています。
複数条件を組み合わせた制御方法
実務では、複数の条件を組み合わせた複雑な制御が必要になることがあります。continue文を使えば、複雑な条件判定でもネストを浅く保ちながら、わかりやすいコードを書くことができます。
まず、論理演算子と組み合わせた条件判定の例です。
# 複数条件でのフィルタリング
products = [
{'name': 'ノートPC', 'price': 80000, 'stock': 5, 'category': '電子機器'},
{'name': 'マウス', 'price': 1500, 'stock': 0, 'category': '周辺機器'},
{'name': 'キーボード', 'price': 3000, 'stock': 10, 'category': '周辺機器'},
{'name': 'モニター', 'price': 30000, 'stock': 3, 'category': '電子機器'},
{'name': 'USBケーブル', 'price': 500, 'stock': 20, 'category': '周辺機器'},
]
# 在庫があり、価格が1000円以上30000円以下の周辺機器を抽出
filtered_products = []
for product in products:
# 在庫切れはスキップ
if product['stock'] == 0:
continue
# カテゴリが周辺機器以外はスキップ
if product['category'] != '周辺機器':
continue
# 価格が範囲外の場合はスキップ
if product['price'] 1000 or product['price'] > 30000:
continue
filtered_products.append(product)
print(f"条件一致:{product['name']} - {product['price']}円")
print(f"\n抽出された商品数:{len(filtered_products)}件")
さらに、ネストしたループでの複雑な制御例も見てみましょう。
# マトリクスデータから特定条件の要素を処理
matrix = [
[1, 2, 0, 4],
[5, -1, 7, 8],
[0, 10, 11, 12],
[13, 14, 0, 16]
]
positive_sum = 0
processed_count = 0
for i, row in enumerate(matrix):
for j, value in enumerate(row):
# ゼロ値はスキップ
if value == 0:
continue
# 負の値はスキップ
if value 0:
print(f"位置[{i}][{j}]:負の値{value}(スキップ)")
continue
# 偶数値のみ処理(追加条件)
if value % 2 != 0:
continue
positive_sum += value
processed_count += 1
print(f"位置[{i}][{j}]:{value}を加算")
print(f"\n合計値:{positive_sum}(処理数:{processed_count}件)")
このように、continue文を使って条件を段階的にチェックすることで、複雑なビジネスロジックでも理解しやすいコードになります。各条件が独立して記述されているため、後からの修正や条件の追加も容易です。
最後に、辞書とリストを組み合わせた実践的な例を示します。
# ユーザー権限チェックを含む複合的な処理
users = [
{'id': 1, 'name': '管理者A', 'role': 'admin', 'active': True},
{'id': 2, 'name': 'ユーザーB', 'role': 'user', 'active': False},
{'id': 3, 'name': 'ユーザーC', 'role': 'user', 'active': True},
{'id': 4, 'name': '管理者D', 'role': 'admin', 'active': True},
]
actions = ['read', 'write', 'delete']
for user in users:
print(f"\n--- {user['name']}の権限チェック ---")
# 無効なユーザーはスキップ
if not user['active']:
print("ステータス:無効(スキップ)")
continue
# 一般ユーザーの場合、削除権限をスキップ
if user['role'] == 'user':
for action in actions:
if action == 'delete':
print(f"{action}権限:なし(スキップ)")
continue
print(f"{action}権限:あり")
continue
# 管理者は全権限を付与
for action in actions:
print(f"{action}権限:あり")
このような複数条件を組み合わせた実装では、continue文を効果的に使うことで、条件ごとに処理を分離でき、コードのメンテナンス性が向上します。特に、チーム開発やコードレビューの場面で、意図が明確に伝わるコードになります。
“`
“`html
continue文に関するよくある質問

Pythonのcontinue文について学習を進める中で、多くの開発者が同じような疑問を抱きます。ここでは、continue文の使用に関してよくある質問とその回答をまとめました。実務でcontinue文を効果的に活用するための参考にしてください。
どんな場合にcontinue文を使うべきか
continue文は、ループ処理の中で特定の条件に合致した要素をスキップしたい場合に使用するのが最適です。主に以下のようなシーンで活用されます。
- リストやデータセットから特定の条件を満たさない要素を除外する処理
- バリデーションで不正なデータをスキップして次の処理を続ける場合
- ネストが深くなることを避け、早期リターンでコードの可読性を高めたい時
- 例外的なケースを先に処理して、メインロジックをシンプルに保ちたい場合
特に、if-elseのネストが深くなりそうな場合、continue文を使って早期に次のループへ移行することで、コードの構造をフラットに保つことができます。例えば、データ処理でエラーケースを先に排除してから正常処理を記述すると、メインロジックが明確になり保守性が向上します。
ただし、continue文を多用しすぎると処理の流れが追いにくくなるため、使用は必要最小限に留め、コードレビューの際には他の開発者にとっても理解しやすい記述になっているか確認することが重要です。
パフォーマンスへの影響はあるか
continue文自体のパフォーマンスへの影響は、ほとんど無視できるレベルです。continue文はループの次の反復に制御を移すだけの単純な制御構文であり、実行速度に対する影響は極めて小さいと言えます。
むしろパフォーマンスの観点では、以下のようなメリットがあります。
- 不要な処理をスキップすることで、全体の実行時間を短縮できる
- 条件に合わない要素の処理を省略することで、計算リソースを節約できる
- 早期スキップにより、ネストされた複雑な条件分岐を回避できる
例えば、大量のデータを処理するループにおいて、特定の条件を満たさないデータを早期にスキップすることで、後続の重い処理(データベースアクセスや複雑な計算など)を実行せずに済み、結果として処理全体が高速化されます。
ただし、無駄なcontinue文を多数配置すると、分岐予測の観点からわずかにオーバーヘッドが発生する可能性はあります。とはいえ、Pythonのような高級言語においては、この影響は通常測定できないほど小さく、可読性や保守性を優先すべきでしょう。パフォーマンスが本当に重要な場合は、continue文の有無よりもアルゴリズム自体の見直しやデータ構造の最適化を検討することが推奨されます。
他の制御文との使い分け方
continue文は他の制御文と組み合わせて使用されることが多く、それぞれの特性を理解した上で適切に使い分けることが重要です。実務では状況に応じて最適な制御文を選択する必要があります。
break文との使い分け
break文はループ自体を終了させる一方、continue文は現在の反復だけをスキップして次の反復に進みます。探索処理で目的の要素が見つかった時点でループを抜けたい場合はbreakを使い、特定の要素だけを処理対象から除外したい場合はcontinueを使います。
| 制御文 | 動作 | 使用シーン |
|---|---|---|
| continue | 現在の反復をスキップ | 条件に合わない要素を除外して処理を続ける |
| break | ループ全体を終了 | 目的の要素が見つかった、またはエラーが発生した |
pass文との使い分け
pass文は何も処理を行わないプレースホルダーであり、continue文のように制御フローを変更しません。pass文は構文的に何かを記述する必要があるが実装が未定の場合や、意図的に何もしないことを明示したい場合に使用します。一方、continue文はループの残りの処理をスキップして次の反復に進むという明確な動作を持ちます。
if-else文との使い分け
単純な条件分岐であればif-else文で十分ですが、複数の例外条件を処理する場合、continue文を使った早期スキップの方がネストが浅くなり可読性が向上します。ガード節パターンとも呼ばれるこの手法は、正常系の処理を見通しよく記述するのに有効です。
# if-elseのネストが深い例
for item in items:
if item.is_valid():
if item.has_permission():
# メイン処理(ネストが深い)
process(item)
# continueを使った改善例
for item in items:
if not item.is_valid():
continue
if not item.has_permission():
continue
# メイン処理(フラットで読みやすい)
process(item)
このように、continue文は他の制御文と適切に組み合わせることで、より読みやすく保守性の高いコードを実現できます。
“`
“`html
Pythonのcontinue文まとめ

本記事では、Pythonのcontinue文について基本概念から実践的な活用方法まで幅広く解説してきました。continue文は、ループ処理において特定の条件に該当するイテレーションをスキップし、次のイテレーションへ移行するための制御文です。適切に使用することで、コードの可読性を向上させ、効率的なデータ処理を実現できます。
continue文を効果的に活用するためには、基本的な動作原理を正しく理解することが重要です。for文やwhile文といったループ構造の中でのみ使用可能であり、continue文が実行されると現在のイテレーションが即座に終了し、ループの先頭に戻って次の処理が継続されます。この動作フローを把握することで、データフィルタリングや条件分岐の最適化など、さまざまな場面で応用できるようになります。
また、continue文を使用する際には、pass文やbreak文との違いを明確に区別する必要があります。pass文は何も処理を行わずに次の行へ進むのに対し、continue文は残りの処理をスキップして次のイテレーションへ移行します。一方、break文はループ自体を終了させるため、処理の目的に応じて適切に使い分けることが求められます。
実践的な活用シーンとしては、リストから特定の要素をスキップする処理、ネストされたループでの最適化、エラーハンドリングとの組み合わせなど、業務で頻繁に遭遇する場面が多数あります。特にデータ処理においては、不要なデータを効率的に除外し、必要な要素のみを処理することで、コードの実行速度とメンテナンス性の両方を向上させることができます。
continue文を使用する際の注意点としては、以下のポイントを押さえておきましょう。
- while文でのcontinue使用時は、カウンタ変数の更新を忘れずに行い、無限ループを防ぐ
- ネストされたループでは、continue文がどのループに対して作用するか明確にする
- 複雑な条件分岐が必要な場合は、continue文の多用を避け、関数分割を検討する
- コードレビューやメンテナンスを考慮し、コメントを適切に記述する
初心者が陥りやすいミスとしては、continue文をループの外側で使用しようとする、無限ループを引き起こす、条件判定の順序を誤るといったパターンがあります。これらのエラーを防ぐためには、デバッグ時にprint文を活用してループの動作を確認し、段階的にコードを検証することが効果的です。
パフォーマンスの観点では、continue文自体が処理速度に大きな影響を与えることは少ないものの、適切に使用することで不要な処理をスキップでき、結果的に全体の実行効率を向上させることができます。ただし、過度な最適化よりも、まずはコードの可読性と保守性を優先することが推奨されます。
Pythonのcontinue文は、シンプルながら強力な制御構文です。本記事で紹介した基本的な使い方、注意点、実践的な活用例を参考にして、日々のプログラミングに取り入れてみてください。経験を積むことで、どのような場面でcontinue文が最適かを自然に判断できるようになり、より洗練されたPythonコードを書けるようになるでしょう。
“`




