JavaScriptのif文の基本構文から応用テクニックまでを網羅的に学べる記事です。条件分岐の書き方、else if・else文の使い方、論理演算子(&&、||、!)による複数条件指定、三項演算子での省略記法、入れ子構造の注意点などを実例付きで解説。初心者のif文理解から、より見やすくスマートなコード記述まで幅広いスキルが身につきます。
目次
JavaScriptのif文とは何か

if文の基本概念と役割
JavaScriptのif文は、プログラムにおいて条件に応じて異なる処理を実行するための制御文です。プログラムが実行される際、特定の条件が満たされているかどうかを判定し、その結果に基づいて処理の流れを分岐させる機能を持っています。
if文の基本的な仕組みは、条件式を評価してその結果がtrue(真)かfalse(偽)かを判定することです。条件がtrueの場合は指定された処理を実行し、falseの場合はその処理をスキップします。これにより、プログラムは状況に応じて柔軟な動作を実現できます。
例えば、ユーザーの年齢によって表示するメッセージを変える場合や、入力された値が正しい範囲内にあるかをチェックする場合など、様々な場面でif文が活用されています。JavaScriptにおいて、if文は最も基本的で重要な制御構造の一つであり、動的なWebアプリケーションの開発には欠かせない要素となっています。
条件分岐処理の重要性
条件分岐処理は、現代のプログラミングにおいてプログラムに知性と柔軟性を与える重要な仕組みです。if文による条件分岐がなければ、プログラムは常に同じ処理を順番に実行するだけの単純な構造となってしまいます。
Webアプリケーション開発においては、ユーザーの操作や入力データに応じて動的に反応する必要があります。例えば、フォームの入力値が正しいかをチェックし、エラーがある場合は警告を表示する処理や、ユーザーの権限に応じて表示するコンテンツを変更する処理などが挙げられます。これらの処理は全て条件分岐によって実現されています。
また、条件分岐処理は以下のような重要な価値を提供します:
- ユーザビリティの向上:ユーザーの状況に応じた適切な表示や操作を提供
- エラーハンドリング:予期しない入力や状況に対する適切な対応
- プログラムの効率性:不要な処理を避け、必要な処理のみを実行
- 保守性の向上:複雑な業務ロジックを整理して実装
これらの理由から、if文を使った条件分岐処理の理解と活用は、JavaScriptプログラミングの基礎として極めて重要な位置を占めています。
if文の基本構文と書き方

JavaScriptにおけるif文は、プログラムの制御構造の基本となる重要な文法です。条件によって処理を分岐させるため、様々な書き方が用意されています。ここでは、if文の基本的な構文から複雑な分岐処理まで、段階的に学習していきましょう。
基本的なif文の構文
最もシンプルなif文は、条件が真(true)の場合にのみ処理を実行する構文です。基本的な書き方は以下の通りです。
if (条件式) {
// 条件が真の場合に実行される処理
}実際のコード例を見てみましょう。
let age = 20;
if (age >= 18) {
console.log("成人です");
}この例では、変数ageが18以上の場合にのみ「成人です」というメッセージがコンソールに出力されます。条件式には比較演算子や論理演算子を使用して、様々な条件を設定できます。
if-else文の構文
条件が真の場合と偽の場合で異なる処理を実行したい時は、if-else文を使用します。else節を追加することで、条件を満たさない場合の処理も定義できます。
if (条件式) {
// 条件が真の場合の処理
} else {
// 条件が偽の場合の処理
}具体的な実装例は以下の通りです。
let score = 75;
if (score >= 80) {
console.log("合格です");
} else {
console.log("不合格です");
}この場合、scoreが80以上なら「合格です」、80未満なら「不合格です」が出力されます。if-else文を使用することで、必ずどちらか一方の処理が実行されることが保証されます。
if-else if-else文の構文
3つ以上の選択肢がある場合は、else if文を使用して複数の条件を順次チェックできます。この構文により、より詳細な条件分岐が可能になります。
if (条件式1) {
// 条件式1が真の場合の処理
} else if (条件式2) {
// 条件式2が真の場合の処理
} else {
// すべての条件が偽の場合の処理
}成績評価システムを例にした実装を見てみましょう。
let score = 85;
if (score >= 90) {
console.log("優秀");
} else if (score >= 80) {
console.log("良好");
} else if (score >= 60) {
console.log("可");
} else {
console.log("不可");
}この例では、scoreの値に応じて4段階の評価が行われます。条件は上から順にチェックされ、最初に真となった条件の処理が実行されて分岐処理が終了します。
複数のelse if文を使った分岐処理
実際の開発現場では、さらに多くの条件を組み合わせた複雑な分岐処理が必要になることがあります。複数のelse if文を効果的に活用することで、読みやすく保守性の高いコードを作成できます。
let userType = "premium";
let loginDays = 30;
if (userType === "admin") {
console.log("管理者権限でログイン");
} else if (userType === "premium" && loginDays > 365) {
console.log("プレミアム長期ユーザー");
} else if (userType === "premium") {
console.log("プレミアムユーザー");
} else if (userType === "standard" && loginDays > 100) {
console.log("標準長期ユーザー");
} else if (userType === "standard") {
console.log("標準ユーザー");
} else {
console.log("ゲストユーザー");
}複数のelse if文を使用する際は、条件の順序が重要です。より具体的な条件から先に記述し、一般的な条件を後に配置することで、意図した通りの分岐処理を実現できます。また、各条件が互いに排他的であることを確認し、想定外の結果を防ぐことが大切です。
JavaScriptで使用する演算子の種類

JavaScriptのif文で条件分岐を行う際には、様々な演算子を使用して条件式を記述します。これらの演算子を適切に理解し使い分けることで、より精密で効率的な条件判定が可能になります。特に比較演算子と論理演算子は、if文の核となる要素であり、プログラムの動作を決定する重要な役割を担っています。
比較演算子の一覧と使い方
比較演算子は、二つの値を比較して真偽値(true または false)を返すJavaScriptの基本的な演算子です。if文において条件式を構築する際に最も頻繁に使用され、プログラムの分岐処理を制御する重要な要素となります。
等価演算子(==)の特徴
等価演算子(==)は、二つの値が等しいかどうかを判定する演算子ですが、型変換を伴う比較を行う特徴があります。この演算子は比較する前に、異なるデータ型の値を自動的に共通の型に変換してから比較を実行します。
// 等価演算子の使用例
if (5 == "5") {
console.log("等価演算子では true と判定される");
}
if (0 == false) {
console.log("数値の0とfalseは等価と判定される");
}
if (null == undefined) {
console.log("nullとundefinedは等価と判定される");
}等価演算子は便利な面もありますが、予期しない結果を招く可能性があるため、使用時には十分な注意が必要です。特に、文字列と数値の比較、真偽値との比較において想定外の動作が発生する場合があります。
厳密等価演算子(===)の特徴
厳密等価演算子(===)は、型変換を行わずに値とデータ型の両方が完全に一致する場合のみtrueを返す演算子です。JavaScriptにおいて、より安全で予測可能な比較を行いたい場合に推奨される演算子となっています。
// 厳密等価演算子の使用例
if (5 === 5) {
console.log("値と型が完全に一致する場合のみtrue");
}
if (5 === "5") {
console.log("この条件は false になる");
}
if (0 === false) {
console.log("この条件も false になる");
}
// オブジェクトの比較
let obj1 = {name: "JavaScript"};
let obj2 = {name: "JavaScript"};
if (obj1 === obj2) {
console.log("参照が異なるため false");
}厳密等価演算子を使用することで、型変換による予期しない動作を避けることができ、コードの安全性と可読性が向上します。現代のJavaScript開発において、等価演算子よりも厳密等価演算子の使用が強く推奨されています。
その他の比較演算子
JavaScriptには等価性を判定する演算子以外にも、数値や文字列の大小関係を比較する演算子が用意されています。これらの演算子を適切に使用することで、範囲指定や順序に基づく条件分岐を実装できます。
| 演算子 | 名称 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| > | 大なり | 左辺が右辺より大きい | age > 18 |
| < | 小なり | 左辺が右辺より小さい | score < 60 |
| >= | 以上 | 左辺が右辺以上 | price >= 1000 |
| <= | 以下 | 左辺が右辺以下 | temperature <= 30 |
| != | 不等価 | 等価演算子の否定 | status != “completed” |
| !== | 厳密不等価 | 厳密等価演算子の否定 | value !== null |
// その他の比較演算子の実用例
let userAge = 25;
let minAge = 18;
let maxAge = 65;
if (userAge >= minAge && userAge = maxAge) {
console.log("年齢条件を満たしています");
}
let inputValue = "";
if (inputValue !== "") {
console.log("入力値が存在します");
}
// 文字列の比較(辞書順)
if ("apple" "banana") {
console.log("文字列も辞書順で比較可能");
}論理演算子を使った複合条件
論理演算子は、複数の条件式を組み合わせてより複雑な条件判定を行うために使用されます。単一の条件では表現できない複合的な条件を設定することで、実用的で柔軟なif文を構築できます。これらの演算子を理解することは、効率的なJavaScriptプログラムを作成する上で不可欠です。
AND演算子(&&)を使った条件判定
AND演算子(&&)は、全ての条件が真である場合のみ全体の条件を真と判定する論理演算子です。複数の条件を同時に満たす必要がある場面で使用され、厳格な条件判定を実現します。
// AND演算子の基本的な使用例
let age = 25;
let hasLicense = true;
let hasExperience = true;
if (age >= 21 && hasLicense && hasExperience) {
console.log("運転資格の全条件を満たしています");
}
// 複数の値の範囲チェック
let score = 85;
if (score >= 80 && score = 100) {
console.log("優秀な成績です");
}
// オブジェクトのプロパティチェック
let user = {name: "田中", email: "tanaka@example.com", verified: true};
if (user.name && user.email && user.verified) {
console.log("ユーザー情報が完全です");
}AND演算子は短絡評価(short-circuit evaluation)の特性を持っており、左側の条件が偽の場合、右側の条件は評価されません。この特性を活用することで、エラーを防いだり処理効率を向上させることができます。
OR演算子(||)を使った条件判定
OR演算子(||)は、いずれか一つでも条件が真であれば全体の条件を真と判定する論理演算子です。複数の選択肢の中から一つでも条件を満たせば処理を実行したい場合に使用されます。
// OR演算子の基本的な使用例
let paymentMethod = "creditcard";
if (paymentMethod === "creditcard" || paymentMethod === "debitcard" || paymentMethod === "paypal") {
console.log("対応している決済方法です");
}
// デフォルト値の設定
let username = "";
let displayName = username || "ゲストユーザー";
console.log(displayName); // "ゲストユーザー"が表示される
// 複数の条件での権限チェック
let userRole = "editor";
if (userRole === "admin" || userRole === "editor" || userRole === "moderator") {
console.log("編集権限があります");
}
// エラーハンドリング
let data = null;
if (!data || data.length === 0) {
console.log("データが存在しません");
}OR演算子もAND演算子と同様に短絡評価を行うため、左側の条件が真の場合は右側の条件は評価されません。この特性は、デフォルト値の設定やnullチェックなどで有効活用されています。
NOT演算子(!)を使った否定条件
NOT演算子(!)は、条件の真偽を反転させる単項演算子です。特定の条件が満たされていない場合に処理を実行したい場面や、真偽値を明示的に反転させたい場合に使用されます。
// NOT演算子の基本的な使用例
let isLoggedIn = false;
if (!isLoggedIn) {
console.log("ログインが必要です");
}
// 配列の存在チェック
let items = [];
if (!items.length) {
console.log("アイテムが存在しません");
}
// 複合条件での使用
let user = {name: "佐藤", isActive: false, isVerified: true};
if (user.isVerified && !user.isActive) {
console.log("認証済みですが、アカウントが無効化されています");
}
// 二重否定による真偽値変換
let value = "hello";
let booleanValue = !!value; // true に変換
if (booleanValue) {
console.log("値が存在します");
}
// falsyな値の判定
let inputData = "";
if (!inputData) {
console.log("入力データが無効です");
}NOT演算子は単純に見えますが、JavaScriptの真偽値変換の仕組みと組み合わせることで、柔軟な条件判定を実現できます。特に、falsyな値(false、0、””、null、undefined、NaN)の判定において非常に有用な演算子となっています。
if文の実践的な使用例

JavaScriptのif文を効果的に活用するためには、実際のコード例を通じて理解を深めることが重要です。ここでは、日常的なWeb開発で頻繁に使用される具体的なif文の実装例を紹介します。基本的な条件分岐から複数条件の組み合わせ、ユーザーとのインタラクションを含む処理まで、段階的に学習していきましょう。
基本的なif文の実装例
最もシンプルなif文の実装例として、数値の判定処理を見てみましょう。以下のコードは、ユーザーの年齢に基づいて適切なメッセージを表示する例です。
let age = 20;
if (age >= 18) {
console.log("成人です");
}
if (age 18) {
console.log("未成年です");
}また、文字列の比較を行う場合の実装例も確認しておきましょう。
let status = "premium";
if (status === "premium") {
console.log("プレミアム会員特典を利用できます");
}
let username = "";
if (username === "") {
console.log("ユーザー名を入力してください");
}これらの例では、JavaScriptのif文における基本的な条件判定の仕組みを理解できます。数値や文字列の比較において、適切な演算子を使用することが重要です。
複数条件を組み合わせた実装例
実際のWebアプリケーション開発では、複数の条件を同時に判定する場面が頻繁に発生します。論理演算子を活用した複合条件の実装例を見てみましょう。
let score = 85;
let attendance = 90;
// AND演算子を使用した複合条件
if (score >= 80 && attendance >= 85) {
console.log("優秀な成績です");
}
// OR演算子を使用した複合条件
if (score 60 || attendance 70) {
console.log("改善が必要です");
}より複雑な条件分岐の例として、ユーザーの権限とアカウント状態を同時に判定する処理を紹介します。
let userRole = "admin";
let isActive = true;
let loginAttempts = 2;
if (userRole === "admin" && isActive && loginAttempts 3) {
console.log("管理者権限でログイン成功");
} else if (userRole === "user" && isActive) {
console.log("一般ユーザーとしてログイン成功");
} else {
console.log("ログインに失敗しました");
}ダイアログボックスを使った条件分岐
ユーザーとのインタラクションを実現するため、JavaScriptのダイアログボックス機能とif文を組み合わせた実装方法を学習しましょう。
確認ダイアログを使用した条件分岐の例:
let userConfirm = confirm("データを削除しますか?");
if (userConfirm) {
console.log("データを削除しました");
// 実際の削除処理
} else {
console.log("削除をキャンセルしました");
}アラートダイアログと組み合わせたエラーハンドリングの例:
let fileSize = 5000000; // 5MB
let maxSize = 2000000; // 2MB
if (fileSize > maxSize) {
alert("ファイルサイズが大きすぎます");
console.log("アップロード処理を中断");
} else {
alert("ファイルのアップロードを開始します");
console.log("アップロード処理を実行");
}ユーザー入力に基づく処理の分岐
Webフォームやプロンプトダイアログからのユーザー入力を処理する際のif文実装例を確認しましょう。これらの例は、実際のWebアプリケーションで頻繁に使用される重要なパターンです。
プロンプトダイアログを使用した入力値判定:
let userInput = prompt("好きな色を入力してください");
if (userInput === null) {
console.log("入力がキャンセルされました");
} else if (userInput === "") {
console.log("何も入力されていません");
} else if (userInput.toLowerCase() === "blue") {
console.log("青色が選択されました");
} else {
console.log(`${userInput}色が選択されました`);
}数値入力の検証を含む実装例:
let ageInput = prompt("年齢を入力してください");
let age = parseInt(ageInput);
if (isNaN(age)) {
alert("正しい数値を入力してください");
} else if (age 0) {
alert("年齢は0以上で入力してください");
} else if (age >= 65) {
console.log("シニア割引が適用されます");
} else if (age >= 18) {
console.log("一般料金が適用されます");
} else {
console.log("学生割引が適用されます");
}これらの実装例を通じて、JavaScriptのif文を様々な場面で効果的に活用する方法を理解できます。実際の開発では、これらのパターンを組み合わせてより複雑な条件分岐処理を構築することになります。
if文のネスト(入れ子)構造
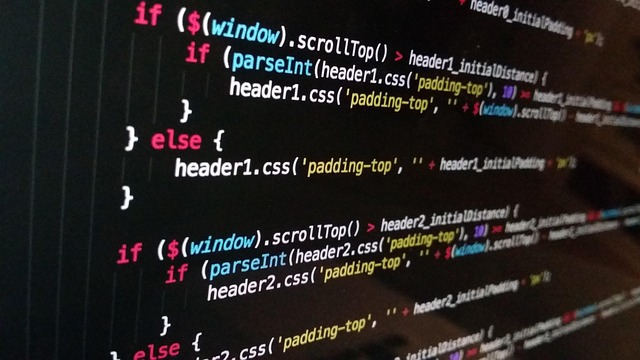
JavaScriptでより複雑な条件判定を行う際、if文を入れ子にして使用することがあります。これをネスト(nest)構造と呼び、複数の条件を段階的にチェックする場面で非常に有用です。ネストしたif文を適切に使いこなすことで、より柔軟で詳細な条件分岐処理を実装できるようになります。
ネストしたif文の書き方
ネストしたif文は、if文の中に別のif文を記述する構造です。基本的な書き方は以下の通りです。
if (条件1) {
if (条件2) {
// 条件1と条件2が両方とも真の場合の処理
} else {
// 条件1が真で条件2が偽の場合の処理
}
} else {
// 条件1が偽の場合の処理
}実際のコード例を見てみましょう。ユーザーの年齢と会員ステータスによって処理を分ける場合です。
let age = 25;
let isPremiumMember = true;
if (age >= 18) {
console.log("成人です");
if (isPremiumMember) {
console.log("プレミアム会員特典をご利用いただけます");
} else {
console.log("一般会員として利用できます");
}
} else {
console.log("未成年のため制限があります");
}さらに複雑なネストも可能です。3層以上のネスト構造を使用する場合の例を示します。
let score = 85;
let hasBonus = true;
let difficulty = "hard";
if (score >= 60) {
if (hasBonus) {
if (difficulty === "hard") {
console.log("ハードモードでボーナス付き合格");
} else {
console.log("イージーモードでボーナス付き合格");
}
} else {
console.log("通常合格");
}
} else {
console.log("不合格");
}ネスト使用時の注意点とベストプラクティス
ネストしたif文は強力な機能ですが、適切に使用しないとコードの可読性や保守性が大幅に低下します。以下に重要な注意点とベストプラクティスをまとめました。
最も重要な注意点は、ネストの深さを制限することです。一般的に、3層を超えるネストは避けるべきとされています。深いネストは以下の問題を引き起こします。
- コードの読みやすさが著しく低下する
- デバッグが困難になる
- ロジックエラーが発生しやすくなる
- メンテナンスコストが増大する
インデント(字下げ)を適切に使用することも重要です。各ネストレベルで一貫したインデントを保つことで、コードの構造を視覚的に把握しやすくなります。
// 良い例:適切なインデント
if (condition1) {
if (condition2) {
if (condition3) {
// 処理
}
}
}
// 悪い例:インデントが不適切
if (condition1) {
if (condition2) {
if (condition3) {
// 処理
}
}
}ベストプラクティスとして、早期リターン(Early Return)パターンの活用をおすすめします。これにより、ネストの深さを減らし、コードをより読みやすくできます。
// ネストが深い例
function checkUserAccess(user) {
if (user) {
if (user.isActive) {
if (user.hasPermission) {
return "アクセス許可";
} else {
return "権限なし";
}
} else {
return "アカウント無効";
}
} else {
return "ユーザー不明";
}
}
// 早期リターンを使用した改善例
function checkUserAccess(user) {
if (!user) {
return "ユーザー不明";
}
if (!user.isActive) {
return "アカウント無効";
}
if (!user.hasPermission) {
return "権限なし";
}
return "アクセス許可";
}また、複雑な条件判定では、論理演算子(&&、||)を活用してネストを減らすことも効果的です。
// ネストを使用した例
if (age >= 18) {
if (hasLicense) {
console.log("運転可能");
}
}
// 論理演算子を使用した簡潔な書き方
if (age >= 18 && hasLicense) {
console.log("運転可能");
}コメントの適切な配置も重要です。特に複雑なネスト構造では、各条件の意図を明確に記述することで、後から読む人(将来の自分を含む)がコードを理解しやすくなります。
if文の代替手法と最適化

JavaScriptのif文は条件分岐の基本的な構文ですが、場面によってはより効率的で読みやすい代替手法が存在します。コードの可読性とパフォーマンスの向上を目指すために、適切な書き方とテクニックを身につけることが重要です。
三項演算子を使った簡潔な書き方
三項演算子(条件演算子)は、シンプルなif-else文を一行で表現できる便利な記法です。「条件 ? 真の場合の値 : 偽の場合の値」という構文で、コードを大幅に短縮できます。
// 通常のif文
let message;
if (score >= 60) {
message = "合格";
} else {
message = "不合格";
}
// 三項演算子を使用
let message = score >= 60 ? "合格" : "不合格";三項演算子は変数への代入や関数の引数として直接使用でき、特にReactなどのフレームワークでのJSX記述において重宝されます。ただし、複雑な条件や処理が多い場合は、可読性を保つために通常のif文を選択することが推奨されます。
ショートサーキット評価の活用方法
JavaScriptの論理演算子(&&、||)はショートサーキット評価という特性を持ち、これを活用することで簡潔なif文の代替表現が可能になります。この手法は、条件チェックと処理実行を同時に行いたい場合に特に有効です。
// AND演算子(&&)を使った条件実行
user && user.name && console.log(user.name);
// OR演算子(||)を使ったデフォルト値設定
const username = user.name || "ゲスト";
// 従来のif文との比較
if (user && user.name) {
console.log(user.name);
}ショートサーキット評価は、オブジェクトの存在チェックやデフォルト値の設定において、コードを劇的に短縮します。特にnullやundefinedのチェックが頻繁に必要なJavaScriptにおいて、この技法は実用的価値が高いといえます。
switch文との使い分け
複数の条件分岐がある場合、if文よりもswitch文の方が適している場合があります。特に同一の変数に対する複数の値比較において、switch文はより読みやすく、パフォーマンスも向上する可能性があります。
// 多重if文
if (dayOfWeek === 1) {
return "月曜日";
} else if (dayOfWeek === 2) {
return "火曜日";
} else if (dayOfWeek === 3) {
return "水曜日";
} // ...続く
// switch文での書き換え
switch (dayOfWeek) {
case 1:
return "月曜日";
case 2:
return "火曜日";
case 3:
return "水曜日";
default:
return "不明";
}switch文は分岐が3つ以上の場合に特に威力を発揮し、コードの構造も一目で理解しやすくなります。ただし、複雑な条件や範囲指定が必要な場合は、if文の方が適切な選択となります。
if文を見やすくするテクニック
if文の可読性を向上させるためには、いくつかの実践的なテクニックがあります。これらの手法を適用することで、保守性の高いコードを作成できます。
- ガード句の活用:早期リターンによってネストの深さを減らし、メインロジックを明確にする
- 変数による条件の明確化:複雑な条件式を意味のある変数名に置き換える
- 否定条件の回避:可能な限り肯定的な条件で記述して理解しやすくする
// 改善前:ネストが深い
function processUser(user) {
if (user) {
if (user.age >= 18) {
if (user.verified) {
// メイン処理
}
}
}
}
// 改善後:ガード句使用
function processUser(user) {
if (!user) return;
if (user.age 18) return;
if (!user.verified) return;
// メイン処理(見やすい)
}これらのテクニックを組み合わせることで、if文をより効率的かつ読みやすく記述できます。適切な手法選択により、コードの品質向上とメンテナンス効率の改善が実現できます。
if文使用時の注意点とトラブル対策
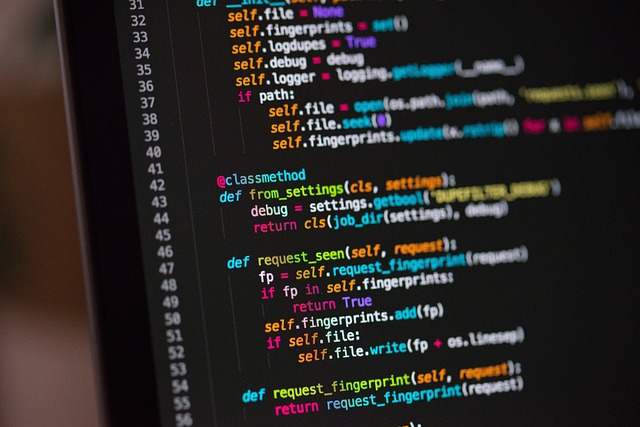
JavaScriptのif文を使用する際には、予期しない動作を避けるためにいくつかの重要な注意点があります。特に初心者が陥りやすい罠や、経験豊富な開発者でも見落としがちなポイントを理解することで、より堅牢なコードを書くことができます。
false判定される値の理解
JavaScriptにおいてif文の条件判定でfalsy(偽と判定される)値を正しく理解することは極めて重要です。これらの値は条件文でfalseとして扱われ、予期しない動作の原因となることがあります。
JavaScriptでfalse判定される値は以下の通りです:
false– ブール値のfalse0– 数値のゼロ-0– 負のゼロ0n– BigIntのゼロ""– 空文字列null– null値undefined– undefined値NaN– Not a Number
// 注意が必要な例
let userInput = "0"; // 文字列の"0"
if (userInput) {
console.log("入力があります"); // これは実行される
}
let numericInput = 0; // 数値の0
if (numericInput) {
console.log("入力があります"); // これは実行されない
}この違いを理解せずにコーディングすると、想定外の動作が発生する可能性があります。特にユーザー入力を処理する際は、文字列と数値の違いに注意が必要です。
スコープに関する注意点
if文内で宣言する変数のスコープは、使用する宣言方法によって大きく異なります。これを理解していないと、変数が予期しない範囲で使用されたり、逆に必要な場所で使用できなかったりする問題が発生します。
var、let、constのスコープの違いは以下の通りです:
// var の場合(関数スコープ)
if (true) {
var varVariable = "var変数";
}
console.log(varVariable); // "var変数" - アクセス可能
// let の場合(ブロックスコープ)
if (true) {
let letVariable = "let変数";
}
// console.log(letVariable); // ReferenceError - アクセス不可
// const の場合(ブロックスコープ)
if (true) {
const constVariable = "const変数";
}
// console.log(constVariable); // ReferenceError - アクセス不可モダンなJavaScript開発では、letとconstの使用が推奨されています。これにより、より予測可能で安全なコードを書くことができます。
実行順序による処理の違い
if文の条件判定は上から順番に評価されるため、条件の記述順序によって処理結果が大きく変わることがあります。特に複数の条件が重複する可能性がある場合、意図しない結果を招く恐れがあります。
let score = 85;
// 問題のある順序
if (score >= 0) {
console.log("有効なスコア");
} else if (score >= 80) {
console.log("優秀"); // この条件は永久に実行されない
} else if (score >= 60) {
console.log("合格"); // この条件も永久に実行されない
}
// 正しい順序
if (score >= 80) {
console.log("優秀"); // これが実行される
} else if (score >= 60) {
console.log("合格");
} else if (score >= 0) {
console.log("不合格");
}このように、より具体的な条件を先に、より一般的な条件を後に配置することが重要です。論理演算子を使用する際も、短絡評価(ショートサーキット)の特性を理解して適切な順序で条件を配置しましょう。
コード省略時のルールと制限
JavaScriptのif文では、波括弧({})を省略して一行で記述することが可能ですが、これには厳格なルールと制限があります。省略記法を誤って使用すると、予期しない動作やバグの原因となります。
波括弧省略時の基本ルール:
// 正しい省略記法
if (condition) console.log("実行される");
// 複数行になる場合は波括弧が必要
if (condition)
console.log("1行目");
console.log("2行目"); // この行は条件に関係なく常に実行される特に注意が必要なのは、後からコードを追加する際の問題です:
// 最初のコード
if (isValid) console.log("検証成功");
// 後から追加(間違った例)
if (isValid) console.log("検証成功");
saveData(); // この行は常に実行される
// 正しい修正
if (isValid) {
console.log("検証成功");
saveData(); // 条件内で実行される
}保守性とコードの可読性を考慮すると、常に波括弧を使用することが推奨されています。多くの開発チームでは、一行の場合でも波括弧を必須とするコーディング規約を採用しています。
if文のコーディングベストプラクティス

JavaScriptでif文を効果的に活用するためには、単に正しく動作するコードを書くだけでなく、読みやすさ、保守性、パフォーマンスを考慮した実装が重要です。優れたif文の実装は、チーム開発における生産性向上や長期的なメンテナンス性の確保に直結します。
読みやすいif文の書き方
読みやすいif文を書くためには、適切な命名規則とコードの構造化が不可欠です。条件式には意味が明確な変数名や関数名を使用し、複雑な条件は適切に分割して可読性を高めましょう。
まず、条件式には説明的な変数名を使用することが重要です。以下のような書き方を心がけることで、コードの意図が明確になります。
// 悪い例
if (user.age >= 18 && user.status === 'active' && user.verified) {
// 処理
}
// 良い例
const isAdult = user.age >= 18;
const isActiveUser = user.status === 'active';
const isVerifiedUser = user.verified;
const canAccessContent = isAdult && isActiveUser && isVerifiedUser;
if (canAccessContent) {
// 処理
}また、条件式が複雑になる場合は、関数として分離することで可読性を向上させることができます。
// 複雑な条件を関数化
function isEligibleForPremium(user) {
return user.subscriptionType === 'premium' &&
user.paymentStatus === 'paid' &&
user.accountAge > 30;
}
if (isEligibleForPremium(user)) {
showPremiumFeatures();
}ネストした条件分岐では、早期リターン(ガード句)を活用して、コードの階層を浅く保つことが推奨されます。これにより、メインロジックが明確になり、読みやすさが向上します。
パフォーマンスを考慮した実装方法
if文のパフォーマンス最適化では、条件の評価順序と不要な計算の回避が重要なポイントとなります。JavaScript エンジンの特性を理解し、効率的な条件評価を実現することで、アプリケーション全体のパフォーマンス向上に貢献できます。
条件の評価順序では、最も可能性の高い条件を最初に配置することで、短絡評価(ショートサーキット)の恩恵を受けられます。
// パフォーマンスを考慮した条件順序
if (commonCondition && expensiveFunction() && rareCondition) {
// 処理
}
// 使用頻度の高い条件を最初に配置
if (user.isActive && user.hasPermission('read') && calculateComplexScore(user) > 80) {
// 処理
}重い処理を含む条件式では、結果をキャッシュすることでパフォーマンスを向上させることができます。
// 計算結果のキャッシュ
const userScore = calculateUserScore(user); // 一度だけ計算
if (userScore > 100) {
handleHighScore();
} else if (userScore > 50) {
handleMediumScore();
} else {
handleLowScore();
}また、オブジェクトのプロパティアクセスが頻繁な場合は、事前に変数に格納することで処理速度を向上させられます。
// プロパティアクセスの最適化
const userAge = user.profile.personalInfo.age; // 一度だけアクセス
if (userAge >= 18 && userAge 65) {
// 処理
}保守性を高めるコーディング規約
長期的な開発において保守性の高いif文を実装するには、一貫したコーディング規約の遵守と、将来の変更に対する柔軟性の確保が必要です。明確なガイドラインに従ってコードを書くことで、チーム全体の開発効率が向上します。
定数やEnum的な値を使用することで、条件の変更に対する保守性を高めることができます。
// 定数を使用した保守性の向上
const USER_ROLES = {
ADMIN: 'admin',
MODERATOR: 'moderator',
USER: 'user'
};
const USER_STATUS = {
ACTIVE: 'active',
INACTIVE: 'inactive',
SUSPENDED: 'suspended'
};
if (user.role === USER_ROLES.ADMIN && user.status === USER_STATUS.ACTIVE) {
// 管理者権限の処理
}複雑な条件ロジックは、専用の関数やクラスとして分離し、単一責任の原則に従って実装することが重要です。
// 条件ロジックの分離
class UserPermissionChecker {
static canEditContent(user, content) {
return user.role === USER_ROLES.ADMIN ||
(user.role === USER_ROLES.MODERATOR && content.category !== 'sensitive') ||
(content.author === user.id && user.status === USER_STATUS.ACTIVE);
}
}
if (UserPermissionChecker.canEditContent(currentUser, selectedContent)) {
enableEditMode();
}条件分岐にコメントを適切に配置し、ビジネスロジックの背景や制約を明記することで、将来のメンテナンス作業を効率化できます。
// ビジネスルールに基づくコメント
if (order.amount > 10000) {
// 高額注文は手動承認が必要(コンプライアンス要件)
requireManualApproval(order);
} else if (customer.riskScore > 70) {
// リスクスコアが高い顧客は追加確認が必要
requestAdditionalVerification(customer);
} else {
// 通常の注文処理
processOrder(order);
}



