この記事では、JavaScriptの非同期処理に欠かせないasync/await構文の基本から応用までを解説します。Promiseとの違いや正しい使い方、エラー処理やawait忘れ防止策を学ぶことで、可読性の高い堅牢なコードを書く力が身につきます。
目次
await演算子とは
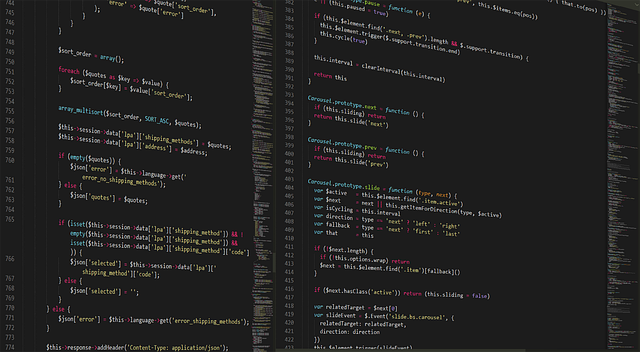
awaitの基本構文
await演算子は、JavaScriptにおける非同期処理をより直感的に記述するための構文です。特にasync関数の中で使用され、Promiseが解決(fulfilled)または拒否(rejected)されるまで処理を一時停止します。これにより、非同期処理をまるで同期処理のように書けるのが大きな特徴です。
基本構文は次のようになります。
const result = await someAsyncFunction(); この場合、someAsyncFunction()が返すPromiseが解決されると、その戻り値がresultに代入されます。もしPromiseが拒否された場合は、例外が発生し、通常のtry...catch構文で扱うことができます。
重要なのは、await演算子はasync関数の外では使用できないという点です。これはJavaScriptの仕様として定義されており、グローバルスコープで使用しようとすると構文エラーになります。
awaitが扱う値(Promise・Thenable・通常値)
awaitが待機できるのはPromiseだけと思われがちですが、実際にはさらに柔軟に動作します。以下の3種類の値を扱うことができます。
- Promiseオブジェクト:最も一般的なケースです。完了を待ち、解決値を返します。
- Thenableオブジェクト:
then()メソッドを持つオブジェクトであれば、Promiseと同様に扱われます。 - 通常値(非Promise):Promiseでない値を渡した場合、
awaitは即時にその値を返します。
この挙動により、開発者は値の種類を常に判定する必要がなく、非同期・同期処理を統一的に扱うことができます。特にAPI通信やデータ取得などで可読性・保守性が大幅に向上します。
awaitの戻り値と例外の扱い
awaitの戻り値は、その対象となるPromiseの最終的な解決値です。たとえば、await fetchData()の結果がオブジェクトであれば、そのオブジェクトを直接受け取ることができます。
一方、Promiseが拒否された場合(rejectされた場合)は、awaitはその拒否理由を例外としてスローします。このため、次のようにtry...catch構文と組み合わせて使うのが一般的です。
try {
const data = await fetchData();
} catch (error) {
console.error(error);
}
このように例外処理を明示的に書けることで、従来の.then().catch()構文よりも読みやすく、エラーハンドリングが容易になります。
awaitがもたらす実行フローの変化
awaitを利用することで、JavaScriptの非同期実行モデルに一時的な「停止点」を設けることが可能になります。これはスレッドをブロックするわけではなく、Promiseが解決するまで関数の残りの処理を中断し、完了後に再開する挙動です。
その結果、非同期処理をチェーンでつなぐ必要がなくなり、コードは上から下に自然に流れるようになります。また、複数のawaitを順番に記述することで、直列的な非同期処理の手続きをシンプルに表現できるようになります。
この実行フローの変化こそが、async/await構文がPromiseベースの非同期処理を抜本的に改善した理由の一つと言えるでしょう。
async/awaitの基礎
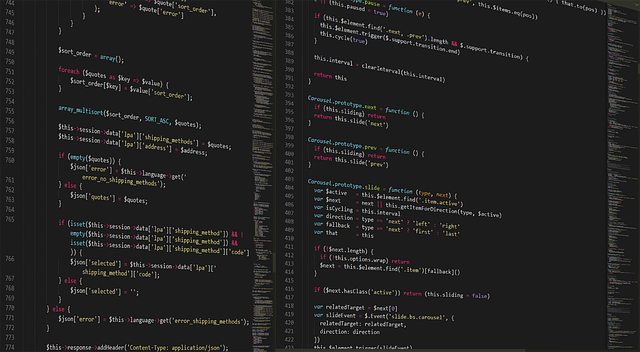
async関数の役割と仕組み
JavaScriptにおけるasync関数は、非同期処理をよりシンプルで直感的に記述するための構文です。asyncキーワードを付与することで、その関数は常にPromiseを返すようになります。関数内でawaitを使用し、非同期処理の完了を待機することで、従来のコールバック構文や.then()チェーンよりも可読性の高いコードを実現できます。
例えば、APIデータを取得してから処理するようなケースでは、async関数を利用することで同期的なフローに近い記述が可能になります。この仕組みにより、非同期の複雑な制御構文を意識せずに、手続き的に処理を進められるのがasync/awaitの大きな強みです。
Promiseとの違いと使い分け
Promiseも非同期処理を扱うための仕組みですが、複雑な処理が連鎖する場合に.then()が多重化し、可読性が低下することがあります。一方、async/awaitはPromiseをベースとしながら、コードの構造を直線的に整理できるため、処理の流れが把握しやすくなります。
ただし、すべてのケースでawaitを使えば良いわけではありません。複数の非同期処理を同時に実行したい場合は、Promise.all()のような並列実行の仕組みを用いた方が効率的です。つまり、「逐次処理が必要なときにはasync/await」、「同時処理が求められるときにはPromise」といった使い分けがポイントとなります。
async/await導入の背景
JavaScriptの非同期処理は、もともとコールバック関数で実装されていました。しかし、ネスト構造が深くなりやすい「コールバック地獄」と呼ばれる問題が発生し、保守性の低下が課題となっていました。その後登場したPromiseにより一定の改善は見られましたが、さらに自然な記述を求める声が多く、ECMAScript 2017(ES8)でasync/awaitが正式に導入されました。
この仕様により、非同期処理が「同期処理のように」書けるようになり、学習コストを下げつつ高品質なコードの実装が可能になりました。つまり、async/awaitは開発者体験(DX: Developer Experience)を大幅に向上させる構文なのです。
非同期処理を直感的に書ける理由
async/awaitが直感的と言われる理由は、プログラムの実行の流れが「上から下へ」読みやすくなる点にあります。従来のPromiseチェーンでは処理の順序関係を追うのが難しくなりがちでしたが、awaitを使うことで、「待ってから次へ進む」という自然な構文で記述できます。
加えて、例外処理にもtry...catch構文を利用できるため、同期処理と同様の感覚でエラーハンドリングが可能です。これにより、非同期特有の煩雑さが軽減され、読み手にも理解しやすいコードが書けます。結果として、より安全で保守しやすいJavaScriptアプリケーション開発が実現します。
awaitの書き方と実践例
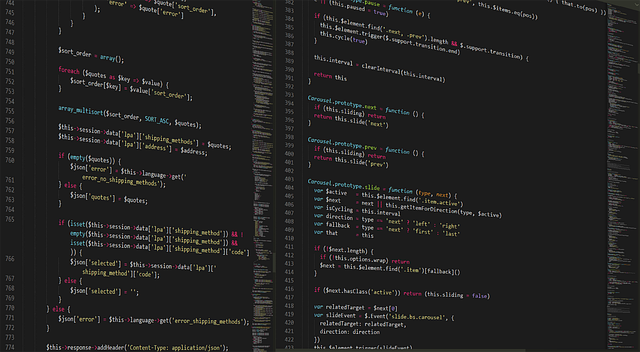
基本の使い方
JavaScriptにおけるawaitは、非同期処理を直感的かつ同期処理のように記述できる強力な構文です。
使用する際のポイントは、必ずasync関数内でのみ利用できるという点です。
awaitを付与することで、Promiseが解決(fulfilled)または拒否(rejected)されるまで次の処理を一時停止させます。
async function fetchData() {
const response = await fetch('https://api.example.com/data');
const json = await response.json();
console.log(json);
}
このように、awaitを活用することで、複雑な.then()の連鎖を書かずに済み、処理の流れを追いやすくなります。
特にAPIリクエストやファイル読み込みなど、非同期処理が多いWeb開発では可読性と保守性の向上に役立ちます。
Promiseの完了を待機する処理例
awaitはPromiseの完了を待つために設計されています。Promiseを関数から返す場合、awaitを使用することで値を直接受け取ることができます。以下は、データベースから情報を取得する例です。
function getUserData() {
return new Promise(resolve => {
setTimeout(() => resolve({ id: 1, name: 'Taro' }), 1000);
});
}
async function showUser() {
const user = await getUserData();
console.log(user.name); // "Taro"
}
上記の例では、getUserData()の結果が返るまでshowUser()関数内の次の処理は実行されません。
awaitによって処理の順序を明確に制御できるため、非同期処理間の依存関係を安全に扱うことができます。
複数の非同期処理を同時に実行する
複数のPromiseを並行して実行したい場合、awaitを直列的に使うと全体の処理速度が低下してしまいます。
そのため、複数の非同期処理を効率的に扱うための手法として、Promise.all()やfor await...ofが用いられます。
Promise.all()による並列処理
Promise.all()は複数のPromiseを同時に実行し、すべての完了を待って結果をまとめて返す方法です。
通信や計算などを同時に進めたいケースで大幅な時間短縮が見込めます。
async function fetchAll() {
const [posts, comments, users] = await Promise.all([
fetch('/api/posts'),
fetch('/api/comments'),
fetch('/api/users')
]);
console.log(posts.status, comments.status, users.status);
}
このコードでは3つのデータ取得が並行して行われ、最も時間のかかる処理の完了を待つだけで済みます。
JavaScript awaitとPromise.all()の組み合わせにより、効率的で高速な非同期処理が実現できます。
for await…ofによる非同期反復
非同期で取得される複数のデータを順番に処理したい場合には、for await...of構文が便利です。
Promiseの配列や非同期イテレーターを順に処理しつつ、各要素の完了を待ちながらループを進めることができます。
async function processData(promises) {
for await (const result of promises) {
console.log(result);
}
}
const dataPromises = [
Promise.resolve('A'),
Promise.resolve('B'),
Promise.resolve('C')
];
processData(dataPromises);
この方法では各非同期処理が完了するたびに順番に結果を受け取ることができ、
APIレスポンスなどのストリーム処理や逐次ダウンロードの実装に適しています。
for await…ofを使えば、非同期処理を読みやすくシンプルに構築することができます。
非同期処理のエラーハンドリング
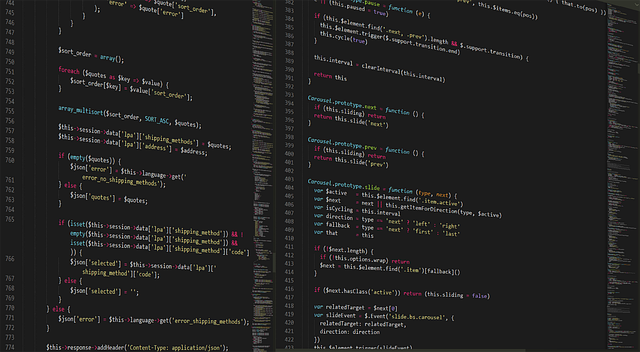
try…catchを使った例外処理
JavaScriptのawaitを用いた非同期処理では、エラーを安全に扱うためにtry...catch構文が重要な役割を果たします。特に、awaitは非同期関数(async function)の中で使用されることが多く、awaitが一時停止するPromiseで例外が発生すると、自動的に例外としてスローされます。そのため、try...catchを併用することで、同期処理と同様にエラーを検知し、明確に制御することができます。
async function fetchData() {
try {
const response = await fetch('https://example.com/data');
const json = await response.json();
console.log(json);
} catch (error) {
console.error('データ取得に失敗しました:', error);
}
}
このように書くことで、ネットワークエラーなどによってPromiseが拒否された際も、スクリプト全体が止まることなく安全に処理を続行できます。
拒否されたPromiseの扱い方
awaitはPromiseが正常に解決されるまで待機しますが、Promiseが拒否(reject)されると例外が発生します。これを正しく処理しないと、アプリケーションの予期せぬ挙動につながることがあります。
代表的な方法として次の2つがあります。
try...catchで明示的に処理する: 上の例のようにawaitを囲むことで、安全なエラーハンドリングが可能です。- Promiseの
.catch()で対応する: 単純な非同期呼び出しや、非同期関数外でのハンドリングが必要な場合に有効です。
fetchData()
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.error('Promiseで処理されたエラー:', error));
awaitを使用する場合でも、状況によっては両方の方法を組み合わせることで耐障害性の高い設計が可能になります。
await内でのエラー再スロー
await内でキャッチしたエラーを再度外部に伝播させたい場合は、throwキーワードを使って再スロー(再送出)します。再スローにより、上位のエラーハンドラーやグローバルエラー監視ロジックに処理を委ねることができます。
async function getUserData() {
try {
const data = await fetch('https://example.com/user');
return await data.json();
} catch (error) {
console.error('ユーザーデータ取得中にエラー:', error);
throw error; // エラーを再スロー
}
}
再スローを行うことで、API呼び出し元がawaitを使用していても一貫したエラーハンドリングが可能となります。システム全体の信頼性を高めるうえで、このパターンは非常に有効です。特に大規模アプリケーションでは、共通のエラー処理メカニズムを構築する際に、この再スローロジックを活用することが推奨されます。
async/awaitの活用事例
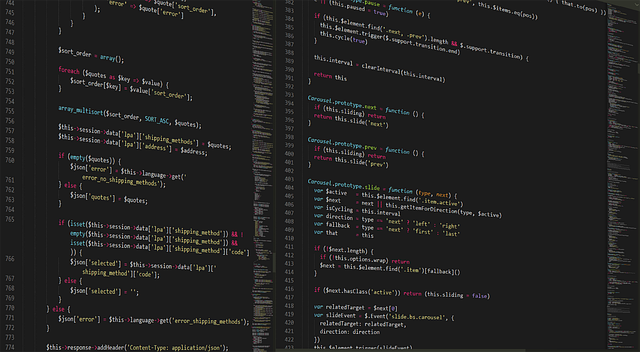
データ取得・送信処理を簡潔に記述する
Webアプリケーションでは、APIからデータを取得したり、サーバーにデータを送信したりといった非同期処理が頻繁に発生します。これらの処理をより直感的かつ可読性の高いコードで記述できるのが、javascript awaitを活用したasync/await構文の大きな強みです。
従来のPromiseチェーンでは、.then()や.catch()を多用するため、処理の流れを追いにくくなる場合があります。しかし、awaitを使うことで、まるで同期処理のようにコードを上から下に自然に読み進めることができ、非同期処理であってもロジックを簡潔に整理できます。
例えば、APIからユーザー情報を取得し、サーバー側へ更新リクエストを送信する処理を考えてみましょう。awaitを使えば、レスポンスの完了を待ってから次の処理へ安全に移行でき、エラー発生時のハンドリングもtry...catchで一元管理できます。
このようにjavascript awaitを活用することで、ネットワーク通信を伴う複雑な非同期コードをよりシンプルかつ保守しやすい形にできます。
Promiseベースのコードを書き換える例
Promiseを使ったコード例
まず、Promiseチェーンを活用したデータ取得と送信処理の例を示します。以下のコードでは、ネストされた.then()によって処理の流れがやや複雑になっています。
// Promiseを使ったデータ取得と送信例
fetch('https://api.example.com/user')
.then(response => response.json())
.then(user => {
user.active = true;
return fetch('https://api.example.com/update', {
method: 'POST',
body: JSON.stringify(user),
headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
});
})
.then(result => result.json())
.then(data => console.log('更新結果:', data))
.catch(error => console.error('エラー:', error));
このように、処理の順序や依存関係が増えるほどコードが入れ子になり、可読性や保守性が低下しやすくなります。
async/awaitでリファクタリングした例
上記のコードをasync/await構文で書き換えると、見通しのよい構造に改善できます。
// async/awaitを使った同等の処理
async function updateUser() {
try {
const response = await fetch('https://api.example.com/user');
const user = await response.json();
user.active = true;
const updateResponse = await fetch('https://api.example.com/update', {
method: 'POST',
body: JSON.stringify(user),
headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
});
const result = await updateResponse.json();
console.log('更新結果:', result);
} catch (error) {
console.error('エラー:', error);
}
}
updateUser();
このようにawaitを用いることで、非同期処理をまるで同期処理のように順序立てて記述できます。エラーハンドリングもtry...catchでまとめて対応可能となり、コード全体が明瞭になります。
結果として、データ取得や送信などの通信処理ロジックをスッキリと表現でき、保守・拡張のしやすい設計につながります。
よくあるミスと防止策
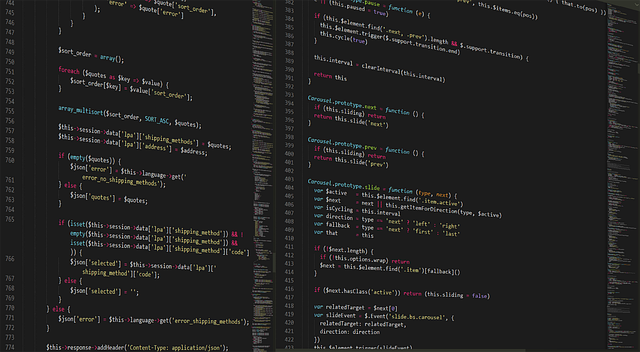
awaitの書き忘れを防ぐ方法
JavaScriptで非同期処理を行う際、awaitの書き忘れはもっとも頻発するミスの一つです。Promiseを返す関数を呼び出した際にawaitを付け忘れると、意図せず未解決のPromiseオブジェクトがそのまま返り、処理が先に進んでしまいます。その結果、値が正しく取得できなかったり、画面表示が更新されないといった不具合が生じます。
このような書き忘れを防ぐためには、いくつかの工夫が有効です。
- 命名規則で明示する:非同期関数名の末尾に
Asyncを付けることで、「この関数はPromiseを返す」という意識を開発者に促せます。例:fetchDataAsync()。 - コードレビュー時にチェック:非同期処理を行う箇所を重点的に確認し、
awaitの漏れを見落とさないようにします。 - TypeScriptの活用:静的型付けを導入している場合、戻り値が
Promise型であることを検知できるため、awaitを記述していない箇所を早期に発見できます。
これらの対策を併用することで、構文エラーにならない範囲で発生する「awaitの書き忘れ」をより確実に防ぐことができます。
ESLintルールによる検知
静的解析ツールであるESLintを利用すれば、JavaScriptにおけるawaitの使い忘れを自動的に検知できます。特に有名なのがeslint-plugin-promiseやeslint-plugin-async-awaitなどのプラグインで、Promiseを返す関数呼び出しにawaitが付いていない場合に警告を表示できます。
ESLintを導入するメリットは、チーム全体でコーディングルールを統一できる点にあります。たとえば、no-return-awaitやrequire-awaitなどのルールを適用すれば、「不要なawait」や「await漏れ」の両方を自動チェックできます。
{
"rules": {
"require-await": "error",
"no-return-await": "warn"
}
}
このように設定しておくことで、開発者が手動で確認する手間を減らし、コード品質の一貫性を保ちながらミスを自動的に防止することが可能です。
非同期関数外でawaitを誤用しないための注意点
awaitはasync関数内でのみ使用可能であり、非同期関数外で誤って使用すると構文エラーになります。とくに初学者に多いのが、通常の関数やスクリプトのトップレベルでawaitを書いて実行時にエラーを発生させてしまうケースです。
この問題を防ぐためには、次のポイントを意識するとよいでしょう。
- 常に
async関数で囲む:awaitを使う処理は関数化し、async functionまたはconst fn = async () =>形式で定義します。 - トップレベルawait対応の確認:Node.jsやブラウザ環境の対応を把握し、トップレベルawaitが使用できる場合のみ利用します。
- コードの構造を整理:awaitの使用箇所を明確に分離し、処理の流れを関数単位で把握できるようにしておくと、誤用を減らせます。
非同期関数外でのawait誤用は構文上すぐに検出される一方、チーム開発時には他メンバーの環境によって挙動が異なる場合があります。そのため、開発環境全体で統一したルール設定とレビュー体制を整えることが重要です。
パフォーマンスとベストプラクティス
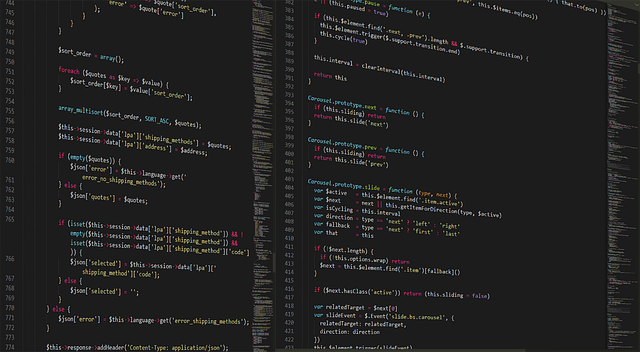
同期・非同期処理の使い分け指針
JavaScriptのawaitは非同期処理を直感的に扱うための強力な構文ですが、あらゆるケースで使用すれば良いというわけではありません。適切な使い分けを理解することが、パフォーマンスと可読性の両立につながります。
まず、UIの描画やイベント処理のようにリアルタイム性が求められる場面では、可能な限り非同期処理を優先すべきです。長時間ブロックされるコードを同期的に実行すると、ユーザー体験が著しく低下します。一方で、小規模なロジックや単純な数値計算のように結果を即時に得られる処理であれば、同期的に実行してもパフォーマンスへの影響は少なく、コードもシンプルに保てます。
基本的な指針としては、「非同期が必須の処理」にのみawaitを使うことです。API通信、ファイル入出力、タイマー処理など、明確に待機が発生するケースに限定することで、無駄な待機時間を発生させず効率的なコード設計が可能となります。
不要なawaitを避ける最適化
パフォーマンスを意識したコード設計では、不要なawaitの乱用を避けることが非常に重要です。awaitを無条件に挿入すると、処理が逐次的に実行され、実行速度が低下してしまう可能性があります。
次のような対処が効果的です:
- 依存関係のない複数の非同期処理は、
Promise.all()などを使って並列実行する。 - 戻り値を利用しない非同期関数の結果はawaitせず、バックグラウンドで進行させる。
- ループ処理の内部でawaitを多用せず、非同期処理を配列化して一括で制御する。
特に、awaitを毎回ループ内に記述すると逐次処理となり、全体の待機時間が大きくなります。非同期処理の特性を理解し、効率よくawaitを配置することが高パフォーマンスコードの鍵です。
コードの可読性と保守性を高めるポイント
パフォーマンス最適化と同時に考慮すべきなのが、可読性と保守性です。awaitを適切に配置することで、処理の流れを直感的に把握しやすくなりますが、過剰に入れるとかえって読みづらいコードになります。
開発チームで共有しやすいコードを維持するために、以下のポイントを意識しましょう:
- 関数や処理単位ごとに「どの非同期処理を待機すべきか」をコメントで明示する。
- 命名規則として、非同期関数には
asyncという接頭辞をつけるなど、可視的に区別できるようにする。 - エラーハンドリングをtry…catchで統一し、awaitを使った箇所での例外伝播を明確にする。
これらを実践することで、非同期処理特有の複雑さを抑えつつ、高いパフォーマンスと安全性を両立できるコードに仕上げることができます。結果として、チーム全体の開発効率と信頼性が向上します。
ブラウザーおよび環境対応状況
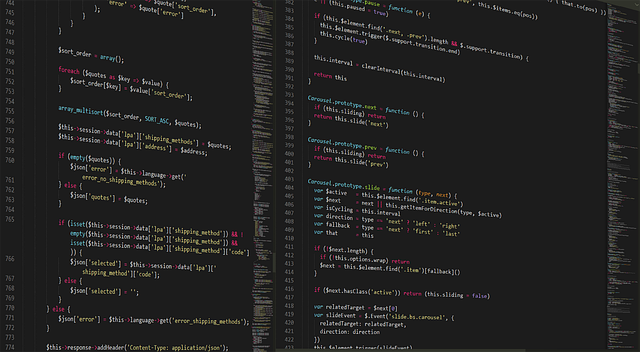
JavaScriptのバージョン別対応
await演算子は、JavaScriptにおける非同期処理をより直感的に記述できる構文として、ECMAScript 2017(ES8)で正式に導入されました。このバージョン以降では、async / await構文が標準機能としてサポートされており、従来のPromiseチェーンを大幅に簡潔化できる点が特徴です。
主要ブラウザーでの対応状況を見てみると、以下のように比較的早い段階からサポートが進みました。
| ブラウザー | 対応バージョン | 対応開始時期 |
|---|---|---|
| Google Chrome | ver.55以降 | 2016年12月 |
| Firefox | ver.52以降 | 2017年3月 |
| Microsoft Edge(Chromium版) | ver.79以降 | 2020年1月 |
| Safari | ver.11以降 | 2017年9月 |
これらの対応状況からも分かるように、現在の主要ブラウザー環境ではすでにawait構文が標準機能として安心して利用可能です。ただし、古いバージョンのブラウザー(特にInternet Explorer)では非対応のため、トランスパイルやポリフィルを通じてES5互換コードに変換する必要があります。
Node.js環境での動作サポート
サーバーサイドJavaScriptを実行するNode.jsでも、await演算子は早期にサポートが進みました。Node.jsではバージョン7.6以降でasync/awaitがデフォルトで使用可能になり、ES2017の仕様に基づく非同期処理がサポートされています。
特にNode.js 8以降ではV8エンジンの更新によりパフォーマンス面が改善され、awaitを含む非同期処理の動作がより高速かつ安定しました。近年では、モジュール形式(ESM)の導入に伴い、トップレベルでもawaitを使用できるトップレベルawaitが追加され、より柔軟なスクリプト実装が可能となっています。
現行のLTS(Long-Term Support)バージョンのNode.jsでは、awaitはすべての環境で正式サポートされており、APIリクエスト処理やファイルI/O、DB操作など、さまざまな非同期処理において広く活用されています。開発者は、プロジェクトのNode.jsバージョンを確認し、ESMモジュール構文を採用することで、最新機能を安全かつ効率的に利用できるでしょう。
まとめ
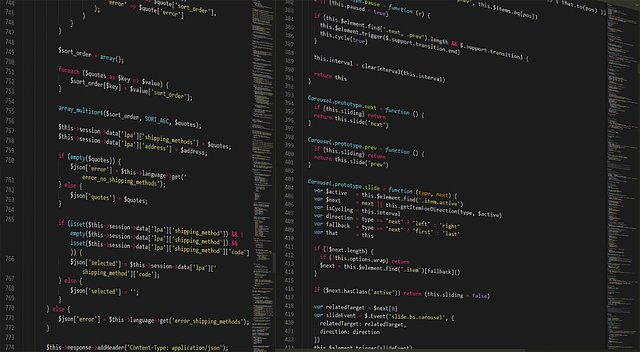
async/awaitを使うメリットの整理
JavaScriptにおけるasync/await構文は、複雑な非同期処理をシンプルに記述できる強力な仕組みです。これにより、非同期処理特有の「コールバック地獄」やPromiseチェーンの可読性の低下を防ぎ、従来よりも直感的で同期的なコードフローを実現できます。
特に次のようなメリットがあります。
- 可読性の向上:非同期処理をまるで同期処理のように書けるため、複雑なネスト構造を回避できます。
- 保守性の向上:関数の流れが明確になるため、後からの修正や機能追加が容易になります。
- エラーハンドリングの一元化:
try...catch構文を活用することで、Promiseチェーンの.catch()よりもスムーズに例外処理を記述できます。 - 非同期ロジックの整理:API通信やファイル読み込みなど、実行順序が重要な処理を制御しやすくなります。
これらの利点により、javascript awaitは現代的なWeb開発やサーバーサイドJavaScriptでも標準的な手法として定着しています。
今後のJavaScript非同期処理の展望
JavaScriptの非同期処理はasync/await登場以降、コード品質と開発効率の両面で飛躍的に向上しました。今後はこれに加え、さらに高度な並列処理やストリーム処理と組み合わせる流れが一般化していくと考えられます。
例えば、Promise.allSettled()やfor await...of、AsyncIteratorなどの仕組みはすでに進化した非同期パターンを提供しており、Web APIやNode.jsでも積極的に活用されています。将来的には、より効率的な非同期I/O最適化やタスクスケジューリングが進むことで、システム全体のパフォーマンス改善にも寄与するでしょう。
最終的に、JavaScript開発者はawaitの概念を理解し、場面に応じて適切に活用することで、より堅牢でスムーズなアプリケーションを実現できます。非同期処理の新たな進化を意識しつつ、async/awaitを中心とした開発スタイルを磨いていくことが今後の鍵となるでしょう。




