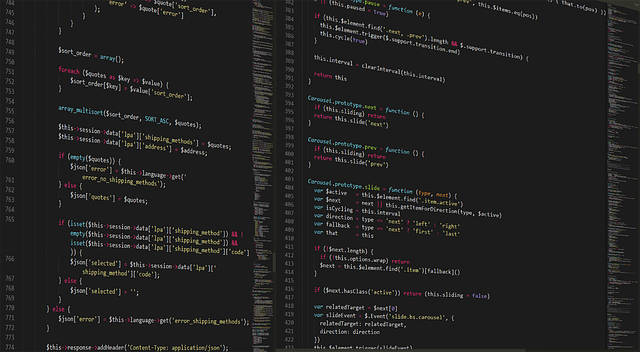C++17の言語/標準ライブラリの追加・削除点(構造化束縛、string_view、filesystem等)を整理。MSVCの/std・/Zc:noexceptTypes、VS2017の対応、CEDECの動向やC++20との接点、学習書も紹介。移行判断と実装方針、トラブル対応に役立つ。
目次
- 1 C++17の概要と位置づけ
- 2 言語仕様のアップデート(C++17)
- 3 標準ライブラリの更新点(C++17)
- 4 C++17対応のビルド設定とツールチェーン
- 5 参考リンク・追加ドキュメント
C++17の概要と位置づけ

C++17(ISO/IEC 14882:2017)は、C++11/14で導入された近代的な言語要素を現場でより運用しやすくする「安定化と実用性の強化」を主眼にした世代です。検索表記としては「c++ 17」と書かれることもあります。3年ごとのリリースサイクルにおける2017年版であり、後続のC++20へとつながる実装・設計慣行の足場を提供します。大規模コードベースや長期保守プロダクトにおいて後方互換性と可読性、生産性のバランスを取りやすいのが特長です。
- 役割: C++11/14で拓かれたモダンC++の実務定着を後押しする安定版。言語コアと標準ライブラリを実用志向で磨き上げ、日常的なコーディングを簡潔にします。
- 導入効果: コードの簡潔化、ビルドやレビューの生産性向上、プラットフォーム間の振る舞いの一貫性向上を通じて保守コストを削減します。
- エコシステム: 主要コンパイラと標準ライブラリ実装で広くサポートされ、サーバー/組み込み/デスクトップといった多様な領域でデファクトなターゲット規格として採用が進みました。
- 戦略的位置づけ: C++20以降へ移行する前段階として、チームの記法・設計スタイルをモダン化する「安全な中継点」。既存資産を崩さずアップグレードしやすい世代です。
規格策定の流れと標準化体制
C++17は、ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG21(C++標準化委員会)によって策定されました。WG21は各国のナショナルボディ(NB)からの代表や産業界・学術界の専門家で構成され、年数回の会合と通年の作業で規格文書を前進させます。運営は合意形成(コンセンサス)を重視し、段階的なレビューと投票を経て国際規格(IS)へ到達します。
- 提案(P紙)提出: 新機能や仕様改善は「Pxxxx」番号の提案文書として提出されます。動機、設計、影響、代替案、仕様文言案を含みます。
- 分科会レビュー: 提案は適切な分科会で検討されます。代表例は以下の通りです。
- EWG(Evolution Working Group)/LEWG(Library Evolution WG): 新機能の設計方針を議論。
- CWG(Core Working Group)/LWG(Library Working Group): 規格文言の精緻化と欠陥修正。
- 各種SG(Study Group): 並行処理、形式化、ユースケース別の専門検討など。
- 本会合での合意形成: 分科会での合意を受け、全体会合(Plenary)で採否の方向性を確認します。ここで規格草案への取り込みが前進します。
- 国際投票フェーズ: 規格草案(CD/ DIS 等)が各国NBに回付され、投票と技術コメントが寄せられます。WG21はコメントを解決し、文言を確定します。
- 発行と保守: 最終承認後、ISO/IEC 14882:2017として発行。以降は欠陥報告(Defect Reports)への対応を継続し、修正は次版や技術勧告に反映されます。
体制面の特徴として、WG21は「段階的な実験と統合」を重視します。特に新規分野はTechnical Specification(TS)として試験運用し、実装経験と利用実績を踏まえて本体規格に統合します。C++17でも、このTSパイプラインを通じて成熟度の高い要素が取り込まれ、実務上の安定性と移行容易性の両立が図られました。こうしたプロセスにより、C++17は過度な破壊的変更を避けつつ、現場価値の高い改善を着実に取り込んだ世代として位置づけられます。
言語仕様のアップデート(C++17)

C++17(c++ 17)は、既存コードの互換性を重視しつつ、設計の負担を減らし可読性と安全性を底上げするコア言語の更新が多数盛り込まれました。以下では、現場でのインパクトが大きいトピックを中心に、実務での使いどころと落とし穴に焦点を当てて解説します。
変数とデータ構造に関する拡張
データの受け渡しやヘッダ専用設計を支える仕組みが強化され、c++ 17の恩恵を最も実感しやすい領域です。
- 構造化束縛(structured bindings)
- 配列、pair/tuple互換オブジェクト、公開メンバのみの構造体などを、変数分解で直感的に扱えます。
struct S { int x; double y; }; S s{42, 3.14}; auto [a, b] = s; // a=42, b=3.14 auto [i, j] = std::array{1, 2}; - inline 変数
- 定数やグローバル/名前空間スコープ変数をヘッダに定義しても「多重定義」になりません。ヘッダオンリー設計の難易度が下がります。
inline constexpr int DefaultPort = 8080; struct Config { inline static std::string_view name = "app"; // 静的メンバにも可 }; - 保証されたコピー省略(guaranteed copy elision)
- prvalue からの初期化で一部のコンストラクタ呼び出しが必ず省略され、無駄なムーブ/コピーが消えます。
struct X { X(); X(const X&) = delete; }; X make(); X x = make(); // C++17ではOK(実体が直接構築される)
制御フロー構文の改良点
分岐の表現力と最適化余地が向上し、メタプログラミングの敷居が下がりました。
- if constexpr
- 条件がコンパイル時に判定され、偽分岐は型チェックも実行もされません。テンプレートの分岐記述を簡素化します。
template <class T> void f(const T& v) { if constexpr (std::is_integral_v<T>) { // 整数専用コード } else { // 非整数専用コード } } - 初期化付きif/switch
- 選択文のスコープに限定した初期化が可能になり、漏れや名前衝突を防ぎます。
if (auto it = m.find(key); it != m.end()) { use(*it); }
ラムダ式の機能強化
より軽量な関数オブジェクトとして幅広い場面に適用できます。
- constexpr ラムダ
- コンパイル時評価に参加できるため、定数式生成の部品として利用可能です。
constexpr auto sq = [](int x) { return x * x; }; static_assert(sq(5) == 25); - thisの値キャプチャ [*this]
- オブジェクトのスナップショットをラムダに取り込み、メンバの不意の変更から隔離できます。
struct Acc { int base; auto adder() const { return [*this](int x) { return base + x; }; // 値キャプチャ } };
テンプレート関連の更新
テンプレート記述のボイラープレート削減と、可変引数の表現力が向上しました。
- クラステンプレート引数推論(CTAD)
- コンストラクタの引数からテンプレート実引数を推論できます(集成体は除く)。
template <class T, class U> struct Pair { T t; U u; }; Pair p{1, 2.0}; // Pair<int,double> と推論 - フォールド式(fold expressions)
- 可変引数の畳み込みを1行で安全に表現。
template <class... Ts> auto sum(Ts... xs) { return (xs + ...); } - auto 非型テンプレート引数(NTTP)
- 許可される領域の型で推論されるため、より汎用的なメタ構築が可能に。
template <auto N> struct size_tag { static constexpr auto value = N; }; constexpr int n = 8; using tag = size_tag<n>; // Nの型はintと推論
定数式(constexpr)の拡充
c++ 17では、コンパイル時計算の実用性がさらに高まりました。if constexpr や constexpr ラムダの追加により、条件分岐や関数オブジェクトを定数式の中で自然に扱えます。また inline 変数と組み合わせることで、定数の配布・再利用が容易になります。
名前空間まわりの改善点
多段の入れ子を宣言する冗長さが解消されます。
namespace net::http::v1 {
// これまでの
// namespace net { namespace http { namespace v1 { ... } } }
}
例外仕様とエラーモデルの変更
例外仕様が整理され、言語の一貫性が増しました。
- 動的例外仕様(throw(Type))の削除
- throw() は noexcept(true) と等価な扱いに統一。throw(int) のような指定はエラーになります。
- noexcept の型系統への組み込み
- 関数型における例外仕様が区別される(詳細は後述)。関数ポインタやテンプレート実体化で影響が出ます。
属性(attributes)の追加と利用指針
コンパイラに意図を明示し、バグやノイズ警告を減らせます。
- [[nodiscard]]
- 戻り値の無視を防止。エラーハンドリング漏れを早期に検知。
[[nodiscard]] int parse(std::string_view); - [[maybe_unused]]
- 条件付きで未使用になりうる変数/関数の警告を抑制。
[[maybe_unused]] const int kDebugOnly = 1; - [[fallthrough]]
- switch のフォールスルー意図を明示し、誤りを防ぎます。
switch (x) { case 1: do_something(); [[fallthrough]]; case 2: do_next(); }
プリプロセッサの見直し
移植性と条件コンパイルの表現力が向上しています。
- __has_include
- ヘッダの存在可否をプリプロセス段階で判定可能に。
#if __has_include(<filesystem>) #define HAS_FS 1 #else #define HAS_FS 0 #endif - トライグラフの削除
- レガシー機能を廃し、予期せぬ文字変換による不具合を回避。
- 機能テストマクロの整備
- __cpp_if_constexpr などの値で機能有無を判定し、ポータブルな分岐が書きやすくなりました。
削除された言語機能
- 動的例外仕様(throw(Type))の削除(再掲)
- register 指定子の実質的な無効化
- 指定しても最適化に影響しない予約語として扱われます。コードから取り除くことが推奨です。
- トライグラフの削除(再掲)
細部仕様の調整と互換性
未定義/未規定動作に関わる角が取れ、バグの温床が減りました。
- 一部の式における評価順序の明確化
- 論理演算子(&&、||)、条件演算子(?:)、カンマ演算子などのシーケンシングが明確になり、副作用の衝突を回避しやすくなりました。
- prvalue の結果オブジェクトの扱い変更
- 一時オブジェクトの実体化ルールが整理され、ムーブ/コピーの発生有無をより直感的に推論できます(保証されたコピー省略と併せて理解)。
- オーバーアライン型のための new/delete
- アラインメント要求の高い型にも標準的に対応できるよう、言語側の拡張が入りました。
noexcept ルールの変更点と実務上の注意
c++ 17では、例外仕様が型システムに深く統合され、関数ポインタやテンプレートの挙動に実務的な影響があります。特に複数コンパイラを横断するコードベースでは、コンパイルフラグの差でビルドが通ったり通らなかったりする事象が生じやすいため注意が必要です。
- 関数型におけるnoexceptの有無は「異なる型」
- noexcept 指定のある関数ポインタ型とない型は互換ではありません。暗黙変換不可、オーバーロード解決にも影響。
- テンプレートの部分特殊化/オーバーロード
- noexcept の有無で別経路に分岐するコードは、推論や一致条件に細心の注意を。
- 移行時は型エイリアスで方針を固定
- 「API境界ではnoexcept必須」などの規約を型で表し、混在を防ぎます。
using FnNoThrow = void() noexcept; using FnMayThrow = void(); void set_handler(FnNoThrow*); // API方針を型で固定
C++17におけるnoexcept型推論の要点
- 関数参照/ポインタへの代入
- noexcept 関数を「noexceptなし」の関数ポインタ型に代入するのは不可(別型)。逆も不可です。
- auto 推論とnoexcept
- auto で関数ポインタを受けると、宣言側が noexcept を明示しない限り、期待と違う型になることがあります。型エイリアスや trailing return で明示を推奨。
void g() noexcept {} auto p1 = > // 型は実装依存に見えることがあるため要明示 void (*p2)() noexcept = > // こちらで意図を固定 - ラムダの operator() noexcept
- キャプチャや本体で投げないと静的にわかる場合でも、noexcept 指定は自動付与されません。必要なら明示します。
auto f = []() noexcept { /* ここで例外を投げない前提 */ }; using F = void(*)() noexcept; F pf = +f; // OK:noexceptで一致
MSVCの/Zc:noexceptTypesオプションと挙動
一部のMSVCツールセットでは、C++17における「noexcept を型の一部として扱う」挙動が切り替え可能です。
- /Zc:noexceptTypes
- 有効化: noexcept の有無を関数型の相違として扱う、より規格準拠のモード。
- 無効化: 互換性重視で noexcept を型差として扱わない場合があり、他実装(GCC/Clang)と差が出ます。
- 実務Tips
- プロジェクト方針として c++ 17 準拠を徹底するなら本オプションの有効化を検討。
- サードパーティ依存が多く混在する場合、段階的移行でビルドマトリクスを確認。
実装間差異と移行時のチェックポイント
- 複数コンパイラでのビルド検証
- GCC/Clang/MSVC で「noexcept を含む関数型」「初期化付きif」「構造化束縛」の挙動をCIで並列検証。
- API境界のnoexceptポリシー
- 公開ヘッダでは noexcept 有無を型に反映する方針を統一。関数ポインタやコールバックの typedef/using で明確化。
- 診断の自動化
- static_assert(noexcept(expr))、機能テストマクロ(例: __cpp_if_constexpr)でビルド時に逸脱を検出。
- レガシー構文の棚卸し
- throw(Type) や register の使用箇所を機械的に除去/置換。
標準ライブラリの更新点(C++17)
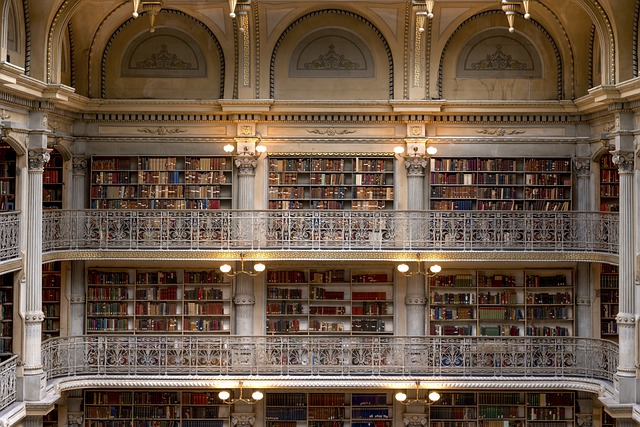
C++17(c++ 17)は言語機能だけでなく、標準ライブラリの広範な拡充・整理が大きな魅力です。日常的に使うユーティリティから大規模開発で効くファイルシステム・並列アルゴリズムまで、開発体験を一段引き上げる更新が多数入りました。以下では、ヘッダ単位・カテゴリ別に重要ポイントを整理します。
新規追加ライブラリの概要
- std::optional(<optional>): 値の有無を型で表現し、nullや番兵値に頼らないAPI設計を可能にします。
- std::variant(<variant>): 複数型のうちいずれかを保持する型安全な共用体。訪問(visit)で網羅チェックを強制できます。
- std::any(<any>): ランタイム型消去。動的型安全な保持と取り出し(any_cast)。
- std::string_view(<string_view>): 文字列の非所有ビュー。コピーなしで部分文字列を扱え、性能改善に直結します。
- std::filesystem(<filesystem>): パス操作、ファイル列挙、コピー/削除、空き容量取得などを標準化。
- std::byte(<cstddef>): バイトを意図する用途向けの型安全な1バイト表現。
- Polymorphic Memory Resources(<memory_resource>、名前空間 std::pmr): アロケータ差し替えを実用的にするメモリ資源API。
- 実用ユーティリティ: std::invoke と std::not_fn(<functional>)、std::apply / std::make_from_tuple(<tuple>)、std::as_const(<utility>)など。
- 高速数値変換(<charconv>): 文字列⇔数値の低オーバーヘッド変換 to_chars / from_chars(整数中心。浮動小数点は実装状況に注意)。
// optional/variant/any の例
#include <optional>
#include <variant>
#include <any>
#include <string>
std::optional<int> parse_or_none(const std::string& s);
using Payload = std::variant<int, double, std::string>;
void f() {
auto v = Payload{42};
std::any a = std::string{"payload"};
}
コンテナの変更・強化
- try_emplace / insert_or_assign(map / unordered_map): 重複キー時のムーブ・構築回避や代入を明示的に制御。
- ノードハンドル(extract / merge): 連想コンテナ間で要素の所有権を安全かつ効率的に移動可能。
- splicing的な統合: 型と比較器が互換なら、map/set 系間で O(1) 近い要素移送が可能に。
#include <map>
#include <string>
std::map<std::string, int> m1, m2;
void g() {
m1.try_emplace("key", 10); // 既存なら何もしない、なければ原位構築
m1.insert_or_assign("key", 20); // 既存なら代入、なければ挿入
auto nh = m1.extract("key"); // ノードハンドルで取り出し
if (nh) m2.insert(std::move(nh)); // もう一方へ移送
}
アルゴリズムの拡張
- 並列実行ポリシー(<execution>)対応: ほぼ全アルゴリズムが seq/par/par_unseq で拡張(詳細は並行・並列処理の項)。
- 新規アルゴリズム: clamp, sample, for_each_n, reduce / transform_reduce, inclusive_scan / exclusive_scan など。
- 検索器: boyer_moore_searcher / boyer_moore_horspool_searcher により高速部分文字列検索を提供。
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <random>
int clamp10(int x) { return std::clamp(x, 0, 10); }
std::vector<int> pick_k(const std::vector<int>& src, std::size_t k) {
std::vector<int> out;
std::mt19937 rng{std::random_device{}()};
std::sample(src.begin(), src.end(), std::back_inserter(out), k, rng);
return out;
}
文字列・文字列ビュー関連の改善
- std::string_view: 非所有の軽量ビューで、関数インターフェイスのコピー削減に有効。
- std::string::data が非constポインタ返却に統一(C++17): バッファアクセスが明確化。
- <charconv>: std::to_chars / std::from_chars による高速変換(ロケール非依存)。
- UDL: “foo”sv(std::string_view)リテラル(std::literals::string_view_literals)。
#include <string_view>
#include <charconv>
#include <string>
int parse_int(std::string_view sv) {
int v{};
auto* first = sv.data();
auto* last = sv.data() + sv.size();
auto res = std::from_chars(first, last, v); // 失敗時は res.ec != std::errc{}
return (res.ec == std::errc{}) ? v : 0;
}
並行・並列処理のアップデート
- <execution>: 実行ポリシー std::execution::seq / par / par_unseq により、多くの標準アルゴリズムを並列化。
- std::scoped_lock(<mutex>): 複数ミューテックスのデッドロック回避ロックを簡潔に。
- std::shared_mutex: 共有ロックと排他ロックを提供(読み取り多・書き込み少に有効)。
#include <execution>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <mutex>
std::mutex m1, m2;
void parallel_sum(std::vector<int>& v) {
std::for_each(std::execution::par, v.begin(), v.end(), [](int& x){ x += 1; });
}
void safe_swap() {
std::scoped_lock lock(m1, m2); // 順序付けは実装が面倒を見る
// ... 共有資源を安全に操作 ...
}
スマートポインタ周辺の見直し
- std::shared_ptr の配列対応: shared_ptr<T[]> により動的配列の所有も型安全に(delete[] が選択される)。
- enable_shared_from_this::weak_from_this: 構築途上での未定義動作を避けつつ弱参照を取得可能。
- ポインタ関連の細部仕様が明確化(ムーブ、比較、スレッド安全性に関する記述の整備)。
#include <memory>
struct Node : std::enable_shared_from_this<Node> {
std::weak_ptr<Node> weak() noexcept { return weak_from_this(); }
};
void h(std::size_t n) {
std::shared_ptr<int[]> buf(new int[n]); // 配列所有
}
数学ユーティリティと定数の追加
- <numeric>: std::gcd / std::lcm が追加。整数演算の基本ツールが標準化。
- 数値アルゴリズム(reduce, transform_reduce 等)との組み合わせで表現力と性能を両立。
#include <numeric>
int g = std::gcd(48, 18); // 6
int l = std::lcm(12, 18); // 36
タプルと構造化束縛まわりの更新
- std::apply / std::make_from_tuple: タプルからの関数呼び出し・生成が簡潔に。
- クラス テンプレート引数推論(CTAD)により、std::pair/ std::tuple の型推論が可能に。
- tuple-like プロトコルの整備により、pair/tuple/array が構造化束縛と自然に連携。
#include <tuple>
#include <string>
struct User { int id; std::string name; };
auto tup = std::make_tuple(7, std::string{"Ada"});
User u = std::make_from_tuple<User>(tup); // User{7, "Ada"}
std::pair p(1, 3.14); // CTAD: std::pair<int, double>
型特性(type traits)の拡張
- 呼び出し可能性: std::is_invocable(_r), std::invoke_result。
- スワップ性: std::is_swappable, std::is_nothrow_swappable。
- 論理合成: std::conjunction, std::disjunction, std::negation。
- 支援: std::void_t と _v 変種(例: std::is_same_v)。
#include <type_traits>
#include <utility>
static_assert(std::is_same_v<std::invoke_result_t<int(&)(int), int>, int>);
template<class T> using Enable =
std::enable_if_t<std::conjunction_v<std::is_move_constructible<T>,
std::is_swappable<T>>>;
時間・日付(chrono)の機能強化
- 丸めユーティリティ: std::chrono::floor / ceil / round(duration, time_point)。
- ファイル時刻との橋渡し: std::filesystem::file_time_type との相互運用を想定した明確化。
#include <chrono>
using namespace std::chrono;
milliseconds ms = 1234ms;
seconds s = floor<seconds>(ms); // 1s
乱数ライブラリの調整
- 仕様の明確化・整合性の改善(分布パラメータの比較・等値要件など)。
- random_shuffle は削除され、std::shuffle と新アルゴリズム std::sample を利用する流れに。
#include <algorithm>
#include <random>
#include <vector>
std::vector<int> v{1,2,3,4,5};
std::mt19937 rng{std::random_device{}()};
std::shuffle(v.begin(), v.end(), rng);
エラーハンドリングの改善
- std::uncaught_exceptions(<exception>): スタック巻き戻し中かをカウントで判定。スコープガードに有用。
- 新例外型: bad_optional_access, bad_variant_access, bad_any_cast。
- filesystem_error: ファイル操作の失敗を error_code とともに表現。
#include <exception>
struct commit_on_success {
int n = std::uncaught_exceptions();
~commit_on_success() {
if (std::uncaught_exceptions() == n) { /* commit */ }
else { /* rollback */ }
}
};
記法・規約の取り決め
- ヘッダ分割の明確化: <filesystem>, <optional>, <variant>, <any>, <string_view>, <execution>, <charconv>, <memory_resource> などを用途ごとに明示。
- UDL の導入位置: using namespace std::literals::string_view_literals; により “txt”sv を利用。
- pmr 規約: std::pmr 名前空間の型(polymorphic_allocator, memory_resource, monotonic_buffer_resource など)でアロケータ差し替えを統一。
- 関数呼び出し規約: std::invoke を経由することでポインタ・メンバポインタ・関数オブジェクトを一様に扱う。
廃止されたAPI
- std::auto_ptr(全関連API): unique_ptr / shared_ptr を使用。
- std::random_shuffle: std::shuffle(URBG 必須)に置換。
- 古い関数アダプタ群: bind1st / bind2nd, mem_fun / mem_fun_ref, ptr_fun, さらに std::unary_function / std::binary_function 基底も削除。std::bind / ラムダ / std::invoke を使用。
- std::allocator<void> の特殊化。
非推奨(deprecated)となったAPI
- std::result_of(C++20で削除予定だった系): std::invoke_result に移行。
- std::is_literal_type: 仕様上の曖昧さから非推奨。代替として個別特性の組合せで検討。
- std::iterator(イテレータ用の基底): 直接の継承を避け、iterator_traits に必要なネスト型/エイリアスを定義。
- std::raw_storage_iterator など一部の古いユーティリティが非推奨扱いに。
上記の更新により、C++17の標準ライブラリは安全性・性能・記述性の三拍子で大幅に前進しました。移行時は「追加(積極活用)」「代替(新APIへ置換)」「非推奨(段階的除去)」の3観点でコードベースを見直すのが効果的です。
C++17対応のビルド設定とツールチェーン

C++17を安定的に使うためには、コンパイラに規格バージョンを明示し、適切なツールチェーン(MSVCのバージョンやVisual Studioのプラットフォームツールセット)を選ぶことが重要です。ここではMSVC/Visual Studioに焦点を当て、/stdオプションの基本、実プロジェクトでの有効化手順、Visual Studio 2017以降の対応状況、そして準拠性・標準ライブラリの品質向上ポイントを整理します。検索の観点でも「c++ 17」という表記を含めつつ、実務に直結する設定の要点を網羅します。
規格バージョン指定の基礎(/stdオプション)
MSVCではC++の規格バージョンを/stdオプションで指定します。C++17を使う場合は/std:c++17を明示し、準拠性向上のために/permissive-(非標準拡張を抑制して標準に忠実にする)と/Zc:__cplusplus(__cplusplusマクロを正しい値に更新)を併用するのが実務の定石です。
- 代表的な値:
/std:c++14… C++14モード/std:c++17… C++17モード(推奨・安定)/std:c++latest… 将来規格案(プレビュー)の集合
- マクロの取り扱い:
_MSVC_LANG… MSVC独自。/stdに応じた値(例: C++17でおおむね201703L相当)__cplusplus… 既定では古い値のまま。/Zc:__cplusplusを付けて正しい値に更新
REM 開発者コマンド プロンプトでの例
cl /std:c++17 /permissive- /Zc:__cplusplus /EHsc /W4 main.cpp
ビルドシステム経由で指定する場合の例:
<!-- .vcxproj(VS 2019/2022 以降)-->
<ItemDefinitionGroup>
<ClCompile>
<LanguageStandard>stdcpp17</LanguageStandard>
<ConformanceMode>true</ConformanceMode> <!-- /permissive- -->
<AdditionalOptions>/Zc:__cplusplus %(AdditionalOptions)</AdditionalOptions>
</ClCompile>
</ItemDefinitionGroup>
# CMake の例(CMakeLists.txt)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
set(CMAKE_CXX_EXTENSIONS OFF) # 非標準拡張を抑制
# MSVC では /std:c++17 へ変換される
MSVCで/std:c++17を有効化する方法
プロジェクトの種類や運用に応じて、GUI・MSBuild・CLIのいずれでも有効化できます。いずれの方法でも、C++17の指定に加えてコンパイラ準拠性スイッチを組み合わせるのがポイントです。
- Visual Studio(プロパティ)での設定
- 「プロジェクトのプロパティ」→「C/C++」→「言語」→「C++ 言語標準」で「C++17 (/std:c++17)」を選択
- 同画面で「準拠モード」を「はい (/permissive-)」に設定
- 「C/C++」→「言語」→「__cplusplus を更新する」を「はい (/Zc:__cplusplus)」に設定
- MSBuild(.vcxproj)での設定
<LanguageStandard>stdcpp17</LanguageStandard>を追加<ConformanceMode>true</ConformanceMode>と/Zc:__cplusplusを併用
- コマンドライン(Developer Command Prompt)
cl /std:c++17 /permissive- /Zc:__cplusplus your.cpp
注意: プラットフォーム ツールセット(v141/v142/v143 など)も併せて確認してください。プロジェクトの「全般」→「プラットフォーム ツールセット」で選択できます。新しいツールセットほどC++17の準拠性と標準ライブラリの品質が向上します。
/std:c++latestとの違いと使い分け
/std:c++latestはC++20/23以降のドラフトやMSVCの先行実装を含む「プレビュー」モードです。将来の変更可能性があるため、プロダクションでは安定版である/std:c++17を基本とし、次の方針で使い分けるのが定石です。
- プロダクション/公開ライブラリ:
/std:c++17で固定し、互換性と再現性を最優先- 準拠性向上のため
/permissive-と/Zc:__cplusplusを併用
- 検証・将来機能の先取り:
- CIの追加ジョブやローカル検証で
/std:c++latestを用い、今後の破壊的変更を早期検知 - 公開ビルドは引き続き
c++ 17で出荷
- CIの追加ジョブやローカル検証で
- バージョン検出のベストプラクティス:
_MSVC_LANGまたは__cplusplus(/Zc:__cplusplus前提)を用いて条件分岐
#if defined(_MSVC_LANG) && _MSVC_LANG >= 201703L
// C++17 相当
#endif
Visual Studio 2017以降の対応状況
Visual Studio 2017以降では、MSVCコンパイラとMSVC STL(標準ライブラリ実装)が継続的にC++17準拠へと進化してきました。概況を押さえ、適切なツールセットを選びましょう。
- Visual Studio 2017(v141 ツールセット)
/stdスイッチが導入され、C++17の大半が段階的に実装- アップデートによりC++17言語機能の対応が大幅に進展
- Visual Studio 2019(v142 ツールセット)
- 言語機能の準拠性がさらに向上し、実務でのC++17採用が安定域に
- 標準ライブラリの機能充足と最適化が進み性能・品質が改善
- Visual Studio 2022(v143 ツールセット)
- 最新の修正と最適化が反映され、C++17を含む広範な準拠性と品質を提供
- 大型コードベースでのビルド・実行性能の改善が多数
実際に必要な機能や不具合修正は、プロジェクト要件や依存ライブラリによって異なります。具体的なバージョンの到達度は各リリースノート(Microsoft Docs / Visual Studio Release Notes)を参照してください。
コンパイラ準拠性の主要アップデート
MSVCはVisual Studio 2017以降でC++17準拠性を大幅に改善してきました。代表的な観点は以下です。
- 標準に準拠した名前探索やテンプレート関連の修正(不適合挙動の是正)
/permissive-の導入と改善による非標準拡張の抑制- 例外仕様や属性、constexprまわりの準拠性強化(段階的なバグ修正と相互運用性の改善)
- 診断品質の向上(テンプレートエラーの可読性改善、警告の粒度調整)
- ビルドパフォーマンスと最適化の強化(インクリメンタルビルドやコード生成の改善)
既存コードをC++17へ移行する際は、/permissive-で標準準拠に寄せたビルドを行い、依存コードの不適合箇所を早期に洗い出すと、後戻りの少ない移行が可能です。
標準ライブラリ実装の準拠・性能改善ポイント
MSVCの標準ライブラリ(Microsoft STL)は、C++17の各種コンポーネントの充足と性能面のチューニングが継続的に行われてきました。実務的にプラスとなる観点は以下です。
- 主要ヘッダの充足と安定化
<string_view>・<optional>・<variant>・<filesystem>などC++17要素の成熟化<charconv>(to_chars/from_chars)の最適化により、文字列変換のオーバーヘッドを削減
- 性能面のQuality-of-Implementation
std::basic_stringや各種コンテナのメモリアロケーション戦略・境界チェックの改善- アルゴリズムの内部最適化(分岐削減、ベクトル化の強化、実装依存の高速パス追加)
- 並列アルゴリズム(
<execution>)の実装品質向上により、対象ワークロードでスループットが向上
- デバッグ体験の改善
- デバッグイテレータやアサートの整備により、未定義動作の早期発見を支援
これらの恩恵は、より新しいツールセット(v142/v143など)を選ぶほど享受しやすくなります。C++17指定そのものに加え、ツールセットの更新で標準ライブラリの性能・安定性が向上する点を意識すると、開発・運用のリスクとコストを下げられます。
参考リンク・追加ドキュメント

ここでは、c++ 17(C++17)の学習、検証、移行や社内標準策定に役立つ信頼性の高い情報源を厳選して掲載します。公式仕様、準公式のリファレンス、各コンパイラの対応状況、ビルド設定の指針、日本語資料をバランス良く参照できるよう整理しました。
- 公式仕様・標準化関連
- WG21 N4659 — C++17 最終ドラフト(PDF):C++17の最終草案。条番号ベースで一次情報を確認可能。
- C++17 最終ドラフト(HTML版, N4659):ブラウザで検索しやすいHTML版。
- WG21 Link(paperナビゲータ):提案文書の恒久リンク。個別機能の出典追跡に便利。
- SD-6: Feature Test Recommendations:__cpp_* などの機能テストマクロの勧告。移行時の条件分岐に必須。
- ISO C++ — Standard status:規格の進捗と版情報のハブ。
- ISO/IEC 14882:2017(規格購入ページ):C++17正式規格の入手(有償)。
- リファレンス(言語・標準ライブラリ)
- cppreference: C++17 まとめ:C++17で追加・変更された言語機能とライブラリ機能の索引。
- cppreference: C++ リファレンス総合:シンボル単位の仕様確認に定番。
- cpprefjp: C++17 言語機能(日本語):日本語で主要機能の概要と注意点を整理。
- cpprefjp: 標準ライブラリ(日本語):C++17で拡充された各ヘッダのAPIを日本語で参照。
- コンパイラ実装・対応状況
- Compiler support for C++17(集約表):主要コンパイラの対応状況を一覧で確認。
- GCC C++17 実装状況:各提案ごとの対応可否とバージョン。
- Clang C++17 実装状況:Clang/LLVMの機能対応表。
- MSVC 言語準拠(C++17 節):MSVCの適合性と注意事項。
- ビルド設定・ツールチェーン
- MSVC: /std オプション(/std:c++17):言語バージョン指定の公式解説。
- GCC: -std=c++17 指定:標準選択と派生方言(gnu++17等)の説明。
- Clang: C++ 標準の選択:-std=c++17 の指定と互換情報。
- CMake: CXX_STANDARD(17):CMakeでC++17を要求・強制する方法。
- 移行ガイド/設計ガイドライン
- C++ Core Guidelines:モダンC++の設計原則。C++17活用の判断基準に。
- Herb Sutter: Trip report: Kona 2017:C++17承認時の背景と意図の理解に役立つ会合レポート。
- 日本語による学習・解説(コミュニティ)
- Qiita: #cpp17 タグ:実務目線の活用例やハンズオン記事。
- Zenn: C++17 トピック:最新のTipsや検証記事。
実装差異の確認は「コンパイラ対応表」+「SD-6の機能テストマクロ」の併用が有効です。仕様の根拠は必ずドラフト原文(N4659)に当たり、実装やビルド設定の詳細は各ベンダのドキュメントで最終確認してください。