この記事では、最新のビジネス向けAIツール20選を種類別に紹介し、チャット・文章作成・画像/動画生成など用途ごとの特徴や選び方を解説します。自社課題や予算に合うAI導入の参考になります。
目次
AIツールとは何か、その概要と仕組み

AI(人工知能)の基本概念
AI(人工知能)とは、人間の知能をコンピュータ上で再現しようとする技術やシステムの総称です。AIは大量のデータをもとに学習し、推論・判断・予測・認識といった知的作業を自動で行うことが可能です。現在のAI技術は大きく分けて「ルールベース型AI」と「機械学習型AI」に分類され、特に機械学習とその応用であるディープラーニングの進歩により、画像認識や自然言語処理などの分野で劇的な性能向上が実現しました。
AIツールは、こうしたAIの機能を特定の業務やタスクに利用できる形にしたアプリケーションやソフトウェアのことを指します。例えば文章生成、画像分析、音声認識、データ分析など、多様な用途に特化したAIツールが存在します。
生成AIの特徴と従来型AIとの違い
AI技術の中でも、近年特に注目されているのが「生成AI(Generative AI)」です。従来型のAIは、主に既存データをもとに分類や予測を行うことが中心でした。例えば、写真から犬と猫を識別する、過去の販売データから売上を予測するといったタスクです。
一方、生成AIは学習した情報をもとに新しいコンテンツを創り出す能力を持っています。代表例として、ChatGPTのような文章生成モデルや、Midjourneyのような画像生成AIがあります。生成AIは、文章、画像、音声、プログラムコードなど、多様なメディア形式を一から生み出すことができるため、創造的業務やコンテンツ制作の現場で革新をもたらしています。
- 従来型AI:分類・予測など既存データの分析が中心
- 生成AI:新しいデータやコンテンツを自動生成できる
- 応用領域:文章作成、広告コピー制作、デザイン案生成、音楽や映像制作など
生成AIの活用が注目される背景
生成AIが急速に注目されている背景には、技術の進歩と社会的ニーズの高まりがあります。特に大規模言語モデル(LLM)の登場により、自然で高精度な文章や複雑な画像を瞬時に生成できるようになりました。また、これまで専門的スキルや多くの時間が必要だった作業をAIツールが代替できるようになったことで、コスト削減や生産性向上の可能性が広がっています。
加えて、リモートワークやデジタルトランスフォーメーション(DX)の加速によって、オンラインで迅速にコンテンツを用意する需要が増加しました。これが、生成AIを活用した業務効率化の追い風となっています。
- 大規模言語モデルの発展による生成精度の向上
- クラウド環境やGPU性能向上による高速処理の実現
- DX推進によるコンテンツ制作需要の拡大
結果として、生成AIを搭載したAIツールは、ビジネスだけでなく教育、医療、エンターテインメントなど幅広い分野で活用が進んでいます。
AIツールの主な種類

チャット型AIツール
チャット型AIツールは、人間との自然な対話を可能にするAIの一種で、質問への回答や情報提供、雑談、意思決定サポートなど幅広く活用されています。高度な自然言語処理(NLP)技術と生成AIモデルを組み合わせており、ユーザーが入力した文章の意図を理解し、適切な応答を返すことができます。カスタマーサポートやFAQ応答、社内ヘルプデスクなど、業務効率化や顧客満足度の向上に直結します。
テキスト生成・文章作成AIツール
テキスト生成・文章作成AIツールは、ブログ記事、広告コピー、メール文面、SNS投稿文など、多様な文章を自動的に作り出す機能を持ちます。AIが文章構造や文体を学習しており、テーマやキーワードを入力するだけで高品質なコンテンツを短時間で生成できます。マーケティング分野やコンテンツ制作の現場で特に需要が高まっています。
コード生成・プログラミング支援AIツール
コード生成・プログラミング支援AIツールは、プログラマやエンジニアが書きたいコードを入力やコメント文から推測して生成したり、既存コードの補完や改善提案を行います。バグ検出やリファクタリング支援も可能で、ソフトウェア開発のスピードと品質の向上を実現します。特に初心者にとっては、学習補助としても役立ちます。
データ分析・リサーチ特化型AIツール
データ分析・リサーチ特化型AIツールは、大量のデータから傾向や洞察を抽出し、意思決定の材料を提供します。統計解析やレポート生成、論文検索や要点抽出などが可能で、科学研究やビジネス戦略立案、マーケティング分析などに活用されています。AIが複雑なデータを自動的に理解・可視化することで、専門知識のない人でも結果を効率的に利用できます。
画像生成・画像編集AIツール
画像生成・画像編集AIツールは、テキストからオリジナルの画像を描き起こしたり、既存の画像を編集・変換することができます。広告やWebデザイン、ゲーム開発、アート制作など幅広い分野で利用され、従来時間を要したクリエイティブ制作を大幅に短縮します。近年ではフォトリアルからアニメ調まで自在に創作できるツールが登場しています。
動画生成・編集AIツール
動画生成・編集AIツールは、少ない素材やテキスト指示から自動で映像を作成したり、既存の動画に字幕やエフェクトを追加する機能を提供します。プロモーション動画、教育コンテンツ、SNS用ショート動画などの制作を効率化し、専門的な映像編集スキルがなくても高品質な動画作成が可能です。
音声・音楽生成AIツール
音声・音楽生成AIツールは、自然な音声の合成や楽曲の自動生成を行います。ナレーションやポッドキャスト作成、BGM制作などに活用され、声質や曲調を細かく設定できるものも多く存在します。コンテンツ制作者だけでなく、マーケティングや教育分野など幅広い業界で導入が進んでいます。
資料作成支援AIツール
資料作成支援AIツールは、プレゼンテーション資料や報告書、提案書などを自動的に生成・整形する機能を備えています。情報構成やデザインのテンプレートを活用しながら、利用者が入力した要点を基にわかりやすい資料を瞬時に作成します。社内外での説明資料作成の負担軽減に役立ちます。
翻訳・要約・議事録作成AIツール
翻訳・要約・議事録作成AIツールは、多言語間での自動翻訳、長文の短縮要約、会議音声の自動文字起こしと要点整理を行います。国際的なビジネスやリモート会議、ドキュメント処理において、時間短縮と正確性の向上を同時に実現します。特にリアルタイム処理機能を持つツールは、現場での即時コミュニケーションを強力にサポートします。
AIツールの選び方

導入目的や解決したい課題を明確にする
AIツールを導入する際にまず重要なのは、何を目的として利用するのか、そしてどのような課題を解決したいのかを明確にすることです。例えば、社内業務の効率化、顧客対応の自動化、データ分析による意思決定の迅速化など、ゴールによって選ぶべきツールの種類や優先すべき機能が異なります。目的があいまいなまま導入すると、使いこなせずにコストだけがかかることになりかねません。導入前に現状の業務フローと課題点を洗い出し、それらをAIツールでどのように改善したいかというビジョンを描きましょう。
操作のしやすさとUIの直感性
AIツールは高機能であっても、操作が複雑すぎると実際の現場で使われなくなることがあります。特に職場の複数メンバーが利用する場合、誰でも短時間で操作方法を理解できるUI(ユーザーインターフェース)が重要です。ボタン配置やメニュー構造がわかりやすいツール、ヘルプやチュートリアルが充実しているツールを選ぶことで、導入後のスムーズな定着が期待できます。
日本語対応の有無
グローバル対応のAIツールは数多く存在しますが、日本語対応が不十分だと利用に支障をきたすことがあります。特にチャット型や文章生成系のAIツールでは、自然な日本語を理解・生成できるかどうかが成果の質を左右します。また、日本語のサポートページや問い合わせ窓口が用意されているかも確認すると安心です。
利用料金と予算のバランス
AIツールの料金体系はサブスクリプション型や従量課金型など多様です。機能や処理速度、利用可能なユーザー数によって価格に差があり、高機能なツールほどコストも高くなる傾向があります。予算内で最大限の効果を得られるよう、必要な機能と不要な機能を選別し、プランを比較検討しましょう。また、初期費用や追加機能の有料オプションの有無も事前に把握しておくことが大切です。
実際の運用環境に適した機能か確認する
AIツールはスペックや機能が豊富でも、実際の業務フローに適していなければ意味がありません。例えば、外出先でも利用したい場合はクラウド型やモバイル対応が必須ですし、特定の業務アプリとの連携が必要な場合はAPIやプラグイン対応を確認する必要があります。事前に導入環境と運用ルールを整理し、それに合致するツールを選びましょう。
セキュリティ性と信頼性の確保
AIツールは多くの場合、社内データや顧客情報を扱います。そのため、セキュリティ対策が不十分なツールは情報漏えいのリスクを高めます。通信データの暗号化、アクセス制限、認証方法、データの保存場所(国内外サーバー)などの観点から安全性を確認しましょう。また、ベンダーの運営実績やユーザーからの評判も信頼性の指標となります。
無料トライアルやデモ版で試してみる
導入を検討しているAIツールがあれば、まずは無料トライアルやデモ版を活用してみましょう。短期間でも実際の業務に組み込むことで、操作感や処理速度、精度、UIの利便性などを具体的に評価できます。また、社内の複数部門で試験的に利用してフィードバックを得ることで、正式導入後のミスマッチを防ぐことができます。
おすすめの汎用型AIツール

ChatGPT
ChatGPTは、OpenAIが開発した高性能な大規模言語モデルを活用したチャット型生成AIツールです。自然な会話形式での情報提供や文章生成が得意で、質問応答、文章作成、ブレインストーミングなど幅広い用途に対応します。特にビジネス現場では、メール文書の作成、アイデア出し、コードのサンプル生成など、多様な業務効率化を支援することが可能です。プラグイン機能やカスタムGPTにより、用途にあわせた拡張も容易になっています。
Gemini
GeminiはGoogleが提供する次世代型の汎用AIツールで、検索エンジンとのシームレスな連携が特徴です。最新の情報にアクセスしつつ、高度な分析や柔軟な文章生成を行うことができます。特にGoogle Workspaceとの統合により、ドキュメント作成やスプレッドシート分析、スライド作成といった業務に直接活用できる点が魅力です。また、マルチモーダル対応により、テキスト・画像・コードなど異なるデータ形式を組み合わせた高度な応答が可能です。
Claude
ClaudeはAnthropic社が開発した、安全性と信頼性を重視した生成AIです。人間との価値観の整合性やハルシネーションの低減に注力しており、ビジネスシーンでも安心して利用できます。長文の文章生成や分析、要約といったタスクにおいても安定性が高く、機密性の高い業務や社内ドキュメント作成に適しています。その落ち着いた応答と精度の高さから、研究や契約書下書きなど正確性が求められる分野でも評価されています。
Copilot(Microsoft 365 Copilotを含む)
CopilotはMicrosoftが提供するAIアシスタントで、特にMicrosoft 365 CopilotはWord、Excel、PowerPointなどのOfficeアプリと統合され、業務ドキュメントの作成・分析・編集を効率化します。自然言語での指示によってデータ集計や資料生成が可能で、反復作業を大幅に削減します。また、GitHub Copilotのように開発支援に特化したバージョンも存在し、プログラミング効率化にも活用可能です。組織全体で統一して利用しやすいのも大きな強みです。
Perplexity
Perplexityは、AIによる自然言語検索と回答生成を組み合わせた革新的な情報探索ツールです。ユーザーの質問に対して、信頼性の高い参考リンクや出典情報を付与しながら回答するため、調査やリサーチ業務に適しています。他のAIツールと比較して検索能力に優れており、最新の情報取得やファクトベースの応答を求めるビジネスパーソンに支持されています。対話形式での深堀り質問にも柔軟に対応します。
Notion AI
Notion AIは、人気のワークスペースツール「Notion」に統合された生成AI機能です。メモやドキュメントの自動要約、文章の改善提案、アイデア生成など、日常的な情報整理を大幅に効率化します。Notion本来のデータベースやプロジェクト管理機能と組み合わせることで、計画立案から実行までのプロセスを一貫してサポート可能です。特にチームでの情報共有や知識管理にAIの力を加えたい場合に最適な選択肢です。
チャット型AIツール

AIチャットくん
AIチャットくんは、LINE上で手軽に利用できるチャット型AIツールです。ユーザーは友だち登録を行うだけで、質問応答や文章作成、アイデア出しなどを日本語でスムーズに行えます。ChatGPTをベースにしており、日常的な雑談からビジネス上の相談まで幅広く対応可能です。スマートフォンから簡単にアクセスできるため、特別なアプリのインストールや難しい操作が不要なのも魅力です。
PKSHA Chatbot
PKSHA Chatbotは、企業向けに特化した国産のチャット型AIツールです。特にカスタマーサポートやFAQ対応に強く、シナリオ設計と機械学習を組み合わせることで高精度な回答を実現します。日本語の自然言語処理に優れており、顧客対応の効率化や応答品質向上に寄与します。社内システムや既存の問い合わせ管理ツールとも柔軟に連携できる点も特徴です。
QuickCEP
QuickCEPは、ECサイトやオンラインストア向けに最適化されたチャット型AIツールです。顧客データや購買履歴を活用し、パーソナライズされた商品提案や自動接客を行えます。マーケティング自動化機能も備えており、訪問者の行動に応じたリアルタイムな対応が可能です。これによりコンバージョン率向上や顧客満足度の向上が期待できます。
Goat Chat
Goat Chatは、複数のAIモデル(GPTシリーズなど)を切り替えて利用できるチャット型AIツールです。ユーザーは対話の目的や内容に応じてモデルを選択できるため、創作や翻訳、プログラミング相談など用途に合わせた最適な応答を得られます。クラウドベースであり、ブラウザからすぐ利用できる利便性も高いです。
ChatSonic
ChatSonicは、Google検索との連携機能を持つチャット型AIツールで、最新情報を反映した回答を生成できる点が特徴です。文章生成だけでなく、音声指示や画像生成にも対応しており、対話の幅が広がります。マーケティングやコンテンツ作成の現場では、トレンドに即した情報提供に活用できます。
Forefront AI
Forefront AIは、チームや組織での利用に適したチャット型AIツールです。高度なプライバシー保護機能やプロンプトの共有機能を備え、共同作業を効率化します。また、複数の言語やモデルに対応しており、グローバルな業務や多様なプロジェクトで活用可能です。ビジネスシーンでの安全性と柔軟性の両立を重視するユーザーに向いています。
テキスト生成・文章作成AIツール
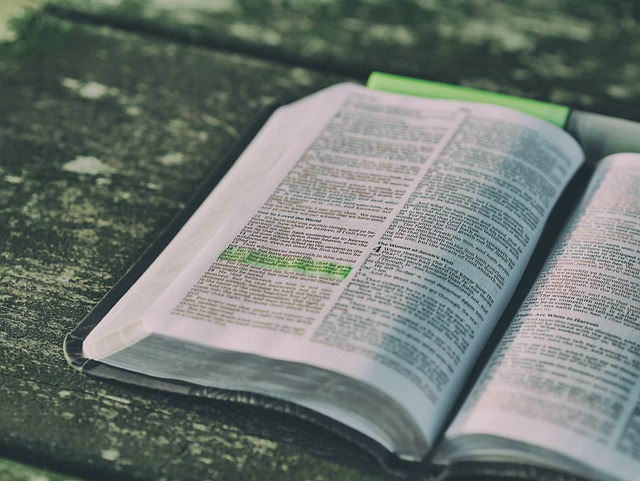
Catchy
Catchyは、日本語マーケティングに特化したAIライティングツールで、広告コピーやブログ記事、SNS投稿文など幅広いコンテンツ作成を支援します。ユーザーが簡単なテーマやキーワードを入力するだけで、自然でキャッチーな文章を生成することが可能です。特にマーケターやコンテンツ制作者にとって、短時間で高品質な文章を量産できる点が魅力です。
EmmaTools
EmmaToolsは、SEO対策に強みを持つ文章生成AIツールです。検索キーワードの分析から記事構成案の自動作成、文章執筆までを一貫してサポートし、検索エンジンで上位表示を狙えるコンテンツ作成を効率化します。SEOの専門知識がなくても、誰でも最適化された記事を作れる点が特徴です。
Jasper
Jasperは、英語圏を中心に利用者が多い高性能な文章作成AIツールで、マーケティングコピーやストーリー、ブログ記事など多様なコンテンツを生成します。豊富なテンプレートや語調の設定機能があり、ブランドトーンに合わせた文章作成が可能です。多言語対応で、日本語の文章生成もサポートしています。
SAKUBUN
SAKUBUNは、日本語学習や文章作成支援に特化したAIツールです。文章の自動生成だけでなく、言い回しの提案や校正機能も備えており、ビジネス文章からクリエイティブな作文まで幅広く対応します。特にネイティブレベルの自然な日本語表現を求めるユーザーに適しています。
Transcope
Transcopeは、リサーチや翻訳、文章生成を組み合わせたハイブリッド型AIツールです。海外情報を日本語化して整理し、そのまま記事やレポートにまとめられる点が特徴で、特に海外市場の動向調査やグローバルコンテンツ制作に強みがあります。
AI Writer
AI Writerは、フルオートで記事を生成することに特化したAIツールです。入力されたタイトルやキーワードから、自動で構成を組み立て、読みやすくSEOに配慮した文章を作成します。下書き段階から完成に近い形まで一気に生成できるため、作業効率を大幅に向上させます。
Numerous.ai
Numerous.aiは、スプレッドシート上で直接AI文章生成を行えるツールです。GoogleスプレッドシートやExcelと連携し、各セルに指定条件を入力するだけで自動的にテキストを生成します。大量の商品説明やデータベース情報からの文章化など、大規模なテキスト生成業務に適しています。
コード生成AIツール
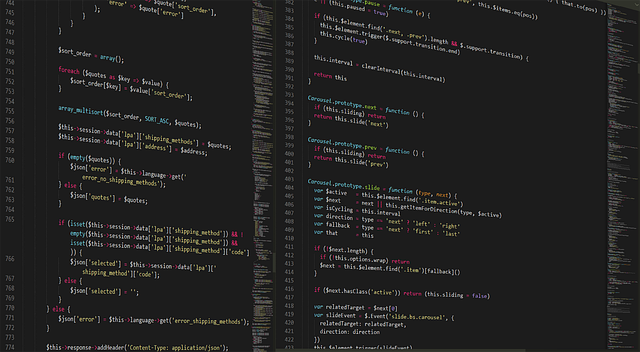
GitHub Copilot
GitHub Copilotは、OpenAIのCodexモデルを基盤としたプログラミング支援型のAIツールです。Visual Studio CodeやJetBrainsなどの主要な統合開発環境(IDE)と連携し、コードの自動補完や関数提案、コメントからのコード生成を行います。開発者が数文字入力するだけで、文脈を理解した適切なコードスニペットを提示してくれるため、開発効率の大幅な向上が可能です。
- 複数のプログラミング言語に対応
- 自然言語のコメントを元に関数や構造体などを生成
- 既存コードの文脈を理解したうえで提案
特にルーチンワーク的なコード記述やAPI利用方法の検索時間を省略できるため、初心者から上級者まで幅広く活用されています。
Amazon CodeWhisperer
Amazon CodeWhispererは、AWSが提供する開発者向けAIコード生成ツールです。Java、Python、JavaScriptなど主要な言語に対応し、AWSの各種サービスとシームレスに連携できることが強みです。コードを入力する中で、リアルタイムに補完や提案を行い、セキュリティベストプラクティスにも配慮したコードを提示します。
- AWS LambdaやAmazon S3などクラウド環境との親和性が高い
- セキュリティスキャン機能で潜在的な脆弱性を検出
- 複数IDEと統合可能(Visual Studio Code、JetBrains製品など)
AWS環境下での開発を効率化したいエンジニアに特におすすめのAIツールです。
TabNine
TabNineは、機械学習による高精度なコード補完に特化したAIツールで、数十種類以上のプログラミング言語に対応しています。軽快な動作とカスタマイズ性の高さが特徴で、クラウド型とローカル型の両方のモデルを選択可能です。
- 高速で遅延の少ないコード補完
- ローカルモデル利用によりコードの機密性を維持可能
- 多言語サポートとプラグインの豊富さ
コンパクトながらも学習済みモデルの性能が高く、特に軽量でセキュアな環境を求める利用者から支持を集めています。
Cursor
Cursorは、AIによるコード補完とチャット形式のコーディング支援を融合させた新しいタイプの開発支援ツールです。エディタ内で生成AIと自然なやりとりをしながらコード改善やアルゴリズム提案を受けられる点が特徴です。
- 対話形式でコードレビューやリファクタリング提案が可能
- 既存コードの理解やドキュメント生成を支援
- 複雑なアルゴリズムの実装も指示ベースで自動化
コードの品質向上を目指す開発者や、生成AIを積極的に活用した新しい開発スタイルを求める現場で注目されています。
データ分析・リサーチAIツール

データ分析・リサーチ分野に特化したAIツールは、膨大な情報から必要な知見を的確かつ迅速に抽出するために活用されています。これらのツールは、ビジネスインテリジェンス、学術研究、競合分析など幅広い分野で役立ち、情報収集や整理の時間を大幅に削減します。以下では、代表的な5つのデータ分析・リサーチAIツールを紹介します。
Consensus
Consensusは、学術論文や研究資料をもとに、ユーザーの質問に対して信頼性の高い回答を提供するAIツールです。特に科学・医療・経済などの専門分野でのリサーチに強みがあり、複数の論文を同時に解析して一貫した結論を提示します。研究の初期段階で「何が既に分かっているのか」を素早く把握したい場合に最適です。
Wolfram Alpha AI
Wolfram Alpha AIは、単なる検索エンジンではなく、膨大なデータベースと計算知能を活用して答えを導き出す「計算知識エンジン」です。数学、統計、科学、技術分野の計算問題やデータ解析に優れ、入力された質問に対して即時に計算結果や可視化グラフを生成します。研究や教育現場において、計算や理論検証の効率化に大きく貢献します。
Glarity
Glarityは、Google検索やYouTube、学術データベースなどで得られる情報をAIが要約し、重要ポイントのみを提示してくれるブラウザ拡張型ツールです。検索効率を高めつつ、冗長な情報の取捨選択をサポートします。特にトレンド調査や競合分析において、膨大なコンテンツを短時間で把握することが可能になります。
SciSpace
SciSpaceは、論文検索・要約・引用管理を一元的に行える研究者向けAIツールです。PDF論文に直接コメントや質問ができるインターフェースを備え、AIが内容を解説してくれるため、専門分野外の研究内容も理解しやすくなります。論文レビューや資料作成時における時間短縮と理解促進に有効です。
ChatPDF
ChatPDFは、PDFファイルをアップロードすると、その内容について自然な会話形式で質問できるAIツールです。長文の資料や報告書から必要な情報を即座に引き出せるため、会議資料の把握や技術文書の理解に役立ちます。多言語PDFや専門用語が多い文書でも、AIが文脈を理解して回答してくれるのが特長です。
画像生成・編集AIツール

Midjourney
Midjourneyは、高品質かつ芸術性の高い画像を生成することで注目されているAIツールです。テキストプロンプトを入力するだけで、フォトリアルからファンタジックなイラストまで多様なスタイルの画像を自動生成できます。特に光や陰影の表現、質感のリアルさに優れ、クリエイターやデザイナーから高い評価を得ています。現在はDiscord上でボットを通じて利用する形式を取っており、コマンド入力によって細かいパラメータ調整も可能です。広告素材作成やコンセプトアート制作など、幅広いクリエイティブ業務で活用できます。
DALL・Eシリーズ(2 / 3)
OpenAIが開発したDALL・Eシリーズは、テキストから画像を生成する代表的なAIツールです。DALL・E 2では高精細な画像生成が可能となり、DALL・E 3ではChatGPTとの統合により、より自然な指示で意図通りの結果を得やすくなりました。また、既存画像の一部を修正・拡張する「インペインティング」機能も搭載しており、編集作業の効率化にも貢献します。コンテンツ制作や商品イメージ作成など、商用利用の場面でも活躍します。
Adobe Firefly
Adobe Fireflyは、PhotoshopやIllustratorといったAdobe製品とシームレスに連携できる生成AIツールです。特長は「生成塗りつぶし」機能で、写真やデザインの特定部分を自然に修正できる点です。また、テキストから直接ベクター画像やスタイルバリエーションを作れるため、デザイナーの制作効率を飛躍的に向上させます。Adobeのクリエイティブクラウドユーザーにとっては、ワークフローに直結する利便性が魅力です。
Stable Diffusion
Stable Diffusionは、オープンソースとして提供されている画像生成AIで、自由度の高さとカスタマイズ性が特徴です。ローカル環境にインストールして利用できるため、プライバシーやデータ管理の面でも安心です。さらに、多様なモデルや拡張プラグインがコミュニティから提供されており、アートスタイルの変更やアニメ調画像の生成など、多彩な用途に対応します。研究開発から同人創作まで、幅広いクリエイター層に支持されています。
Bing Image Creator
Bing Image Creatorは、Microsoftが提供する無料で使える画像生成AIツールで、DALL・Eの技術を採用しています。ブラウザ上から簡単にアクセスでき、テキスト入力のみでイメージを作成可能です。Bing検索との連携により、生成した画像をすぐに活用できるのも利点です。特にAIツール初心者や、短時間で試作品を作成したいユーザーに向いています。
Canva
Canvaはデザインツールとして広く知られていますが、近年はAI機能を強化し「テキスト to 画像」機能を搭載しています。これにより、ユーザーは特別なスキルがなくてもプロ品質のデザイン素材を生成できます。さらに、AIによる自動レイアウト調整や背景除去など、編集工程の多くを効率化できます。SNS投稿用バナー、プレゼン資料、チラシなど幅広い用途に対応し、マーケティング担当者やフリーランスデザイナーにとって強力な味方です。
niji・journey(にじジャーニー)
niji・journeyは、Midjourneyの派生モデルとして開発された、アニメ・漫画スタイルに特化した画像生成AIです。キャラクターデザインやイラスト制作に強みを持ち、日本のアニメ文化に馴染む色彩やタッチを忠実に再現します。ゲーム開発やライトノベルの挿絵制作など、エンタメ分野での利用価値が高いツールです。特定のアートスタイルが必要なクリエイターにとって、効率良く作品を量産できる選択肢となります。
Leonardo.AI
Leonardo.AIは、ゲームアセットや高解像度の商用グラフィック生成に特化したAIツールです。用意された多様なプリセットモデルにより、背景、キャラクター、アイテムなどテーマごとに最適な画像生成が可能です。また、ワークスペース機能でプロジェクト単位の管理がしやすく、チームでの共同制作にも向いています。特にゲーム・メディア制作企業のプロフェッショナル利用が進んでいるサービスです。
動画生成・編集AIツール

Runway
Runwayは、生成AIを活用した動画編集・生成プラットフォームとして、クリエイターやマーケターに広く利用されています。特に「Text to Video」や「Image to Video」といった最新機能では、テキストや静止画を入力するだけで、短時間で高品質な動画を生成可能です。機械学習モデルを駆使して、自動で背景除去やカラーグレーディングを行えるため、従来の編集作業を大幅に短縮できます。映像制作のプロだけでなく、動画初心者でも直感的に操作できるUI設計も魅力です。
Vrew
Vrewは、動画の自動字幕生成と編集効率化に特化したAIツールで、特にYouTubeや企業研修動画の制作で高い評価を得ています。音声認識機能による自動テキスト化、字幕の自動整形、タイミングの最適化など、煩雑な字幕製作作業をほぼ全自動で完了できます。また、テキスト編集を行うだけで動画の該当部分が自動でカットされる機能があり、非映像専門職の人でも簡単に動画編集が可能です。
Pika
Pikaは、短い動画クリップやSNS向けコンテンツの生成を得意とするAI動画編集ツールです。ユーザーが指定するキーワードやテーマに沿って映像素材を生成し、そのままSNSにアップロードできる形式で出力します。高速なレンダリングとシンプルな操作性が特徴で、素早く企画から配信までを完了したいマーケティングチームや個人クリエイターに最適です。
Synthesia
Synthesiaは、AIによるアバターと音声合成を組み合わせ、実在の人物が話しているかのような動画を作れる革新的プラットフォームです。多言語対応しているため、グローバル企業が複数言語の研修動画や営業資料を短期間で制作する用途に活用されています。カメラ撮影やスタジオ収録が不要なため、コスト削減とスピード面で大きなメリットがあります。
HeyGen
HeyGenは、AI生成アバターを使った動画作成に特化し、プレゼンテーションや製品デモ用コンテンツの作成に有効です。ユーザーはスクリプトを入力するだけで、AIアバターが自然な表情や口の動きで台詞を話す動画を生成します。テンプレートやアニメーションエフェクトも豊富で、ビジネス用途から教育コンテンツまで汎用的に利用可能です。
Kaiber
Kaiberは、音楽や静止画からインスピレーションを得て映像を生成するユニークなAIツールです。特にアーティストや映像クリエイターから人気が高く、ミュージックビデオやアート映像の制作に適しています。ユーザーがアップロードした曲や画像を解析し、それにマッチしたビジュアルスタイルや動きを自動生成する機能が特徴です。
Lumen5
Lumen5は、ブログ記事やテキストコンテンツを自動で動画化することに特化したAIツールです。AIが文章を解析し、関連する映像素材やBGMを選定してシーン構成を自動生成します。特に企業のコンテンツマーケティングやSNS運用において、大量のコンテンツを効率的に動画化できるため、ブランドの情報発信をスピードアップする効果があります。
音声・音楽生成AIツール

音声・音楽生成AIツールは、AI技術を用いて人間の声や楽曲を自動的に生成・編集できる革新的なツール群です。ナレーション制作や音声コンテンツの作成、楽曲制作の効率化など、クリエイティブ分野やビジネスの現場で活用が広がっています。ここでは、代表的な音声・音楽生成AIツールを4つ紹介します。
Suno
Sunoは、テキスト入力だけで高品質な楽曲を自動生成できる音楽特化型AIツールです。ユーザーは歌詞や音楽ジャンル、曲調などの条件を指定するだけで、数十秒から数分の楽曲が生成されます。インストゥルメンタルからボーカル入り楽曲まで対応し、個人の創作活動はもちろん、動画コンテンツや広告用のBGM制作にも活用可能です。また、商用利用に対応したプランが用意されている点も魅力です。
ElevenLabs
ElevenLabsは、高精度な音声合成(TTS: Text-to-Speech)に特化したAIツールです。自然で抑揚のある音声を生成でき、複数言語・多様な声質に対応しているため、グローバルな音声コンテンツ制作にも向いています。特徴的なのは、数分間の音声データから特定人物の声を高精度に再現できる「ボイスクローン」機能で、パーソナライズされたナレーションやブランドボイスの構築に利用されています。
CoeFont STUDIO
CoeFont STUDIOは、日本発のクラウド型音声合成サービスで、プロの声優やナレーターの声をベースにした高品質な音声を生成できます。直感的な操作で文章を音声化でき、日本語に最適化された発音とイントネーションの自然さが特長です。教育コンテンツ、ナレーション、読み上げサービスなど幅広い用途で利用されており、声質や感情表現の細かなカスタマイズも可能です。
Voicevox
Voicevoxは、無料で利用できるオープンソースの音声合成AIツールです。複数のキャラクターボイスが用意されており、ユニークで親しみやすい音声を簡単に作成できます。商用利用にも対応しているため、動画制作やVTuber活動、ゲーム実況など、個人クリエイターから企業プロジェクトまで幅広く活用されています。動作も軽快で、ローカル環境とクラウドの両方で利用できる点も利便性の高さにつながっています。
資料作成AIツール

Gamma
Gammaは、プレゼンテーション資料や提案書、企画書などをわずかなテキスト入力から自動生成できる資料作成特化型のAIツールです。従来、構成の設計やデザイン作業に多くの時間をかけていた業務を大幅に効率化できるのが特徴です。直感的な操作でページ構成を変更でき、用意されたテンプレートやデザインテーマも豊富なため、非デザイナーでも視覚的に優れたスライドを作成できます。
- テキスト入力から自動的にスライド構成を生成
- AIによる内容要約や追加情報の提案機能
- ブラウザベースで共同編集が可能
企業の営業資料作成や社内共有用のスライド、イベント用プレゼン作成など、多彩なビジネスシーンで活用が進んでいます。
Tome
Tomeは、ストーリーテリングに力を入れた資料作成AIツールです。シンプルな文章入力からスライドを生成するだけでなく、画像や動画、埋め込みリンクなどのマルチメディア要素を組み合わせ、動きのあるダイナミックな資料を作成できます。そのため、製品やサービス紹介のプレゼン、ピッチ資料、ビジュアル重視のレポート作成に適しています。
- AIによるストーリー構成の自動提案
- 画像生成AIとの連携機能
- レスポンシブ対応でモバイル表示も最適化
特にスタートアップやデザイン志向の強いチームに人気があり、印象的かつわかりやすい資料づくりを強力にサポートします。
Beautiful.ai
Beautiful.aiは、デザイン自動補正機能が特徴の資料作成AIツールです。ユーザーが入力したテキストやデータをもとに、スライドのレイアウト・配色・フォントバランスを自動で最適化します。これにより、プレゼン初心者でも美しいデザインの資料を効率よく仕上げられます。
- スライドデザインの自動補正&調整
- 豊富なアイコン・図解テンプレート
- リアルタイム共同編集に対応
社内外での提案資料やセミナー用スライド、カンファレンス資料の作成など、幅広い用途で利用されています。
Napkin.AI
Napkin.AIは、アイデアの整理やブレインストーミングを支援しながら、そこから直接資料にまとめられるAIツールです。メモや構想段階の文章を入力すると、関連情報の補完や章立ての提案を行い、そのままスライドや文章構造へ変換可能です。特に初期の企画段階からアウトプットまで一貫して支援できる点が特徴です。
- アイデアマップの自動生成
- 関連トピックや追加情報の提案機能
- 資料形式へのワンクリック変換
チームの発想段階から完成資料までをAIでスムーズに繋ぐことができるため、クリエイティブ業務や企画推進におすすめです。
翻訳・要約・議事録作成AIツール

ビジネス現場や国際的なコミュニケーションにおいて、正確かつ迅速な情報の共有は欠かせません。近年は、AI技術を活用した翻訳・要約・議事録作成ツールが登場し、会議やインタビュー、グローバルなやり取りを効率化する手段として注目されています。ここでは代表的な5つのAIツールを紹介します。
Notta
Nottaは、音声をリアルタイムで文字起こしし、そのまま要約や翻訳まで行える多機能なAIツールです。オンライン会議や対面での講演など、幅広い場面に対応可能で、特に日本語と英語の精度が高く評価されています。スマートフォンアプリやWebブラウザから利用でき、クラウド上で自動保存されるため、議事録の共有や再編集もスムーズです。
CLOVA Note
LINE株式会社が提供するCLOVA Noteは、録音データや音声ファイルをアップロードするだけでAIが自動的に文章化するサービスです。LINEのアカウントと連携できるため使い始めやすく、複数話者の識別機能も搭載しています。AIによる要約生成やキーワード抽出機能があり、会議後の情報整理に要する時間を大幅に削減できます。
ACES Meet
ACES Meetは、オンライン会議専用のAI議事録作成ツールです。ZoomやGoogle Meetなど主要な会議プラットフォームと連携し、会議中の発言を即座に文字化します。議事録は自動的に整形され、アクションアイテムや重要なトピックを抽出する機能も提供。チーム全体の意思決定を早めるためのサポートツールとして有効です。
AI議事録取れる君
AI議事録取れる君は、日本語環境に特化した議事録作成AIツールです。シンプルな操作で、会議音声をアップロードするだけで発言者ごとのテキスト化と要約を自動で実行します。オンプレミス対応も可能で、セキュリティ要件の厳しい業種でも利用しやすいのが特徴です。公共機関や医療機関での活用事例も増えています。
YOMEL
YOMELは、長文テキストや音声記録を短時間で要約してくれるAIツールです。特にインタビュー記事や研究会議のように情報量が多い資料を短くまとめるのが得意で、重要ポイントのみを抽出する機能も備えています。翻訳機能も搭載しているため、国際的な情報共有や多言語資料の作成にも活用できます。
AIツール活用事例と業務効率化のポイント

コンテンツマーケティングへの活用
コンテンツマーケティングでは、情報発信のスピードと質の両立が求められます。AIツールを活用することで、記事やブログ投稿、SNSコンテンツの企画から執筆、編集までを効率化でき、限られたリソースでも継続的に高品質なコンテンツを配信できます。
例えば、生成AI搭載の文章作成ツールを使えば、キーワードに基づいた構成案の作成や、SEOを意識したタイトル・見出しの提案が可能です。また、校正AIを併用することで、誤字脱字やスタイルの統一も容易になります。さらに、画像生成AIを組み合わせることで、記事やSNS投稿に適したビジュアル素材を短時間で用意でき、読者の関心を引きつけやすくなります。
- ターゲット層に合わせたパーソナライズ記事の作成
- SEOキーワード分析と自然な文章生成の両立
- 画像・動画生成AIとの連携によるコンテンツ強化
プレゼン資料・社内文書作成の効率化
ビジネスシーンにおいて、プレゼン資料や社内報告書の作成は頻繁に発生しますが、時間や手間がかかる作業のひとつです。AIツールを活用すれば、情報の整理からスライドデザインまで一括で効率化できます。
たとえば資料作成支援AIは、与えられたテキストやデータをもとに自動でスライド構成を提案し、デザインも統一してくれます。また、文書の要約AIを使えば、長文の報告資料や会議議事録を短時間で読みやすくまとめられ、共有や意思決定のスピードアップに繋がります。
- 長文の要約やポイント抽出による資料短縮
- ビジュアルテンプレート自動適用によるデザイン品質の均一化
- データ入力からグラフ作成までの自動化
カスタマーサポートの自動化
顧客対応のスピードや質は、企業の信頼性に直結します。AIツールによるカスタマーサポートの自動化は、人的負担を大幅に軽減し、24時間対応を可能にします。
AIチャットボットは、顧客からのよくある質問への自動応答や、問い合わせ内容の分類・エスカレーションを行うことができます。さらに、自然言語処理機能を備えたAIは、文脈を理解して的確な回答を返すことが可能で、人間のサポート担当者はより高度な対応に集中できます。
- FAQ対応の完全自動化による問い合わせ対応時間の短縮
- 感情分析機能による顧客満足度向上
- CRMとの連携による顧客データ活用の最適化
市場調査・競合分析のスピード向上
従来の市場調査や競合分析は、人手での情報収集や資料作成に時間がかかっていましたが、AIツールの導入により、膨大なデータを短時間で分析し、意思決定までの時間を大幅に短縮できます。
たとえば、AIリサーチツールはウェブ上のニュース、SNS投稿、企業のIRデータなどを迅速に収集し、重要なトレンドや競合動向を自動抽出できます。また、データ可視化AIを用いれば、集めた情報をグラフやチャートで直感的に理解できるため、経営層へのプレゼン資料も効率よく作成できます。
- 複数のデータソースからの自動情報収集
- テキストマイニングによる市場トレンド分析
- レポート自動生成による調査コスト削減
AIツールを安全に使うための注意点

利用ルールの事前設定
AIツールを業務に導入する際には、組織としての利用ルールを事前に設定しておくことが重要です。ルールが曖昧なまま利用を始めると、誤用や情報流出のリスクが高まります。具体的には、利用目的の明確化、使用できる機能や範囲の制限、業務外利用の禁止などを文書化し、全社員が共有できる状態にしておくことが望まれます。また、AIツールの利用履歴を記録できる管理体制を整えることで、トラブル発生時の原因究明にも役立ちます。
社員のAIリテラシー向上
いくらルールを整備しても、利用者の知識が不足していては安全な運用は難しいものです。そのため、AIツールの基本的な仕組みや長所・短所、リスクに関する知識を社員教育として組み込むことが必要です。定期的な研修やワークショップを通じて、プロンプトの作成方法、出力結果の評価の仕方、著作権やデータ保護に関する知識を身につけてもらいましょう。AIリテラシーの向上は、業務効率化だけでなくリスク回避にも繋がります。
生成コンテンツの人間による確認
AIツールが生成した文章や画像は一見正確に見えても、事実誤認や偏り、法的リスクを含んでいる場合があります。したがって、生成されたコンテンツは必ず人間が内容を確認し、必要に応じて修正を加えることが不可欠です。特に外部に公開する資料や顧客への提案資料などは、誤情報や不適切な表現が含まれると企業の信頼性低下に直結するため、複数人でのレビュー体制を構築するのがおすすめです。
機密情報や個人情報の取り扱いに関する配慮
AIツールに入力する情報には細心の注意が必要です。特にクラウド経由で処理されるツールでは、入力した内容が外部サーバに送信され、学習データやログとして保存される可能性があります。顧客データや社内の極秘情報、個人を特定できる情報は入力しないという基本方針を徹底しましょう。また、必要に応じてオンプレミス型のAIツールやプライバシー保護機能を備えたツールを採用し、情報漏洩リスクを最小限に抑えることが重要です。
まとめ・AIツールを活用して業務を革新する

AIツールは、単なる業務支援ツールにとどまらず、企業の生産性や競争力そのものを引き上げる革新的な存在となっています。特に近年は、生成AIや機械学習を活用した高性能なツールが数多く登場し、文章作成、データ分析、クリエイティブ制作、顧客対応など、業務のあらゆる領域において飛躍的な効率化が実現可能になりました。
このような変化は、単に時間やコストを削減するだけでなく、従来では不可能だったスピードと精度で意思決定や価値創造を行える点に大きな特徴があります。その結果、社員一人ひとりがより創造的な業務に集中できるようになり、組織全体のアウトプット向上につながります。
AIツールを効果的に活用するためには、以下のポイントが重要です。
- 導入目的と解決したい課題を明確にする
- 自社の業務フローに適した機能を持つツールを選ぶ
- セキュリティや個人情報保護の方針を事前に整備する
- 試用期間を活用し、実運用の課題を早期発見する
今後もAI技術は進化を続け、より高精度・高速・汎用的なAIツールが市場に登場すると予想されます。企業にとって重要なのは、この変化を受け身で眺めるのではなく、積極的に取り入れ、自社の強みに変えていく姿勢です。
まとめると、AIツールの活用は業務効率化にとどまらず、ビジネスモデルや働き方そのものを変える可能性を秘めています。今から計画的に導入と最適化を進めることで、未来の競争優位を確立することができるでしょう。




