この記事では、文章や画像を生成する最新の生成AIツール20選とその特徴、活用法、選び方のポイント、利用時の注意点を解説します。業務効率化や創作の幅を広げたい方が、自分に合ったAIサービスを見つけ、安全かつ効果的に活用できる知識が得られます。
目次
画像生成AIとは何か

画像生成AIの基本的な仕組み
画像生成AIとは、人工知能がテキストや条件を入力として、リアルな画像やイラスト、デザインなどを自動的に生成する技術を指します。特に近年では「画像 作成 AI」と呼ばれる分野が急成長しており、画像生成AIはクリエイターや企業の注目を集めています。この技術のベースとなっているのは、膨大なデータから学習したディープラーニングであり、人間の手作業を補助するだけでなく、全く新しいビジュアルを創り出せる点に特徴があります。
代表的な仕組みとしては次のようなものがあります。
- ディフュージョンモデル(拡散モデル):ノイズの状態から徐々にクリアな画像を生成する技術で、Stable Diffusionなどの人気サービスで使われています。
- GAN(Generative Adversarial Network):生成ネットワークと識別ネットワークが対決することで、よりリアルな画像を出力する仕組み。
- トランスフォーマーモデル:テキストを解析して意味を理解し、テキストの指示を反映した画像を生成する自然言語処理ベースのアプローチ。
これらの仕組みを活用することで、ユーザーは「森の中の未来都市」「油絵風の人物画」といった具体的な指示を入力するだけで、数秒から数分で高品質な画像を作成できます。従来の手作業デザインと比べて圧倒的にスピーディで、柔軟なビジュアル制作が可能になっています。
急速に普及している背景
画像生成AIが急速に普及しているのは、技術革新と社会のニーズが一致した結果です。インターネット上のコンテンツが増加し、SNSやマーケティングにおいて「視覚的に魅力的な画像」が不可欠になったことが大きな要因です。また、AI関連の研究が進む中で、高性能なGPUやクラウド環境が整備され、誰でも手軽にAIを利用できるようになったことも背景にあります。
普及を後押しする要素としては以下が挙げられます。
- 低コストでの利用:無料または低価格の生成AIサービスが登場し、個人から企業まで幅広く利用可能になった。
- 手軽さとスピード:デザイン知識がなくても、キーワード入力だけで数秒で画像を生成できる。
- 多用途への展開:広告、ブログ、商品デザイン、教育資料など、幅広い分野で応用が進んでいる。
こうした背景により、従来は専門知識がないと難しかった画像作成の世界が、今では誰でも簡単に取り組めるものへと変わりつつあります。
従来の画像編集ツールとの違い
画像生成AIと従来の画像編集ツールは、目的や操作のアプローチで大きく異なります。従来ツールは「既存の画像を加工する」ことが中心でしたが、画像生成AIは「ゼロから新しい画像を作る」ことができる点が最大の特徴です。
| 項目 | 従来の画像編集ツール | 画像生成AI |
|---|---|---|
| 主な用途 | 既存画像の修正・加工 | テキストや指示から新規画像を生成 |
| 必要なスキル | デザイン知識や編集スキル | プロンプト入力の工夫 |
| 作業効率 | コツを覚える必要があり時間がかかる場合も多い | 短時間で大量のアイデアを試せる |
| 得意分野 | 写真レタッチ、正確な修正 | 創造的なビジュアル生成、オリジナルコンセプト制作 |
そのため、従来の編集ツールと画像生成AIは競合関係というよりも補完関係にあります。例えば、AIで生成した画像をベースにフォトショップで微調整を行うといった組み合わせが非常に有効です。こうした使い分けにより、デザインや制作の可能性がこれまで以上に広がっています。
画像生成AIを活用するメリット

作業効率の向上
画像生成AIを活用する最大のメリットのひとつが、作業効率の大幅な向上です。従来であれば数時間から数日かかっていたビジュアル制作も、AIを用いれば数分で完成させることができます。例えば、背景やテクスチャ、アイキャッチ用の画像を一から作成する場合、デザインソフトの習熟やストック素材の調達に時間を取られてしまいがちです。しかし、画像作成AIを利用すれば、プロンプトを入力するだけで必要なイメージを瞬時にアウトプットできるため、時間を大幅に節約できます。
また、修正やバリエーション違いの作成も容易であり、制作現場における反復作業の負担を軽減します。これにより、担当者は単純作業に追われるのではなく、より創造的な部分や戦略的な業務に集中できる環境が整います。
デザインやクリエイティブの幅を広げる
画像生成AIは、ユーザーの発想を補完し、デザインやクリエイティブ表現の幅を大きく広げる力を持っています。多様なスタイルやアート表現を瞬時に生成できるため、これまでプロのイラストレーターやデザイナーに依頼しなければ実現できなかったようなビジュアルを、自分で手軽に試すことが可能になります。
例えば、アニメ調のイラストからフォトリアルな写真風画像まで、プロンプト次第で幅広い表現を一度に試すことができ、想像以上のアウトプットが得られることも少なくありません。そのため「アイデア出しの壁打ちツール」としても役立ち、クリエイティブな発想を刺激してくれる存在となります。
さらに、初心者でも直感的に操作できるサービスが多く、専門的なデザインスキルがなくても個性的な作品を生み出せる点は大きな魅力です。
マーケティングやビジネスにおける利用価値
画像生成AIの活用は、マーケティングやビジネスの分野にも大きなインパクトを与えています。キャンペーンバナーやSNS用コンテンツ、広告用のキービジュアルなどを素早く制作できるため、トレンドや市場変化に柔軟に対応可能です。スピード感のあるクリエイティブ制作は、市場に対してタイムリーに情報を発信する上でも大きな強みとなります。
また、同じプロンプトから複数の候補画像を生成し比較検討できるため、A/Bテストにおけるクリエイティブ検証の効率化にも役立ちます。加えて、商品コンセプトやブランドイメージの表現を多様な視点から試せるため、よりターゲット層に訴求するビジュアルを作成しやすくなります。
このように、画像作成AIは単なる作業効率化のツールに留まらず、ビジネスの競争力を高める戦略的な資産としての価値を持つのです。
画像生成AIサービス・アプリの選び方

生成可能な画像スタイルの豊富さ
画像生成AIを選ぶ際の大きなポイントの一つが「対応している画像スタイルの幅」です。AIによって得意とするジャンルは異なり、フォトリアルなものからアニメ風、イラスト調、抽象的なアートまで多様です。例えば、広告やバナーを作成したい場合にはリアル寄りのスタイルに対応しているAIが有効ですが、SNSのアイコンやブログの挿絵にはイラスト調、アニメ調のスタイルが求められる場合もあります。利用用途に合ったスタイルに柔軟に対応できるサービスを選ぶことで、創作の幅を広げることが可能になります。
操作性とカスタマイズ性
操作性がわかりやすいかどうかは、初心者にもプロにも大切な要素です。直感的に操作できるUI(ユーザーインターフェース)を持つサービスは、学習コストを抑えつつ効率的に作品を生み出せます。また、生成後に細かい編集ができたり、プロンプト入力に加えて詳細なカスタマイズ(色、構図、質感など)が可能なAIは、細部までコントロールしたいクリエイターに向いています。
出力される画像の品質
どれだけ操作が簡単でも、最終的なアウトプットの品質が低ければ活用の幅は狭まります。画像生成AIサービスを比較する際には、生成される画像の解像度やノイズの少なさ、リアリティ、そして商材に使える水準かどうかを確認することが重要です。また、高解像度の出力が可能かどうかは印刷物や大判広告に利用する際に非常に重要な要素になります。
料金やライセンス体系
画像生成AIは無料プランを提供するものもありますが、本格的に利用するには有料のサブスクリプションやクレジット購入が必要になることが多いです。料金体系はサービスによって異なり、月額制、従量課金制などさまざまです。さらに重要なのは「生成した画像をどこまで自由に使えるか」というライセンス条件です。コストだけでなく利用範囲の自由度も比較検討すべきポイントです。
商用利用の可否と著作権の取り扱い
ビジネスに画像生成AIを取り入れる場合には、商用利用が可能かどうかを確認することが必須です。サービスによってはクリエイティブを自由に使える場合もあれば、商用利用には追加ライセンスが必要な場合もあります。また、著作権の取り扱いにどのような規約があるかもチェックし、自社のプロジェクトに安心して活用できるかを判断するようにしましょう。
ヘルプ・サポートの充実度
初心者や非デザイナーにとって重要なのが、ヘルプやサポート体制の充実度です。公式ドキュメントやチュートリアル動画、FAQの豊富さはもちろん、チャットサポートやユーザーフォーラムなどで迅速に問題を解決できる体制が整っていると安心です。特に業務での利用を考える場合、迅速にトラブルを解決できるサポート体制があるサービスを選ぶことが、業務効率化に直結します。
おすすめの画像生成AIサービス・アプリ
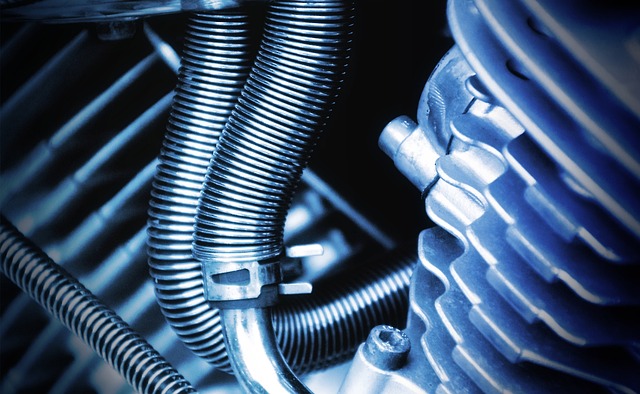
Adobe Firefly
Adobe Fireflyは、クリエイター向けに設計された画像生成AIで、自然な文章入力(プロンプト)をもとに多彩なビジュアルを作成できます。特徴として、商用利用に配慮した生成機能や、フォント・パターン・スタイルに強い点が挙げられます。特にデザインワークフローとの親和性が高く、PhotoshopやIllustratorといったAdobe製品と組み合わせて使うことで、制作効率を飛躍的に高められるのがポイントです。
Adobe Photoshop / Express
従来からデザインツールとして広く使われているPhotoshopも、AI機能を搭載し「生成塗りつぶし」などの革新的な画像生成が可能になりました。また、簡易版のAdobe ExpressでもAIを活用でき、初心者でも直感的に画像の編集や生成が行えます。特定の要素を追加したり、不要な部分を自然に消去したりと、従来のレタッチ機能がAIによってさらに強化されています。
Stable Diffusion / DreamStudio
Stable Diffusionはオープンソース型の画像生成AIで、最大の魅力は高いカスタマイズ性にあります。DreamStudioは公式のWebサービスで、ブラウザから簡単に操作でき、細かいパラメータ調整やスタイル指定が可能です。オープンソースの特性を活かして、多くのユーザーや開発者が改良を加えており、生成の自由度や学習モデルの多様性に優れています。
Midjourney
Midjourneyはアーティスティックな表現に強みを持つ画像生成AIです。Discordを通じて操作するユニークな仕組みを採用しており、コミュニティ内で他のユーザーと成果を共有しながら利用できます。特に幻想的で美しいアートやイラストの生成に定評があり、アーティストやデザイナーから高い支持を得ています。
DALL·E 3
OpenAIが開発したDALL·E 3は、自然言語理解に優れており、複雑なプロンプトでも意図を反映した精度の高い画像が生成できます。ChatGPTと統合されているため、会話を通じてプロンプトをブラッシュアップしながら自然に画像作成AIを活用できるのが魅力的です。多様なジャンルに対応するため、幅広い目的で導入しやすいサービスといえます。
Bing Image Creator
Bing Image Creatorは、Microsoftが提供する無料で利用可能な画像生成AIサービスです。DALL·Eの技術をベースにしており、検索と組み合わせることで誰でも簡単に高品質な画像を得られます。特に、初心者が試しやすいサービスとして人気があります。
Microsoft Designer
Microsoft 365と連携できるMicrosoft Designerは、プレゼン資料やSNS投稿に最適化された画像生成とデザイン機能を兼ね備えています。AIを活用してレイアウトやカラーリングを自動提案してくれるため、デザインスキルに自信がなくても高品質な作品を仕上げられます。
Canva
Canvaはオンラインデザインツールとして定評がありますが、AIによる画像生成機能も提供しています。テンプレートと合わせて利用できるため、簡単にプロフェッショナルなデザインを作成可能です。SNSバナーやプレゼン資料など、ビジネスから個人利用まで幅広く対応できます。
Picsart
Picsartは写真編集アプリとして有名ですが、AI画像生成機能によって一層便利になっています。スマートフォンから気軽に利用でき、フィルターやステッカーと組み合わせてクリエイティブなコンテンツを作成しやすいのが特徴です。SNS向け画像の作成に適しています。
MyEdit
MyEditは、写真や音声編集機能を備えつつAI画像生成にも対応しているオンラインツールです。操作がシンプルで、初心者でも短時間でユニークな画像を作れるため、気軽にAIを取り入れたいユーザーにおすすめです。
NovelAI
NovelAIは、特にアニメ調のイラスト生成に特化した画像作成AIです。細かいキャラクターデザインや背景描写まで美しく仕上げられるため、イラストレーターや同人活動をしているユーザーから高い人気を集めています。自由なカスタマイズが可能で、オリジナリティのある作品を生み出せます。
PixAI.Art
PixAI.Artはアニメ系やイラスト系の生成に強いオンラインサービスです。簡単に操作できるユーザーインターフェースで、キャラクター設定やシーンの雰囲気を指定しやすく、作品制作をサポートしてくれます。趣味だけでなく商用利用にも活用しやすい点が魅力です。
Artbreeder
Artbreederは、既存の画像をベースにAIが新しいビジュアルを生成し、さらに「遺伝子操作」のように画像を調整できるユニークなサービスです。ポートレートや風景を多様に組み合わせ、独創的な作品を作れるため、実験的な表現を楽しみたいユーザーに支持されています。
DeepArt
DeepArtは、任意の写真を名画風やアート作品風に変換できるAIサービスです。ニューラルスタイル転送を採用しており、ユーザーが指定した画風を自然に適用して新しいビジュアルを生成します。アーティスティックな演出に適しており、SNSやポートフォリオ作品にも活用できます。
AIピカソ
日本発のサービスであるAIピカソは、初心者でも気軽に使えるシンプルな画像生成AIアプリです。スマホから手軽に操作でき、SNS投稿用のイラストやデザインを短時間で生成できます。日本語でのプロンプト入力に対応しているため、難しい英語指示を使わずに思い通りの作品を生み出せます。
画像生成AIの活用シーン

SNSやブログ用のアイキャッチ作成
SNS投稿やブログ記事において、目を引くビジュアルはユーザーの関心を惹きつける大切な要素です。画像生成AIを使えば、記事の内容やテーマに合わせて独自性のあるアイキャッチを短時間で作成できます。例えば「未来的な都市」「やさしい雰囲気のイラスト」「モダンなビジネス風デザイン」などキーワードを指定するだけで、多彩なスタイルの画像を自動生成可能です。これにより、デザイン経験がない人でも印象的なビジュアルを手軽に取り入れられます。
マーケティング資料や広告バナー
広告やキャンペーンに使用するバナーは、ターゲット層や訴求ポイントに即したデザインが求められます。画像生成AIを活用すると、製品やサービスの特長に合わせて複数のデザイン案をスピーディーに生成でき、A/Bテストにも役立ちます。またサイズやフォーマットを調整しやすい点もメリットで、Web広告からSNS広告まで幅広いチャネルに対応可能です。
製品・サービスのコンセプトデザイン
新しい製品やサービスを企画する際、ビジュアルイメージをチームで共有することは重要です。画像生成AIで作成したコンセプト画像を用いれば、アイデア段階でのビジョンを素早く具現化できます。たとえば「環境にやさしいイメージのパッケージデザイン」や「未来志向のUIデザイン」を生成して、関係者間で意思疎通をスムーズに進められるのが利点です。
アニメーションやゲーム制作への応用
アニメーションやゲームといったエンターテインメント分野でも、画像生成AIは大いに役立ちます。キャラクターデザイン、背景美術、アイテムのコンセプトアートなど、制作初期のクリエイティブ作業を効率化できます。特にプロジェクトが大規模になるほど時間やコスト削減の効果が大きく、企画段階でもイメージ共有を容易にしてくれます。
プレゼン資料や企画書の補助素材
ビジネスプレゼンにおいて、テキストだけでなく視覚的な資料を提供することは説得力を高める上で不可欠です。画像生成AIは、説明したいテーマに合わせて図解やビジュアルイメージを自動生成でき、抽象的な概念を分かりやすく伝える補助的な役割を果たします。特に企画書や提案資料を限られた時間でまとめる際に重宝されます。
画像生成AIの使い方ガイド

基本的なプロンプト入力のコツ
イメージするビジョンを具体的に説明する
画像生成AIで理想の結果を得るためには、まず自分が実現したいビジョンをできる限り具体的に伝えることが重要です。たとえば「猫のイラスト」では漠然としていますが、「青い瞳を持った黒猫が窓辺に座っている水彩画風のイラスト」といった具合に、被写体・特徴・シーン・質感まで詳細に記述すると、生成される画像の精度が高まります。プロンプトが明確であればあるほど、AIはユーザーの意図を的確に反映できます。
構図やスタイルを明確に指示する
構図やスタイルを指定することで、より狙い通りの画像を生みやすくなります。例えば「俯瞰視点」「背景は夜空」「油絵スタイル」「写真のようなリアルさ」といった要素を追加するだけで仕上がりは大きく変わります。特に商用利用やプレゼン用のビジュアルを作成したい場合には、スタイルやアングルをしっかりとプロンプトに組み込むことが欠かせません。
改善と試行錯誤を繰り返す
最初の生成で理想の画像が得られない場合も少なくありません。そのような時は、プロンプトを細かく修正し、繰り返し生成を試みることが成功への近道です。例えば「光の当たり方が弱かった」と感じた場合、「強い逆光で」「明るい日差しを受けて」と修正を加えると、イメージに近い結果が得られることがあります。画像生成AIは試行錯誤を前提としたツールであり、小さな指示の違いが作品の完成度を大きく左右します。
初心者でもできるステップごとの操作例
ツールにアクセスしAI画像生成を選択
まずは利用する画像生成AIのツールやアプリにアクセスし、メニューから「AI画像生成」機能を選択します。サービスによってはテキスト入力専用の画面が用意されており、ここでプロンプトを入力できるようになっています。初心者の方は公式のチュートリアルやガイドを参考にすると安心です。
スタイルを選んでプロンプトを入力
続いて、どのようなスタイルで画像を生成するのか選択します。例えば「アニメ風」「イラスト」「写真風」「油絵風」などが一般的です。その上で、想像しているイメージをプロンプトに入力します。この際、具体的でわかりやすい指示を加えることが生成精度を上げるポイントです。
必要に応じて参考画像をアップロード
多くの画像生成AIでは、参考画像をアップロードする機能が搭載されています。参考画像を提示することで、AIにより正確なイメージを伝達でき、仕上がりが自分の意図に近づきます。ブランドカラーやキャラクターデザインを反映させたい場合にも有効です。
生成結果を保存・活用する
生成された画像は気に入ったものをダウンロードして保存しましょう。その後、SNS投稿のアイキャッチやプレゼン資料、クリエイティブ制作など、さまざまなシーンで活用できます。また、生成結果を振り返り、「もっとこうしたい」と思う部分を次回のプロンプトに反映することで、より完成度の高いビジュアルを生み出すことができます。
画像生成AIを利用する際の注意点

プライバシーや肖像権の尊重
画像生成AIを活用する際にまず重要となるのが、プライバシーや肖像権の配慮です。特定の人物の顔写真や特徴をそのまま学習データやプロンプトに使用すると、本人の同意なしに肖像を利用してしまう可能性があります。これは法的なトラブルや社会的な信頼の失墜につながりかねません。
例えば、知人や著名人の顔をもとにした画像を生成してSNSに公開する場合、本人の意図に反した利用になれば深刻な問題を引き起こします。したがって、画像生成AIでは架空の人物や権利関係が整理された素材を活用することが望まれます。
著作権やライセンスへの配慮
画像生成AIで作成されたコンテンツは、元データの学習に著作物が含まれている場合があります。そのため、生成結果を商用利用する際には、著作権やライセンスの扱いを十分に理解しておく必要があります。
各サービスには利用規約やライセンス体系が明記されており、それに従うことで安心してコンテンツを活用できます。特に商業利用を予定しているユーザーは、二次利用や商標への影響も事前に確認すると良いでしょう。
不適切なコンテンツ生成の防止
文字通り「何でも生成できる」ことは利点ですが、一方で不適切な画像を作り出してしまうリスクもあります。過激な表現や差別的なビジュアル、社会的に不快感を与えるコンテンツを意図的・無意識に生成してしまう可能性があり、これを防ぐため各ツールには利用規約が設けられています。
ユーザー側も倫理的な視点を持ち、公共の場に公開すべきではない画像制作は避けることが重要です。
SNS公開時の炎上リスク対策
SNSに画像生成AIを用いて作成した作品を投稿する際には、炎上のリスクを考慮する必要があります。例えば、他人の権利を侵害した画像やセンシティブなテーマを扱った画像は、拡散のスピードが速いSNSでは大きな問題に発展しやすいです。
炎上を避けるためには、
- 著作権や肖像権を侵害しない素材を利用すること
- ユーモアや風刺を込める場合も誤解を招かない表現にすること
- 公開前に第三者に確認してもらうなどリスク評価を行うこと
といった対策が有効です。
AI生成であることを明示する透明性
最後に、AIによって生成されたコンテンツであることを明示する「透明性」も重要です。ユーザーや閲覧者が自然な画像だと誤解する可能性があり、それが報道や教育、広告といった分野では信頼性の失墜につながります。
SNSに投稿する際には「#AI生成」や「AIで作成した画像です」と明記するだけでも、誤解を避けられます。また、企業がマーケティングに活用する場合も、信頼性を担保するためにこの一言を添えることが推奨されます。
まとめ:画像生成AIを賢く活用するために

画像生成AIは、これまで専門的なスキルや時間が必要だったデザイン作業を効率化し、誰でもクリエイティブな表現に挑戦できる可能性を広げています。一方で、著作権や肖像権、生成物の取り扱いといったリスクについてもしっかりと認識することが求められます。単に便利なツールとして使うだけでなく、効果的かつ安全に活用するための判断力が必要です。
まとめると、画像生成AIを賢く活用するには以下の3つのポイントが重要です。
- 目的に応じて適切なサービスを選ぶ:利用する用途(SNS投稿、広告素材、プロジェクトのデザインなど)に合わせて、出力品質やライセンス条件を確認しましょう。
- プロンプトの工夫で理想に近づける:生成結果は入力次第で大きく変わります。具体的で明確な指示を与えることで、より精度の高い画像を得ることが可能です。
- リスクとルールを意識する:著作権侵害や不適切な利用を避けるため、利用規約や法的リスクを理解し、透明性を持って運用することが求められます。
今後も画像生成AIは進化し続け、デザインやビジネスの在り方をさらに変えていくと考えられます。便利さとリスクの両面を理解し、適切なルールを守りつつ活用することが、持続的にAIの恩恵を受けるための鍵となるでしょう。




