この記事では、ノーコードで生成AIアプリを開発できる「Dify」の特徴や使い方、料金プラン、活用例を紹介します。非エンジニアでも直感的に操作でき、チャットボットや要約アプリ作成など具体的な活用方法がわかるため、自社業務の効率化やAI導入の不安解消に役立ちます。
目次
Difyとは?

基本概要と特徴
Difyは、オープンソースで提供されている次世代のAIアプリ開発プラットフォームです。ノーコードで直感的にAIアプリを構築できる点が特徴であり、エンジニアだけでなく非専門職のユーザーでも活用できるように設計されています。
特に「dify 使い方」を学びたいユーザーにとって魅力的なのは、複数の大規模言語モデル(LLM)を組み合わせ、自由度の高いアプリ開発をサポートしている点です。
Difyの主な特徴は以下の通りです。
- ノーコード/ローコード対応:専門的なプログラミングスキルが不要で、GUIベースでAIアプリを設計可能。
- マルチモデル対応:OpenAI、Anthropic、Google Geminiなど複数のモデルに対応しており、柔軟な切り替えができる。
- ワークフロー設計機能:複雑な処理フローをビジュアルエディタで設計可能。
- 拡張性とオープンソース:独自のカスタマイズやプラグイン追加ができ、オンプレミス導入も可能。
- チーム開発向け機能:ユーザー権限やデータセット管理を備え、プロジェクト単位での協業に適している。
シンプルなUIながら、RAG(Retrieval Augmented Generation)などの高度な処理を実装可能なのも評価されており、社内の業務効率化から商用アプリまで幅広く対応できる点が大きな強みです。
開発できるアプリの種類
Difyを使うことで、幅広いジャンルのAIアプリを簡単に構築できます。たとえば、チャットボットや文章要約といった一般的なユースケースにとどまらず、ビジネスや研究開発にも応用可能です。dify 使い方を理解することで、以下のようなアプリを自在に設計できます。
- チャットボットやカスタマーサポートAI:自然な対話を実現し、FAQ対応や問い合わせ削減に利用可能。
- 文書生成・要約ツール:ニュース記事、レポート、社内資料の要約や自動生成が可能。
- 社内ドキュメント検索システム:RAGを活用することで社内ナレッジを効率的に検索できる。
- リサーチ支援・スクレイピングツール:ウェブから情報を収集・整理し、インサイトを提供するアプリの開発。
- エージェント型アプリ:外部APIと連携し、タスクを自動処理するアプリ開発も可能。
このように、Difyは単なるチャットAIの作成にとどまらず、業務効率化、情報検索、データ分析など多方面での応用を実現できるプラットフォームです。そのため、個人利用はもちろん、DX推進を目指す企業や組織にとっても大きな可能性を持っています。
Difyの主な機能と特長

ノーコードでAIアプリを開発できる
Difyは、プログラミングの専門知識がなくてもAIアプリを構築できるノーコード開発プラットフォームです。直感的なUI操作によって、プロンプト設計やワークフローの構築を行えるため、非エンジニアでもアイデアをすぐに試せる点が大きな魅力です。たとえば、チャットボットや自動文章生成ツールを最短数分で試作することが可能です。
複数のLLM(大規模言語モデル)に対応
Difyは、OpenAIやAnthropic、またはオープンソースのモデルを含めて複数のLLMプロバイダーに対応しています。シーンに応じて最適なモデルを切り替えられるため、コストや精度を考慮した柔軟なアプリ開発が実現できます。特定のモデルに依存しないアーキテクチャが、開発の自由度を高めています。
RAG(Retrieval Augmented Generation)による高度な検索機能
高度な情報検索を可能にするRAG(検索拡張生成)機能を備え、ユーザー独自のデータを参照しながらAIが回答を生成できます。大量のドキュメントやナレッジベースを組み込むことで、より正確でコンテキストに即した応答を実現できるため、社内FAQシステムやリサーチアシスタントの開発に適しています。
外部API・ツールとの連携性
Difyは外部サービスとの統合も容易で、REST APIや様々なツールと連携できます。これにより、既存の業務システムや外部のSaaSとシームレスに統合しながら、AIアプリケーションの拡張が可能です。たとえば、CRMやデータ分析ツールと組み合わせて、自動化や高度な分析を実現できます。
エージェント作成と自動化機能
Difyでは、エージェント機能を用いてタスク実行を自動化することができます。特定の条件に応じたアクションを定義し、複数のプロセスを自動で処理させることで、業務の効率化や人的リソースの削減に繋がります。特に繰り返しの多い業務フローにおいてその効果を発揮します。
データセット管理機能と拡張性
Difyはプロジェクト単位でデータセットを管理できる仕組みを備え、学習用データや参照データを整理するのに適しています。さらに、構造化データや非構造化データの取り扱いにも柔軟で、規模が拡大しても対応可能な設計となっています。これにより、小規模なPoCから大規模運用までスムーズにスケールできます。
オープンソースによるセキュリティ・オンプレミス対応
Difyはオープンソースとして公開されているため、コードの透明性が高く、セキュリティ要件に合わせたカスタマイズが可能です。オンプレミス環境や自社クラウドに導入することで、重要情報を外部に出さずに利用でき、金融や医療などセキュリティ要件の厳しい業界でも安心して利用できます。
開発を効率化するテンプレート機能
豊富なテンプレート機能が搭載されており、ゼロから開発を始める必要がありません。よくある業務自動化やチャットアプリ、文章要約などのテンプレートが用意されているため、それを基にカスタマイズするだけでスピーディにプロジェクトをスタートできます。これにより、試作から本格運用への移行を効率的に進められます。
Difyの最新アップデート情報

メタデータフィルタリング機能の追加
Difyの最新アップデートでは、「メタデータフィルタリング機能」が新たに追加されました。この機能により、AIが利用するデータ検索結果をメタデータに基づいて効率的に絞り込むことが可能になります。従来の検索機能では関連度スコアやテキスト内容を中心に抽出が行われていましたが、メタデータを活用することで、より精密な情報取得やビジネス要件に合わせたデータ活用が容易になります。
- ドキュメントの作成日時や更新日時を基準にした抽出
- データのカテゴリやタグ付けでの検索制限
- 顧客IDや業務コードを用いたセグメント化
これにより、例えば「最新の議事録だけを対象に要約する」や「特定の案件に関連するドキュメントのみを回答に利用する」といった応用が可能になり、Difyの使い方は従来以上にビジネス現場へ直結する実用的なものとなっています。
エージェントノードの導入
さらに注目すべきは、「エージェントノード」が導入された点です。これはワークフロー内でAIエージェントをノード化して利用できる仕組みで、タスクごとに異なるAIロジックを柔軟に組み合わせられるようになりました。従来は固定的な処理フローでの自動化が中心でしたが、この機能により複雑な意思決定やタスク分岐が可能になります。
- ユーザーの入力内容に応じて異なるプロセスへ振り分け
- API連携や外部サービス接続を組み込んだ多段階処理
- エージェント同士の協調による業務自動化フロー構築
例えば、カスタマーサポート分野では「FAQ回答 → 複雑な相談時は人間オペレーターへ引き渡し」といった高度な自動化シナリオを構築でき、dify 使い方の幅を大きく広げています。
プラグイン拡張機能対応
さらに利便性を向上させるアップデートとして、プラグイン拡張機能にも対応しました。これにより、開発者や利用者はDifyの標準機能に加えて、外部の拡張機能を組み込むことで、自身のワークフローやアプリケーションに合わせた独自のカスタマイズが可能となります。
具体的には以下のような使い方が想定されています。
- 外部データベースやCRMとの連携プラグイン導入
- 自然言語処理の高度化や翻訳機能の追加
- 業務特化型APIとの組み合わせによる効率化
今後、サードパーティによるプラグイン提供も拡大していくことが予想され、オープンな開発エコシステムとしての魅力がさらに増しています。この拡張性は、Difyを導入する際に「標準機能+必要に応じた拡張」で運用できる大きなメリットとなり、ユーザーにとって持続的な競争優位性を生み出す鍵となるでしょう。
Difyの導入方法と基本設定
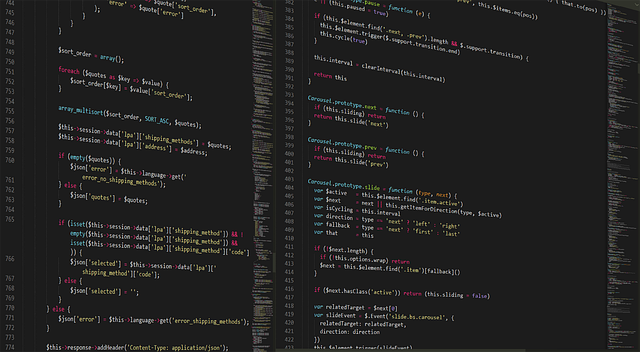
アカウント作成とログイン方法
Difyを利用するための第一歩は、公式サイトでのアカウント作成です。メールアドレスやGitHub、Googleアカウントを利用して簡単に登録することができます。個人で利用する場合でも、チームで利用する場合でも、最初にアカウントを作成することでブラウザ上からすぐに開発環境へアクセスできます。
具体的には、以下の流れで進めます。
- 公式サイトにアクセスし、「Sign Up」をクリック
- メールアドレスもしくは外部アカウント(Google / GitHub)で登録
- 登録した情報でログインし、ダッシュボードにアクセス
ログイン後は、自分専用のワークスペースが用意されるため、すぐに「dify 使い方」を学びながらアプリ開発を開始することが可能です。
モデルプロバイダーとAPIキーの設定
アカウントを作成した後は、利用する大規模言語モデル(LLM)のプロバイダーとAPIキーを設定する必要があります。DifyはOpenAIやAnthropic、Azure OpenAI、Google AI Studioなど複数の提供元に対応しており、ユーザーのニーズに合わせて選択可能です。
設定方法は以下の通りです。
- ダッシュボードの「Settings」から「Model Providers」を選択
- 利用したいプロバイダー(例:OpenAI)を選ぶ
- 各プロバイダーの管理画面から取得したAPIキーを入力
- 接続テストを実行し、正常に動作するか確認
この設定を済ませることで、プロジェクト内で指定のモデルを呼び出せるようになります。複数のプロバイダーを切り替えながら利用できる点もDifyの大きな強みです。
開発環境(ブラウザ版 / ローカル版)の準備
Difyは、クラウド上でそのまま利用できるブラウザ版と、自分のマシンにインストールして動作させるローカル版の2種類の環境に対応しています。用途や開発規模に応じて、どちらを利用するかを選択すると良いでしょう。
ブラウザ版の準備は非常にシンプルで、アカウント作成後すぐに利用可能です。特に初学者や試験的にプロジェクトを始めたい場合にはこちらが最適です。
一方で、ローカル版はDockerを利用して環境を構築する必要があります。こちらはオンプレミスでの利用や、セキュリティ要件から外部クラウドに依存できないケースに有効です。
- Dockerをインストール
- Difyの公式リポジトリをクローン
- 環境設定ファイルにAPIキーやモデル情報を追記
- コンテナを起動し、ローカルでDifyにアクセス
クラウド環境にデータを置きたくない場合はローカル版を選択することが推奨されます。一方で簡単に試したい段階ではブラウザ版を利用するのが効率的です。
【ブラウザ版】Difyの使い方

ワークフローの選択とアプリ基本情報の入力
ブラウザ版のDifyを利用する際、まず行うべき重要なステップが「ワークフローの選択」と「アプリ基本情報の入力」です。これらは、開発するアプリケーションの骨組みを決定する段階であり、後のプロンプト設計や機能追加をスムーズにするための基盤となります。ここでの設定が不十分だと、アプリ全体の方向性に影響を与えてしまうため、しっかり押さえておく必要があります。
まず、「新しいアプリケーションを作成」ボタンをクリックすると、テンプレートの選択画面やワークフローの設定画面が表示されます。Difyでは、チャット形式・問い合わせ処理・コンテンツ生成など目的別のワークフローが用意されているため、開発するユースケースに応じて最適なものを選びましょう。例えば、社内FAQシステムを作りたいなら「チャットボット」ワークフロー、記事の自動生成を目指すなら「テキスト生成」ワークフローを基盤とするのが効率的です。
次に、アプリの基本情報を入力します。ここで設定するのは以下の項目です。
- アプリ名:ユーザーや管理者がすぐに識別できる分かりやすい名称を設定
- 説明文:アプリの目的や利用シーンを簡潔に記載することで、後の共有や管理時に便利
- 公開設定:プライベートな利用か、チームや社外ユーザーへの公開を想定するかを選択
- タグやカテゴリー:複数のアプリを管理する際に有効な整理機能
これらを正しく設定することで、後のワークフロー編集・プロンプト調整のプロセスが格段に楽になり、Difyの使い方を最短ルートでマスターできるようになります。特に初めてブラウザ版Difyを利用する方は、アプリの設計方針を明確にしながら進めるのが成功のポイントです。
【ローカル版】Difyの使い方

Dockerのインストール
ローカル環境でDifyを利用するためには、まず前提としてDockerのインストールが必要となります。Dockerを利用することで、環境構築時の依存関係やバージョン差異によるトラブルを回避し、簡単かつ安定した形でDifyを稼働させることが可能です。
Dockerのインストール手順は以下のようになります:
- 公式サイト(Docker公式ページ)からお使いのOS(Windows / macOS / Linux)に対応したインストーラーをダウンロードします。
- インストーラーを実行し、画面の指示に従って設定を完了させます。
- インストール後、ターミナル(またはコマンドプロンプト)を開き、以下のコマンドを実行します。
docker --version
docker compose version
上記のコマンドにより、DockerおよびDocker Composeのバージョン情報が正しく表示されれば、インストールは正常に完了しています。
特にWindows環境では、WSL2(Windows Subsystem for Linux 2)が有効化されていないとDocker Desktopが正しく動作しないため、事前に設定を確認しておくことをおすすめします。また、macOSやLinuxユーザーの場合は比較的スムーズに導入でき、追加の仮想化設定も不要です。
この環境が整うことで、Difyを効率的にローカルで起動し、安心してアプリ開発を進められるようになります。次に、具体的なDifyのダウンロードと環境構築のステップへと進みます。
Difyで作れるアプリと活用事例

チャットボット開発
Difyを活用すれば、カスタマーサポートやFAQ対応に特化したチャットボットを直感的に作成できます。ノーコードでワークフローを設定し、シナリオに沿った回答パターンを柔軟に構築できるため、従来のルールベース型チャットボットよりも自然な会話が可能です。業種を問わず、社内ヘルプデスクや顧客対応の自動化に役立ちます。
Webページ要約・記事自動生成ツール
ニュース記事や専門的なWebページの内容を短時間で要約したり、指定したテーマに基づいて記事を自動生成するアプリもDifyで開発できます。SEO用のコンテンツ作成やレポートの下書きとして使えば、ライティング業務の効率化に大きく貢献します。特に「dify 使い方」を知りたいユーザーにとっても、自動生成アプリはコンテンツ作成の代表的な成功事例です。
音声認識・音声アプリ
近年ニーズが高まっている音声認識アプリも、Difyなら容易に構築できます。ユーザーの音声をテキスト化し、翻訳や要約、指示の実行などに応用可能です。会議の議事録作成や多言語対応のカスタマーサポートなど、ビジネス現場での利便性が高い点が特長です。
Webスクレイピング・情報収集
インターネット上の膨大な情報を効率的に収集・整理するWebスクレイピングツールも、Difyを利用して開発できます。APIや外部サービスとの連携機能を使えば、マーケットリサーチやニュース分析を自動化でき、担当者の業務時間を削減できます。データ分析の前段階を効率化することにより、より深いインサイトの抽出が可能になります。
社内ドキュメント検索システム
ナレッジ共有を効率化する社内検索システムもDifyで実装可能です。PDFやテキスト、社内向けのマニュアルといったドキュメントをアップロードしておけば、自然言語での質問に対して最適な情報を返す仕組みを構築できます。既存の知識を最大限活用し、社員の情報探索コストを減らせる点が大きな魅力です。
マーケティング分析・レポート作成支援
マーケティングデータをもとにインサイトを抽出し、自動的にレポートにまとめるアプリケーションも構築可能です。キャンペーン効果の測定やKPI分析を自動化することで、マーケターはより戦略的な意思決定に時間を割けるようになります。ExcelやBIツールとの連携も可能で、業務全体の効率化が期待できます。
業務自動化ツールやスケジュール管理
日々の業務プロセスを自動化するツールや、スケジュールをAIが最適化してくれるアプリもDifyの得意分野です。タスク管理やリマインダー、リソース配分を効率化することで、個人の生産性向上だけでなく、チーム全体のワークフロー改善にもつながります。特にバックオフィス業務の効率化に大きな効果があります。
Difyの料金プラン
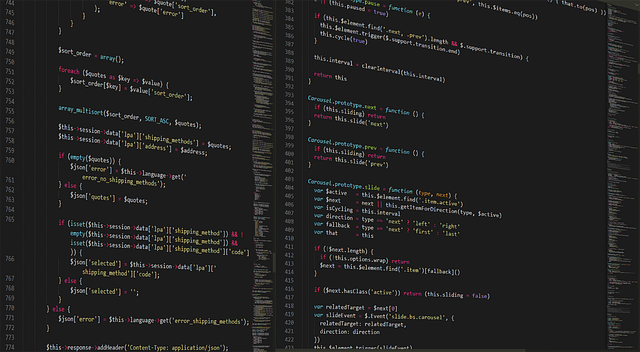
Sandbox(無料プラン)の特徴
Difyを初めて利用するユーザー向けに提供されているのが、Sandbox(無料プラン)です。無料で利用できることから、学生や個人開発者、導入検討をしている企業の担当者がまずDifyの使い方を体験するために最適な選択肢となっています。
このプランでは、基本的な機能がすべて利用可能であり、ノーコードでAIアプリを開発したり、複数のLLMを試すことができます。ただし、利用には制限も設けられており、例えば実行可能なリクエスト数やデータセットの容量には上限があります。また、チーム開発や大規模な商用利用には不向きです。
- 初期費用ゼロで利用可能
- 主要な機能を体験できる
- APIコール数やストレージ容量に制限あり
- 個人利用・小規模なプロジェクトに適する
まずはこのプランでDifyの操作性を確認した上で、必要に応じて上位プランへ移行するのがおすすめです。
Professionalプラン
Professionalプランは、個人開発者や小規模事業者が日常的にAIアプリ開発を進めたい場合に適したプランです。Sandboxよりも利用制限が緩和され、より多くのAPI利用回数やデータ保持が可能になります。
- 月額料金制で安定的に利用できる
- より大きなデータセット容量を確保
- 商用利用が可能
- 開発スピードと実用性を両立
無料版以上の拡張性を求めつつ、コストを抑えて利用したい場合に最適なプランといえるでしょう。
Teamプラン
複数メンバーでの開発・運用を前提としたのがTeamプランです。共同作業を効率化するための機能が追加されており、中小企業やスタートアップに向いています。チーム全体でDifyを使いこなすことで、プロジェクトのスピードアップと品質向上が期待できます。
- 複数ユーザーによる同時利用が可能
- 権限管理機能によるセキュリティ強化
- より高いAPI利用上限
- チーム開発や業務利用に最適
個人レベルでは対応しきれない規模のアプリ開発や、専門チームでの導入に向いているプランです。
Enterpriseプラン
大規模な企業導入を目的としたEnterpriseプランは、セキュリティ要件の厳しい法人や大規模利用を前提とした組織に特化しています。専用サポートやカスタマイズ対応、オンプレミス環境での展開といった柔軟性が提供される点が特徴です。
- 大規模データ処理・高負荷利用に対応
- 専任サポートや導入コンサルティングが利用可能
- セキュリティやガバナンスに考慮された設計
- オンプレミス導入オプションあり
特に金融、医療、公共機関など、セキュリティやデータ主権が重要な分野でのDX推進に適したプランとなります。
Difyを利用するメリットと注意点
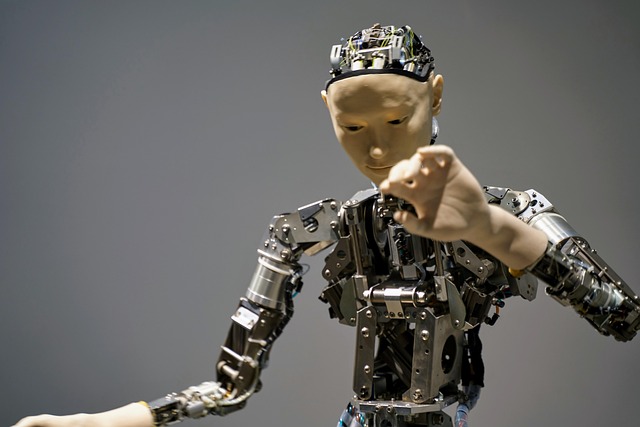
非エンジニアでも直感的に使える
Difyの大きな魅力のひとつは、プログラミングの経験がない人でも直感的にAIアプリを作成できる点です。ドラッグ&ドロップ操作やシンプルなプロンプト設定機能によって、コードを書かずにワークフローを構築できます。そのため、非エンジニア層でも自分のアイデアを形にしやすく、ビジネス部門やマーケティング担当者など幅広い職種で活用が進んでいます。
- 直感的なUIで開発のハードルが低い
- 試行錯誤しながら短期間でアプリを作成可能
- IT部門に頼らず業務効率化ツールを自作できる
商用利用が可能
Difyは個人利用にとどまらず、商用利用に対応しているため、ビジネス現場でも安心して導入できます。自社専用のチャットボットや自動化ツールを開発し、そのまま業務システムに組み込むことも可能です。さらに、外部への提供を目的としたアプリ開発にも活用できるため、新規プロダクトやサービスの開発にもつながります。
このように、「アイデアをスピーディに実現し、市場に投入できる」点は、スタートアップから大企業まで幅広い層にとって大きなメリットとなります。
無料版の利用制限について
Difyには無料で利用できる「Sandbox環境」が用意されていますが、商用利用を前提とした場合には一定の制約がある点に注意が必要です。たとえば、利用できるリソースが限定される、APIコール数に上限があるなど、機能制限が設けられています。これにより、初期段階の試用や小規模プロジェクトでの検証には適していますが、本格的な運用を検討する場合には有料プランを検討する必要があります。
- 無料枠では実行回数やリソースに制限あり
- 高度な機能を利用するには有料プランへの移行が必要
- プロトタイピングや学習目的には十分活用可能
セキュリティ管理・情報漏えいへの注意点
AIアプリ開発において特に重要なのが、セキュリティと情報管理です。Difyはオープンソースとして公開されているため、自社の環境に導入して運用する「オンプレミス環境」での利用も可能ですが、その分管理責任も発生します。特に、個人情報や社内機密データを扱う場合には、アクセス制御や暗号化といった基本的なセキュリティ設計を徹底することが不可欠です。
また、外部APIと連携する際にはデータの送信先や取り扱いに注意が必要です。情報漏えいや不正アクセスのリスクを軽視すると、重大なトラブルにつながる可能性があります。そのため、運用前にセキュリティポリシーを明確化し、適切なルールを組織全体で共有しておくことが非常に重要です。
Dify活用のコツ

ワークフロー全体像を理解する
Difyを効果的に使いこなすためには、まず「ワークフロー全体像」を把握することが欠かせません。DifyはノーコードでAIアプリを構築できる強力なプラットフォームですが、単にプロンプトを設定するだけでは十分に活用できません。開発プロセスにおいては、データの入力から処理、そして出力に至る一連の流れを理解して設計することが重要です。
ワークフローの全体像を把握することで、アプリの完成度や運用性は格段に向上します。例えば、チャットボットを構築する場合でも「ユーザーの入力 → モデルによる処理 → 応答生成 → 必要に応じた外部連携」という一連のプロセスを意識することで、スムーズかつ使いやすいアプリを設計できるのです。
- 最初にユーザーからどのようなデータを受け取るのかを定義する
- AIモデルがどのように入力を処理し、出力を返すのかを整理する
- 必要に応じて外部APIやエージェントを組み込み、追加機能を実現する
- 出力結果をどの形式で表示・返却するかを決める
特に初めてDifyの使い方を学ぶ段階では、細かい設定に入る前に、アプリ全体がどのように動くかを紙やホワイトボードに書き出すと理解が深まります。ワークフローを俯瞰することこそが、効率的な開発と将来的なスケーラビリティ確保につながるのです。
まとめ

Difyを活用した効率的なAIアプリ開発への第一歩
Difyはノーコードで直感的に操作できることから、専門的なプログラミングスキルがなくてもAIアプリの開発を始められる点が大きな魅力です。「dify 使い方」を理解することで、初学者でもAIを業務やサービスに組み込みやすくなるため、効率的かつスピーディにアイデアを形にできます。さらに、複数のLLMに対応しているため、自社のニーズに合ったモデルを柔軟に活用できる点も開発効率を高める要因となります。
最初の一歩としては、無料で利用できる環境から試してみることをおすすめします。小規模なプロジェクトで「使い勝手」や「開発フローの感覚」を掴むことで、本格的な業務適用にスムーズにつなげられるでしょう。Difyを活用すれば、AI開発の参入障壁をぐっと下げ、新しいサービスやソリューションへの挑戦を現実的なものにできます。
今後の進化とDX推進における可能性
Difyはオープンソースとして継続的に開発が進められており、今後もさらなる機能拡張が期待されています。たとえば、RAG機能の高度化や外部サービスとの連携強化は、企業の業務効率を飛躍的に高める可能性を秘めています。また、チーム開発やオンプレミス対応など、より現場のニーズに即した使い方が広がっていくと考えられます。
企業がDXを推進する上で、Difyのような柔軟かつ拡張性の高いAIプラットフォームを活用することは大きな武器になります。社内業務の自動化、データ分析の精度向上、新規サービス開発など幅広い領域で活躍できるため、競争力を高める戦略的ツールとして注目すべき存在です。
つまり、Difyは単なるAI開発プラットフォームにとどまらず、DX推進の加速装置となる可能性を秘めているといえるでしょう。今後の動向をチェックしつつ、積極的に活用シナリオを描いていくことで、企業や個人が新しい価値を生み出すチャンスにつながります。




