この記事では、React Flowでドラッグ&ドロップ可能なフローチャート/ダイアグラムを作る方法を、導入からノード・エッジ描画、カスタマイズ、複雑化の例まで具体的に解説します。AstroやStreamlit連携、onNodeDrag不具合の原因と修正、ELKによる自動レイアウトも扱い、実装・選定・トラブル解決に役立ちます。
目次
React Flowとは何か:できることと採用メリット

React Flowの概要とユースケース
React Flowは、React上でインタラクティブなノード(箱)とエッジ(線)を用いたダイアグラムを構築できるライブラリです。単に図を「描画する」だけでなく、ユーザーがノードを動かしたり、接続を作ったり、選択・編集したりといった操作を前提に設計されている点が特徴です。いわゆるフローチャート、ワークフロー、ネットワーク図のような「操作できるキャンバスUI」をWebアプリに組み込む用途で力を発揮します。
React Flowで実現しやすい代表的なユースケースは次の通りです。
- 業務フロー/承認フローの作成・編集UI(ノードを追加し、条件分岐を線で接続する)
- ETLやデータパイプラインの可視化(処理ステップをノード化して流れを表現)
- ルールエンジン/シナリオ設計(「もし〜なら」を分岐ノードとして組み立てる)
- システム構成図・依存関係グラフ(サービスやモジュールの関係を線で表す)
- LLM/生成AIのワークフロー(プロンプト、ツール呼び出し、分岐、評価などをノードで表現)
採用メリットとしては、Reactとの親和性が高く、UIコンポーネント設計(再利用・状態管理・権限表示など)をReact流で組み立てやすい点が挙げられます。ノードやエッジを「データ」として管理しやすいため、保存・共有・差分管理といったプロダクト要件にもつなげやすいのが強みです。
似たダイアグラム描画ライブラリとの違い(選定観点)
ダイアグラムを扱うライブラリは多数ありますが、React Flowは「Reactアプリに組み込み、ユーザーが編集できるダイアグラムUI」を作る目的に最適化されています。選定時は、単なる描画か、編集まで含めるか、またUI拡張の柔軟性をどこまで求めるかで比較すると判断しやすくなります。
React Flowを選ぶかどうかを決める主な観点は次の通りです。
- インタラクションの強さ:ドラッグ、選択、接続、ハンドル操作など「触って作るUI」が必要ならReact Flowが有力
- コンポーネント拡張:ノード内にフォームやボタン、メニューなどアプリ固有UIを入れたい場合、Reactコンポーネントとして構成しやすい
- 状態管理・データ連携:ノード/エッジをアプリ状態として扱いやすく、権限制御やバリデーション、保存などの要件と結びつけやすい
- 表現の中心が「ノード+エッジ」か:自由な図形描画(製図のような)より、グラフ構造(関係性)を表す用途に向く
- 将来の拡張:カスタムノード、独自の接続ルール、編集体験の作り込みが必要なら「素の描画ライブラリ」より優位になりやすい
一方で、最終成果物が「固定の図をきれいに描いて出す」だけで編集UIが不要なケースでは、より軽量な描画手段(SVG/Canvasや別種のライブラリ)が適することもあります。React Flowは「編集できること」に価値があるため、要件がインタラクティブ性を求めるかを最初に見極めるのが選定のコツです。
大規模サービスでの採用例から学ぶ活用ポイント
React Flowは、ノードベースの編集体験が重要な領域で広く使われています。代表例として、ワークフロー/自動化の文脈で知られるn8nは、ノードをつないで処理を組み立てるUIを提供しており、この種のプロダクト要件(多数ノードの操作、編集、視認性、拡張性)とReact Flowの得意領域が一致します。こうした採用例からは、「小さく作って終わり」ではなく、運用と拡張を見据えた設計が重要だと分かります。
大規模化を見据えてReact Flowを活用する際のポイントは次の通りです。
- “ノードの見た目”と“データ”を分離する:UIはカスタムノードで表現しつつ、永続化するのは最小限のグラフデータに絞ると保守しやすい
- 編集体験の一貫性を最優先する:選択状態、ハイライト、接続可否のフィードバックなど、操作の迷いを減らす設計が品質に直結する
- ノード種類の増加を前提に拡張ポイントを用意する:ノードタイプごとの設定項目や表示差分が増えるため、共通レイアウト・共通バリデーション方針を持つ
- パフォーマンスを意識した設計に寄せる:ノード数が増えると再描画やイベント処理が効いてくるため、更新単位やレンダリング範囲を意識する
- 権限・監査・共同編集など“プロダクト要件”と結びつける:誰が編集できるか、何を変更したか、といった要件はノード/エッジ操作と密接に絡む
React Flowは、プロトタイプでも本番でも同じ「編集UIの型」を使ってスケールさせやすいのが強みです。採用例に共通するのは、単なる図の描画ではなく、ユーザーが迷わず組み立てられる“道具”としてダイアグラムを提供している点であり、React Flowの価値が最も出る領域だと言えます。
導入手順:インストールと基本セットアップ

インストール方法と必要な前提
React Flowをスムーズに導入するには、まず「Reactが動くフロントエンド環境」と「React Flow本体+スタイル(CSS)」を正しく揃えることが重要です。ここを押さえておくと、後続のノード表示やエッジ接続などの実装でつまずきにくくなります。
前提として、React FlowはReact向けライブラリのため、React(一般的にはReact 18系)で動くプロジェクトが必要です。Next.js、Vite+React、Create React Appなど、Reactが利用できる構成であれば導入できます。
- Node.js / npm(またはyarn、pnpm)が使えること
- Reactプロジェクトが作成済みであること
- 画面にキャンバスを表示するため、描画領域(高さ)をCSSで確保できること
インストールはパッケージマネージャから行います。代表的なコマンドは以下です。
# npm
npm i reactflow
# yarn
yarn add reactflow
# pnpm
pnpm add reactflow
また、React Flowは見た目のベースとなるCSSを読み込まないと、ハンドルやキャンバスのスタイルが崩れて「動いているのに見づらい」状態になりがちです。基本セットアップの段階でCSSの読み込みまで行うのがポイントです。
CSSの読み込みを忘れると、ノードやハンドルの見た目が想定どおりにならず「壊れている」と誤解しやすいので注意してください。
最小構成で動かすための雛形(初期表示まで)
ここではReact Flowを「とりあえず初期表示する」ための最小構成を作ります。やることは大きく3つで、(1) CSSを読み込む、(2) nodes/edgesを用意する、(3) ReactFlowコンポーネントを描画して表示領域の高さを確保する、です。
まず、React FlowのCSSをアプリのエントリ付近(例:main.tsx や App.tsx)で読み込みます。
import 'reactflow/dist/style.css';
次に、最小のノードとエッジを用意して描画します。以下は「2つのノードを置いて、線でつないで表示する」雛形です。ポイントは、nodes に id / position / data を最低限入れること、そしてキャンバス用のコンテナに高さを与えることです。
import React from 'react';
import ReactFlow from 'reactflow';
import 'reactflow/dist/style.css';
const initialNodes = [
{
id: 'node-1',
position: { x: 0, y: 0 },
data: { label: 'Node 1' },
},
{
id: 'node-2',
position: { x: 200, y: 120 },
data: { label: 'Node 2' },
},
];
const initialEdges = [
{ id: 'edge-1-2', source: 'node-1', target: 'node-2' },
];
export default function App() {
return (
<div style={{ width: '100%', height: '60vh' }}>
<ReactFlow nodes={initialNodes} edges={initialEdges} />
</div>
);
}
初期表示でつまずきやすいのが「何も表示されない」問題ですが、原因の多くはコンテナの高さ不足です。React Flowはキャンバスを描画するために、親要素の高さが必要になります。上の例では height: 60vh を与えているため、画面に確実に表示されます。
- 画面が真っ白:コンテナの高さ(
height)が0になっていないか確認 - ノードが見えない:
nodesにpositionがあるか、idが一意か確認 - 見た目が崩れる:
reactflow/dist/style.cssを読み込んでいるか確認
ここまでで、React Flowの最小構成による初期表示は完了です。以降の実装(状態管理での更新やインタラクションの追加)に進む前に、この雛形がローカル環境で安定して描画できる状態を作っておくのが導入の近道になります。
基本操作を実装する:ノードを表示して動かす

React Flowの魅力は、ノード(箱)とエッジ(線)を「描いて終わり」ではなく、ユーザーが直接操作できるインタラクションを手早く実装できる点にあります。このセクションでは、まずノードを表示し、ドラッグで動かし、キャンバスをズーム・パンできる状態までを一気に作ります。ここまでできると、ワークフロー図や簡易エディタとしての土台が整います。
ノードを描画する基本
React Flowでノードを描画する基本は、nodes配列(各ノードのID・種類・座標・表示内容など)を用意し、<ReactFlow />へ渡すことです。最小限では「どこに」「何を」表示するかの2点が押さえどころになります。
- id:ノードを一意に識別するための文字列
- position:キャンバス上の座標(
{ x, y }) - data:ラベル等、表示に使うデータ(
labelなどを入れることが多い) - type:ノードの種類(未指定ならデフォルト)
まずは固定のノードを1〜2個出して、表示ができることを確認します。初期表示で意識したいのは、座標が近すぎて重なっていないか、画面外に出ていないかです。特に試作段階では、見失いにくい位置(例:左上寄り)に置くとデバッグが楽になります。
import React, { useMemo } from 'react';
import ReactFlow from 'reactflow';
import 'reactflow/dist/style.css';
export default function BasicNodes() {
const nodes = useMemo(
() => [
{
id: 'n1',
position: { x: 80, y: 80 },
data: { label: 'Node 1' },
},
{
id: 'n2',
position: { x: 320, y: 200 },
data: { label: 'Node 2' },
},
],
[]
);
return (
<div style={{ width: '100%', height: 500 }}>
<ReactFlow nodes={nodes} />
</div>
);
}
また、React Flowはコンテナのサイズが描画に直結します。高さが0だと何も表示されないため、height(例:500pxや100vh)を必ず確保してください。
ドラッグ&ドロップでノードを移動できるようにする
ノードをドラッグで動かせるようにするには、ユーザー操作で変化した座標を状態として保持し、React Flowから渡される変更イベントを反映する必要があります。固定配列のままだと、ドラッグしても描画が元に戻る(状態が更新されない)ため、「変更を受け取ってnodesに反映する」実装が重要です。
基本形は、useNodesStateを使ってnodesとonNodesChangeをセットで扱う方法です。これにより、ドラッグ移動・選択などの変更がイベントとして渡され、それをそのまま状態更新に適用できます。
import React from 'react';
import ReactFlow, { useNodesState } from 'reactflow';
import 'reactflow/dist/style.css';
const initialNodes = [
{ id: 'n1', position: { x: 80, y: 80 }, data: { label: 'Drag me' } },
{ id: 'n2', position: { x: 320, y: 200 }, data: { label: 'Me too' } },
];
export default function DraggableNodes() {
const [nodes, setNodes, onNodesChange] = useNodesState(initialNodes);
return (
<div style={{ width: '100%', height: 500 }}>
<ReactFlow nodes={nodes} onNodesChange={onNodesChange} />
</div>
);
}
ドラッグ操作を実装する上でのポイントは次の通りです。
- 状態管理が必須:
nodesを固定値にすると、移動しても永続化されません。 - パフォーマンス配慮:ノード数が増えると再レンダリングが重くなるため、初期値の生成は
useMemo等で安定させると安心です。 - 編集モードの制御:運用では「閲覧のみ」モードも必要になりがちです。ドラッグ可否の切り替えが必要なら、ノード側設定やReact Flow側オプションで制御する設計を考えます。
ここまでで、React Flowの“触れるダイアグラム”として最低限の体験(ノードが表示され、掴んで動かせる)が完成します。
ズーム・パンなどキャンバス操作の基礎
ノードを動かせるようになったら、次に必要になるのがキャンバスの操作性です。図が大きくなるほど、ズーム(拡大縮小)やパン(ドラッグで移動)がないと閲覧・編集が成立しません。React Flowでは、これらの基本操作をコンポーネント設定で扱えます。
一般的に押さえておきたいのは以下の操作です。
- ズーム:ホイールやピンチで拡大縮小
- パン:キャンバスを掴んで移動
- フィット:ノード全体が画面内に収まるように表示
まずは、ユーザーが迷わず操作できるよう、ズーム範囲(最小・最大)を適切に制限し、初期表示を整えるのが基本です。初期表示で便利なのが、全体が見えるようにするfitViewです。
import React from 'react';
import ReactFlow, { useNodesState } from 'reactflow';
import 'reactflow/dist/style.css';
const initialNodes = [
{ id: 'n1', position: { x: 80, y: 80 }, data: { label: 'Node 1' } },
{ id: 'n2', position: { x: 520, y: 300 }, data: { label: 'Node 2' } },
];
export default function CanvasBasics() {
const [nodes, , onNodesChange] = useNodesState(initialNodes);
return (
<div style={{ width: '100%', height: 500 }}>
<ReactFlow
nodes={nodes}
onNodesChange={onNodesChange}
fitView
minZoom={0.2}
maxZoom={2}
/>
</div>
);
}
ズーム・パンを導入するときの注意点としては、操作が過剰に自由だと「迷子」になりやすいことです。たとえば、極端にズームアウトできるとノードが見えなくなったり、ズームインしすぎて位置感覚を失ったりします。minZoom/maxZoomを設けるのは、体験面でもデバッグ面でも効果的です。
これでReact Flowにおける基本操作(表示・ドラッグ移動・ズーム/パン)の基礎が揃います。次の段階では、図として意味を持たせるために接続(エッジ)を扱えるようにしていきます。
エッジ接続の実装:ノード同士を線でつなぐ

React Flowでフロー図らしさを出すうえで欠かせないのが、ノード同士を結ぶ「エッジ(線)」です。エッジを描画できるようになると、処理の順序や依存関係、データの流れなどを視覚的に表現できます。このセクションでは、React Flowでエッジを追加して接続を表現する方法と、接続ルール(接続可否)やイベントの扱い方を整理します。
エッジを追加して接続を表現する
React Flowではエッジもノードと同様に「配列データ」として管理します。基本的には、source(接続元ノードID)とtarget(接続先ノードID)を持つオブジェクトをedges配列に追加すると、キャンバス上に線が描画されます。
最もシンプルな方法は、初期状態としてエッジを定義しておくやり方です。たとえば「AからBへ」を表現したい場合、次のようにエッジを用意します。
const initialEdges = [
{ id: 'e1-2', source: '1', target: '2' },
];さらに、ユーザーがドラッグ操作でノードのハンドル同士をつないだときにエッジを追加するには、React Flowが提供するonConnectイベントを使います。接続操作で渡されるconnection情報(source/targetなど)を受け取り、ヘルパーのaddEdgeで状態に反映させるのが定石です。
import React, { useCallback } from 'react';
import ReactFlow, { addEdge, useEdgesState } from 'reactflow';
function Flow() {
const [edges, setEdges, onEdgesChange] = useEdgesState([]);
const onConnect = useCallback((connection) => {
setEdges((eds) => addEdge(connection, eds));
}, [setEdges]);
return (
<ReactFlow
edges={edges}
onEdgesChange={onEdgesChange}
onConnect={onConnect}
/>
);
}この形にしておくと、React Flowの標準UI(ハンドルをドラッグして接続)に沿って、自然にエッジ追加を実装できます。業務要件によっては、エッジにlabelを持たせたり、typeを指定して線の見た目(直線/曲線など)を切り替えたりしますが、まずは「sourceとtargetの指定で接続が描ける」ことを押さえるのが重要です。
接続ルールやハンドリング(接続可否・イベント)
実運用のフローでは「何でもつなげて良い」ケースは少なく、React Flowでも接続可否(バリデーション)や、接続時のイベントハンドリングを設けることが多いです。ここでは代表的な考え方を、React Flowのイベントに沿って整理します。
1) 接続可否を制御する(誤接続を防ぐ)
接続可否の判定は、ユーザーが接続したタイミングでonConnect内でチェックする方法が分かりやすいです。たとえば次のようなルールが典型です。
- 同一ノードへの自己ループ(
source === target)は禁止 - 同じ接続(同じ
source→target)の重複は禁止 - 特定のノード種別同士だけ接続を許可(例:開始ノード→処理ノードはOK、終了ノード→開始ノードはNG)
- ハンドル単位で接続方向を制限(入力ハンドルには入るだけ、出力ハンドルから出るだけ等)
重複エッジを防ぐ例は次の通りです(edgesの状態を参照して判定します)。
const onConnect = useCallback((connection) => {
const { source, target } = connection;
// 自己ループ禁止
if (!source || !target || source === target) return;
// 重複接続禁止
setEdges((eds) => {
const exists = eds.some((e) => e.source === source && e.target === target);
if (exists) return eds;
return addEdge(connection, eds);
});
}, [setEdges]);接続可否の判定を入れないと、意図しない重複や循環が簡単に作れてしまい、後続の処理(保存・検証・実行)で不整合が起きやすくなります。
2) 接続に関するイベントを使い分ける
React Flowでは「接続が確定した瞬間」以外にも、エッジ操作に関連するイベントが用意されています。目的に応じてフックする場所を分けると、実装が破綻しにくくなります。
onConnect:ユーザーが接続を確定したときに呼ばれる(エッジ追加の起点)onEdgeClick:エッジ選択や、UI(削除ボタン表示など)のトリガーに使うonEdgesChange:削除・選択状態変更など、エッジ配列に対する変更をまとめて受ける
たとえば「エッジクリックで詳細を開く」「選択中だけ強調する」といった振る舞いは、onEdgeClickと選択状態の管理で実現します。一方、エッジの追加自体はonConnectに集約すると責務が明確になります。
3) 接続時にメタ情報を付与する(後工程のため)
接続は「線を引く」だけでなく、後で保存・実行・検証するための情報を持たせることが多いです。React Flowのエッジオブジェクトには任意のプロパティを持たせられるため、onConnectで追加するときに、たとえば次のような情報を一緒に入れる設計が考えられます。
- 作成日時や作成者(監査・履歴用途)
- エッジの種類(成功/失敗分岐、依存関係、参照など)
- ビジネス上の条件(例:分岐条件の式をラベルやdataに保持)
const onConnect = useCallback((connection) => {
setEdges((eds) => addEdge({
...connection,
id: `e-${connection.source}-${connection.target}`,
data: { relation: 'depends_on' },
}, eds));
}, [setEdges]);エッジ追加の時点で最低限のルール判定とメタ情報付与まで行うと、React Flow上の操作とアプリ側の整合性が取りやすくなります。
カスタマイズ:独自ノード・見た目・挙動を作り込む
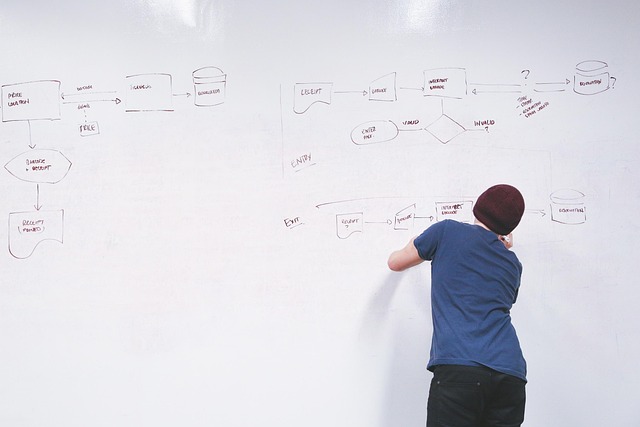
React Flowの魅力は、単にノードとエッジを表示するだけでなく、プロダクト要件に合わせて「UI」「見た目」「操作感」を深く作り込める点にあります。ここでは、React Flowを実務レベルで使い込むために重要なカスタマイズ領域として、カスタムノード、スタイル調整、ツールチップなどの補助UI追加を整理します。
カスタムノードを作成してUIを拡張する
React Flowでは、ノードを単なる四角い箱として表示するのではなく、任意のReactコンポーネントとして描画できます。これにより、ステータス表示、アイコン、入力フォーム、アクションボタンなどをノード内部に組み込み、業務アプリに必要な情報密度を保ったまま操作性を高められます。
基本は「ノードtype」と「nodeTypesマップ」を定義し、該当typeのノードを描画したいコンポーネントに紐付けます。ノード固有の表示内容は、dataに詰めて渡すのが一般的です。
// カスタムノード例(概念)
import { Handle, Position } from 'reactflow';
function StatusNode({ data }) {
return (
<div className="node status-node">
<div className="title">{data.label}</div>
<div className={`badge ${data.status}`}>{data.status}</div>
{/* 接続口(ハンドル) */}
<Handle type="target" position={Position.Left} />
<Handle type="source" position={Position.Right} />
</div>
);
}
// ReactFlowに渡す
const nodeTypes = { status: StatusNode };カスタムノード設計で意識したいポイントは次の通りです。
責務分離:表示はノードコンポーネント、状態更新は親(ストア)に寄せ、ノードは必要なイベントをコールバックで通知する
data設計:表示・判定に必要な最小限の値を持たせ、肥大化しすぎないようにする
操作の衝突回避:ノード内ボタンや入力がある場合、ドラッグ等の操作と競合しないようイベント伝播(例:クリック)を意識する
拡張性:同系統ノードを増やすなら、共通のベースコンポーネント化(タイトル領域、フッター、ハンドル配置など)で保守性を上げる
「ノード=UIコンポーネント」と捉えると、React Flowはダイアグラムというより“キャンバス上のUIレイアウト基盤”として活用できます。
スタイル調整(ノード/エッジ/ハンドル/背景)
React Flowの見た目を整えるうえで重要なのが、ノード・エッジ・ハンドル・背景(グリッド等)の一貫したデザインです。情報を扱うダイアグラムでは「読める」「迷わない」「状態が分かる」ことが最優先になるため、スタイルは装飾というより機能として設計します。
ノードのスタイルは、サイズ、余白、角丸、影、タイポグラフィ、状態(選択・エラー・無効)といった要素を整理して作ります。特に状態表現はUIの理解速度に直結します。
選択中:枠線を強調、背景を薄く変更
エラー:赤系の枠・バッジで明示
正常/稼働中:青系や緑系のバッジ(色弱配慮のため形状差も併用)
エッジのスタイルは、線の太さ・色・破線・矢印・ラベル表示などで意味を持たせられます。例として、通常フローは実線、条件付きは破線、重要経路は太線、といったルール化が有効です。React Flowではエッジtypeを使ってカスタムエッジを作ることもでき、ラベル位置や装飾をより細かく制御できます。
ハンドル(接続口)のスタイルは、接続可能性の分かりやすさに影響します。小さすぎると操作性が落ち、大きすぎるとノードの情報を邪魔します。推奨としては、
通常は控えめ(半透明や小さめ)
ホバー時に強調表示
接続できない状態はグレーアウト
のように「必要なときだけ見せる」設計が使いやすくなります。
背景(グリッドやドット)は、配置の目安・整列感を与える一方で、強すぎると可読性を下げます。薄い色で主張を抑え、ズーム時にうるさくならないパターンを選ぶのがコツです。背景は“情報”ではなく“補助”なので、コンテンツ(ノード/エッジ)より目立たないことが重要です。
また、スタイル調整の運用面では、個別にCSSを当て続けるよりも、デザインルール(色、余白、状態)をトークン化して統一する方が、ノード種別が増えたときに破綻しにくくなります。
ツールチップなど補助UIの追加
ダイアグラムは情報量が増えるほど、ノード上にすべてを載せると読みにくくなります。そこで有効なのが、ツールチップ、ポップオーバー、コンテキストメニューなどの補助UIです。React Flowでの補助UIは「表示は簡潔に、必要時に詳細を出す」という設計を実現する手段になります。
ツールチップは、ノードやエッジにマウスオーバーした際に補足情報(説明、ID、最終更新、担当、メモなど)を表示する用途に向きます。ポイントは、
遅延表示(意図しないチラつきを抑える)
表示位置(カーソル追従 or 対象固定)
ズーム時の可読性(フォントや最大幅、折返し)
を調整し、操作の邪魔にならないことです。
クリックで開く詳細パネル/ポップオーバーは、編集や追加操作を伴う場合に有効です。ノード内に入力フォームを詰め込みすぎるとドラッグや選択がしづらくなるため、詳細は外出し(オーバーレイやサイドパネル)にすると扱いやすくなります。React Flowの選択状態(どのノード/エッジが選ばれているか)に応じて、補助UIの表示内容を切り替える設計が定番です。
コンテキストメニュー(右クリック)は、削除、複製、リンクコピー、関連ノード追加など、頻繁に使う操作をまとめるのに向きます。操作の発見性が上がる一方で、誤操作防止のために破壊的操作(削除など)は確認導線を用意するなど、補助UI側のUXも合わせて設計すると安全です。
補助UIを上手く組み込むと、React Flow上の情報密度と可読性を両立できます。まずは「通常時はシンプル、必要なときだけ詳細」という原則で、ツールチップから段階的に導入するのがおすすめです。
応用例:より複雑なフロー/ネットワークを扱う設計

React Flowを「ノードを並べて線でつなぐ」段階から一歩進め、実運用に耐える複雑なフロー/ネットワークを扱うには、データ設計・前処理・可視性の工夫・ユーザー操作の扱いをセットで考える必要があります。ここでは、規模が大きくなっても破綻しにくい設計の勘所を整理します。
データ構造(nodes/edges)の設計と取得方法
React Flowの中心は nodes と edges の2配列です。複雑なグラフになるほど、画面表示の都合ではなく「ドメインデータをどう保持するか」から逆算して設計すると破綻しにくくなります。
まずは、ノード/エッジのID設計を明確にします。IDが安定しているほど、差分更新・選択状態の保持・サーバー同期が容易になります。
- ノードID:DBの主キーや業務上の一意キーを利用(例:
task:123) - エッジID:
sourceとtargetと関係種別から合成(例:task:123->task:456:depends) - リビジョン/更新時刻:競合解決や再取得判定のために持つ(必要なら)
次に、ノード/エッジの data に「UI向け情報」と「業務ロジック向け情報」を混ぜすぎないのがポイントです。React Flowは描画の器なので、data は表示や操作に必要な最小限に寄せ、詳細は別のストア(Redux/Zustandやサーバー取得結果)に置く設計がスケールします。
- nodes[].data:ラベル、状態(警告/完了など)、クリック時に参照するID程度
- edges[].data:関係の種類、重み、方向性の補助情報など
取得方法は大きく2系統あります。1つは「グラフとしてAPIが返す」方式、もう1つは「テーブルデータをクライアントでグラフ化する」方式です。どちらでもReact Flowに渡す形は同じですが、後者は前処理が重要になります。
- グラフAPI:
{ nodes: [], edges: [] }をそのまま受け取り、必要に応じて表示用にマッピング - 関係テーブル型:例)エンティティ一覧とリレーション一覧から、ノード/エッジを組み立てる
// 例:関係テーブル型の入力から React Flow 形式へ変換するイメージ
const entities = [
{ id: "A", name: "Service A" },
{ id: "B", name: "Service B" },
];
const relations = [
{ from: "A", to: "B", type: "calls" },
];
const nodes = entities.map((e) => ({
id: e.id,
type: "default",
position: { x: 0, y: 0 }, // 初期値(後段でレイアウト反映)
data: { label: e.name },
}));
const edges = relations.map((r) => ({
id: `${r.from}-${r.to}-${r.type}`,
source: r.from,
target: r.to,
data: { type: r.type },
}));グラフデータの前処理(整形・集約・計算)
複雑なネットワークをそのまま描くと、情報量が多すぎて読み取れないケースが頻発します。そのため、React Flowに渡す前に「整形」「集約」「計算」を行い、表示の目的に沿ったグラフへ変換するのが実務的です。
整形では、欠損や不整合を潰します。例えば、存在しないノードへのエッジを除外する、重複エッジを統合するなどです。
- 参照整合性:
source/targetが nodes に存在するか検証 - 重複の扱い:同一ペアの関係が複数あるなら束ねる(件数を
data.countに入れる等) - 表示不要データの除外:管理用ノード・内部イベントなどをフィルタ
集約は「縮約して見せる」ための処理です。代表例として、サブフローを1ノードに畳む、同種のノードをグルーピングする、といった手法があります。React Flow側はあくまで描画なので、どの粒度で見せるかの判断は前処理に寄せるほど運用が楽になります。
- クラスタリング:部署/ドメイン/タグ単位でまとめる
- レベル別表示:詳細(L2)/概要(L1)を切り替えられるよう、複数のグラフ表現を用意
- エッジ束ね:多数のエッジを「代表線+件数表示」にする
計算は「意味づけ」のための処理です。例えば、次数(入出力の多さ)に応じて重要ノードを強調する、到達可能性や依存関係の深さを算出して色分けするなど、可視化の価値を上げられます。
- 次数の算出:入次数/出次数を数えて注目ノードを抽出
- 到達/依存の計算:選択ノードからの影響範囲を事前計算してハイライト
- メトリクス付与:
nodes[].dataにスコアを載せ、表示(色・サイズ)に反映
フィルタリングや検索で見やすくする
大規模グラフでは「全部見せる」より「探して絞る」体験が重要です。React Flowはキャンバス操作に強い反面、情報の取捨選択はアプリ側の設計が成果を左右します。
フィルタリングは、表示対象のノード/エッジを減らすだけでなく、理解を助けるための「強調/非強調」も含めて設計します。
- 属性フィルタ:種別、ステータス、タグ、所有チームなどで絞り込み
- 関係フィルタ:特定のエッジ種別(例:depends/calls)だけを表示
- 近傍表示:選択ノードのNホップ以内だけを表示して密度を下げる
検索は、候補を出して「そこへ導く」体験にすると効果的です。検索結果をクリックしたら該当ノードを選択状態にし、周辺をハイライトして文脈を失わないようにします。
- インクリメンタル検索:入力に応じて候補リストを更新
- フォーカス:該当ノードを選択状態にして視覚的に目立たせる
- 周辺強調:接続ノードや接続エッジを強調し、理解を促進
また、フィルタ/検索の結果としてノードが消える場合、エッジの扱い(両端が表示されないエッジは非表示にする等)をルール化しておくと、見た目の一貫性が保てます。
ユーザー操作の取り扱い(選択・編集・追加/削除)
応用段階では「眺める」だけでなく、React Flow上で編集できることが求められます。ここで重要なのは、キャンバスの状態(選択・ドラッグ等)と、業務データ(ノード/エッジの実体)を分離し、操作の責務を整理することです。
選択は最も頻度が高い操作です。単一選択・複数選択・範囲選択などを想定し、選択中のIDを基準にサイドパネルで詳細を出す設計が一般的です。
- 単一選択:詳細パネルに属性表示、関連ノードをハイライト
- 複数選択:一括編集(タグ付け、削除、移動など)に接続
- 選択の永続化:フィルタ変更でも選択をどう扱うか(解除/維持)を決める
編集は「どこで編集するか」を決めるのが先です。ノード上でインライン編集するのか、フォームで編集するのかで、React Flow側の実装難易度とUXが変わります。重要なのは、編集結果を nodes に即時反映しつつ、保存(サーバー同期)は別アクションとして扱い、失敗時のロールバック方針も持つことです。
- インライン編集:素早いが誤操作対策(確定/キャンセル)が必要
- サイドパネル編集:項目が多い業務データに向く
- 楽観更新/悲観更新:保存失敗時の戻し方を事前に設計
追加/削除はデータ整合性に直結します。ノードを消したら接続エッジをどうするか、エッジ追加時に禁止ルール(自己ループ不可、特定タイプ間のみ接続可等)をどう適用するか、といった「業務ルール」を操作ハンドラに閉じ込めず、ルールとして再利用できる形にしておくと保守性が上がります。
- ノード追加:作成直後の初期属性、仮IDから確定IDへの切替を考慮
- ノード削除:関連エッジの自動削除、確認ダイアログ、復元(Undo)検討
- エッジ追加:接続可否の判定、重複防止、方向性(source/target)の扱い
最後に、操作ログや変更履歴(誰がいつ何を変えたか)が必要な領域では、React Flowの見た目の更新だけで完結させず、変更イベントを「ドメインイベント」として蓄積できる設計にしておくと、運用・監査・トラブル対応が現実的になります。
自動レイアウト連携:ELK等でノード配置を最適化する

自動配置の考え方と導入メリット
React Flowはノードとエッジを自由に描画・操作できる一方で、ノード数や接続関係が増えるほど「どこに配置すべきか」を手作業で決めるのが難しくなります。そこで有効なのが、グラフの構造(ノードとエッジのつながり)から最適な座標を計算する自動レイアウトです。代表的なエンジンとしては、Eclipse Public Licenseで提供されるELK(Eclipse Layout Kernel)があり、React Flowと組み合わせることで見やすいダイアグラムを安定して生成できます。
自動配置の基本的な考え方は「入力はグラフ構造、出力は各ノードの座標」という割り切りです。ユーザーの視点で読みやすい図にするために、レイアウトエンジンは以下のような制約や最適化を行います。
- 方向性の統一:左→右、上→下など、フローの読み方向を揃える
- 交差の最小化:エッジ同士の交差を減らし、視認性を上げる
- 重なりの回避:ノードが重ならないように間隔を確保する
- 階層化:有向グラフを層(レイヤ)に分け、依存関係が追いやすい配置にする
React Flowで自動レイアウトを導入するメリットは、見た目が整うだけにとどまりません。運用・開発面でも効きます。
- 初期表示が常に「読める図」になる:データが毎回変わっても、一定品質の配置で提示できる
- 手動調整コストを削減:ノード追加・削除のたびにレイアウトを作り直す手間を抑えられる
- 大規模グラフに強い:人手では破綻しやすいノード数でも、交差や密集を抑えやすい
- UX改善:見やすい配置は理解速度を上げ、誤操作や探索コストを減らす
一方で、自動レイアウトは万能ではありません。ノードサイズや接続密度、レイアウトアルゴリズムの相性によっては期待通りの配置にならない場合があります。そのため「読み方向」「ノード間隔」「階層の作り方」など、レイアウトオプションを明示して調整する設計が重要です。
位置計算結果をReact Flowに反映する手順
React FlowにELK等の計算結果を反映する流れはシンプルで、(1)React Flowのnodes/edgesをレイアウト用の入力形式に変換 →(2)レイアウト実行 →(3)返ってきた座標でnodesを更新という3段階です。ポイントは「ノードIDの対応」と「ノードサイズの扱い」で、ここが曖昧だと配置がズレたり、重なりが発生しやすくなります。
レイアウトに必要な情報を揃える
レイアウトエンジンは基本的に、ノードのIDとサイズ(幅・高さ)、エッジの接続(source/target)を必要とします。React Flow側のnode.idとedge.source/edge.targetをそのまま使えば、対応関係が崩れにくくなります。
- 必須:node.id / edge.source / edge.target
- 推奨:nodeの幅・高さ(固定値でも可。実測する場合はレンダリング後に取得)
- 任意:読み方向やノード間隔などのレイアウトオプション
ELK等で座標を計算する
ELKを使う場合、入力は「children(ノード)」と「edges(エッジ)」を持つグラフオブジェクトになり、出力として各ノードのx/yが返ります。レイアウトは非同期になることが多いため、React側ではレイアウト完了後にまとめて状態更新するのが安定します。
// 例:ELKでレイアウトしてReact Flowのnodesに座標を反映する(概念コード) import ELK from 'elkjs/lib/elk.bundled.js'; const elk = new ELK(); async function layoutWithElk(nodes, edges) { const graph = { id: 'root', layoutOptions: { // 例:左→右に流す(必要に応じて調整) 'elk.direction': 'RIGHT', // 例:間隔系(値はプロジェクトに合わせて調整) 'elk.spacing.nodeNode': '40', 'elk.layered.spacing.nodeNodeBetweenLayers': '60', }, children: nodes.map((n) => ({ id: n.id, width: n.width ?? 180, height: n.height ?? 60, })), edges: edges.map((e) => ({ id: e.id, sources: [e.source], targets: [e.target], })), }; const result = await elk.layout(graph); // ELKの結果をReact Flowのnode.positionに反映 const positioned = nodes.map((n) => { const r = result.children?.find((c) => c.id === n.id); if (!r) return n; return { ...n, position: { x: r.x ?? 0, y: r.y ?? 0 }, }; }); return positioned; }このとき、React Flowの「position」はノード左上を基準にするのが一般的です。レイアウト側の座標系も同様(左上基準)で返ることが多いですが、エンジンや設定によっては解釈が異なる場合があるため、最初に少数ノードで検証して基準を揃えてください。
React Flowの状態(nodes)を更新し、必要なら表示範囲を調整する
座標反映は、React Flowで管理しているnodes配列のpositionを書き換えて再レンダリングさせます。レイアウト直後は図が画面外に飛ぶことがあるため、ビューを合わせる処理(例:全体が収まるように調整)も併用すると体験が安定します。ただし、ここでは「座標を反映する」ことが主題のため、まずはnodes更新を確実に行うのが優先です。
- レイアウト結果を受け取ったら、一括でnodesを差し替える(ちらつき・中途半端な配置を避ける)
- node.idの不一致があると反映されないため、IDの一意性を保証する
- ノードサイズが実態とズレると詰まりやすいので、固定サイズ運用か実測→再レイアウトのどちらかに設計を寄せる
React Flow × ELKの自動レイアウトは、「毎回整った配置を作る」ための基盤になります。運用で効くのは、レイアウトを一度きりの処理にしないことです。データ更新時・ノード追加時など、どのタイミングで再計算するかを決め、ID・サイズ・オプションを固定化していくと、安定して“読めるフロー”を提供できます。
フレームワーク連携:Astroや他UI基盤で使うときの注意点

Astro環境でReact Flowを動かすための構成ポイント
Astroは基本的に「静的HTMLを生成し、必要な部分だけをクライアントで動かす」思想のため、キャンバス上でドラッグやズーム、接続などのインタラクションが中心となるreact flowは、どのコンポーネントをどのタイミングでクライアント側に“水和(hydrate)”させるかが実装の肝になります。Astro側の設計が曖昧だと「表示はされるが操作できない」「イベントが効かない」といったトラブルに直結します。
構成上まず押さえたいのは、react flowを動かす領域を“Reactアイランド”として分離し、Astroからはその島をクライアント実行する指定を行うことです。具体的には、React Flowを描画するReactコンポーネント(例:FlowCanvas.tsx)を用意し、Astroページ(.astro)側ではそのコンポーネントを client:load / client:visible / client:only="react" などで読み込みます。どのディレクティブを選ぶかは要件次第で、初期表示の速さを優先するなら遅延水和(client:visible 等)、確実な動作を優先するなら早めの水和(client:load)が選択肢になります。
次に重要なのが「描画領域のサイズ確保」です。react flowは親要素のサイズを元に表示領域を計算するため、Astro側のレイアウト(特にdisplayや高さ指定)が不十分だと、キャンバスが0px相当になって何も見えない/操作できない状態になります。Reactコンポーネント側に任せるだけでなく、Astro側のコンテナにも明確な高さを与えるのが安全です。
Astroのレイアウトコンテナに対して、
height: 100vhや固定高、あるいは親要素からの高さ継承が成立する設計にするReact Flowを載せる要素が
positionやoverflowの影響を受ける場合、ズーム・パン操作の体感が崩れないか確認する
また、Astroはサーバーサイドでレンダリング(SSR)されるケースがあるため、クライアントAPI(window、document)に依存するコードをモジュールトップレベルで実行しないこともポイントです。react flow自体はクライアント動作が前提のため、周辺実装で「初期化時にDOM参照する」「サイズ計測を即時実行する」などを行うと、SSR時に落ちたり挙動が不安定になったりします。クライアント水和後に実行するよう、Reactのライフサイクル(例:useEffect)に寄せるのが基本方針です。
最後にスタイル面です。react flowは見た目のためのCSSが必要になりますが、AstroではCSSのスコープや読み込み場所が分散しやすく、必要なスタイルが当たらず「ハンドルが見えない」「操作領域がズレる」などが起きがちです。React Flow用のCSSは、適用漏れがない位置(グローバルCSSや対象コンポーネントの読み込み箇所)に整理し、AstroのCSSスコープ(<style>のスコープ化)で意図せず効かなくならないように注意してください。
他フレームワーク/外部UIとの組み込み時の落とし穴
react flowをAstro以外のフレームワークや、外部UI(デザインシステム、UIコンポーネント群、既存のレイアウト基盤)に組み込むときは、「イベントの取り合い」「レイアウト計算のズレ」「描画層(z-index)問題」が典型的な落とし穴になります。見た目は出ているのに操作が不安定、というケースほど原因が複合的になりやすいため、事前に地雷ポイントを把握しておくと実装が安定します。
まず多いのが、親コンテナや周辺UIがマウス/タッチイベントを先に処理してしまう問題です。react flowはドラッグ、パン、ズームなどでポインターイベントを多用しますが、外部UI側で次のような指定があると操作が阻害されます。
親要素での
pointer-events設定により、キャンバスがクリック・ドラッグを受け取れないスクロールコンテナの
touch-actionや、モバイル向けのジェスチャー制御が競合してパン操作が途切れるモーダル、ドロワー、ツールチップ等の外部UIが「ドラッグ中のマウス移動」をグローバルに捕捉してしまう
この手の競合は「react flow側の設定」ではなく「周辺のUI基盤のイベント設計」に原因があることが多いため、React Flowを配置する領域の親子関係(どの要素がイベントを握っているか)をDOM構造で確認するのが有効です。
次に、レイアウトやサイズ計測のタイミングによる表示崩れです。外部UIと組み合わせると、アコーディオン展開、タブ切り替え、サイドバーの開閉などでコンテナサイズが動的に変化します。react flowは表示領域が変わると再計算が必要になる場面があり、何もしないと「キャンバスが一部しか描画されない」「ズーム/座標がずれる」といった違和感が出ます。特に「初期表示時は非表示(display:none)→後から表示」のパターンは要注意で、表示されたタイミングで正しいサイズを取れず不自然な初期状態になることがあります。
さらに、重なり順(z-index)とオーバーレイUIの問題も起きがちです。react flowのキャンバス上に外部UI(ポップオーバー、コンテキストメニュー、ツールバー)を重ねる場合、以下のような現象が出やすくなります。
メニューがキャンバスの背面に潜ってクリックできない(z-indexの不足)
逆にオーバーレイがキャンバス全面を覆い、ノード操作ができない(透明でもクリックを奪う)
transformが付いた親要素配下で位置計算がズレ、ポップオーバーが意図しない場所に出る
対策としては、React Flow領域を「イベントとスタッキングコンテキストの境界」として設計し、上に載せる外部UIは“クリックを奪う範囲”を最小化する、あるいは必要に応じてキャンバス外(レイアウト上の別レイヤー)に逃がす、といった方針が有効です。特にデザインシステム由来のコンポーネントは、内部でposition: fixedやポータル(Portal)を使うことも多いため、react flowの座標系・重なり順と衝突しない配置戦略を先に決めておくと手戻りが減ります。
まとめると、react flowを他のUI基盤に組み込む際は「クライアント実行の境界」「サイズ確保と再計算のタイミング」「イベント競合」「z-index/オーバーレイ」をセットで点検することが、安定動作への近道です。
トラブルシューティング:動かない・イベントが発火しない時の調査手順
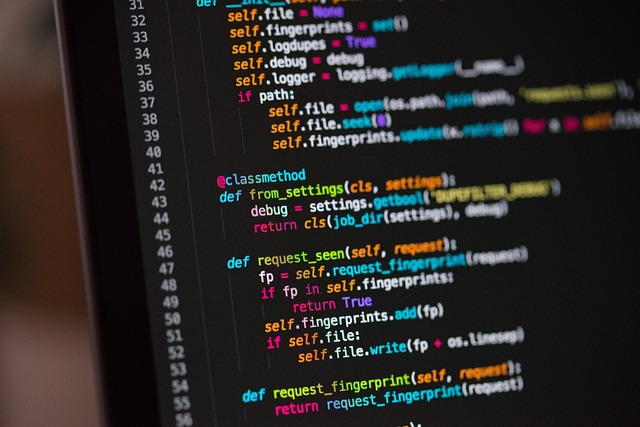
React Flowで「ドラッグできない」「エッジ接続できない」「イベントが発火しない」といった不具合が起きた場合、原因は大きく分けて(1)見た目やDOM(CSS/オーバーレイ)による入力阻害、(2)React Flow側の前提条件(providerや設定)、(3)自作コード(状態管理/ハンドラ)の不整合の3系統に集約されます。闇雲に修正するのではなく、症状を切り分けてから、ライブラリ挙動→自作コードの順に追うと短時間で特定できます。
よくある症状の切り分け(ドラッグ不可・接続不可など)
まずは「どの入力がどこで止まっているか」を確認します。React Flowはキャンバス上のポインター操作に強く依存するため、入力がそもそも届いていないケース(DOM/CSS)と、届いてはいるが状態更新が反映されていないケース(状態管理/props)が混ざりがちです。
ノードがドラッグできない:ノードの上でマウスダウンしても動かない場合、最初に疑うのは「別要素が上に被ってクリックを奪っている」「ノードのドラッグが意図せず無効化されている」です。開発者ツールで該当位置の要素を調べ、想定外のオーバーレイや透明レイヤーがないか確認します。
エッジ接続(ハンドルからのドラッグ)ができない:ハンドルが表示されているのに接続操作が始まらない場合、ハンドル周辺の
pointer-events設定、ハンドル自体のDOM構造、または接続イベントがキャンセルされている(接続ルールの実装やイベント内での早期return)可能性があります。クリック/ホバーなどのイベントが発火しない:React Flow上のノード内に独自のボタンや入力を置くと、イベントのバブリング・キャプチャ、またはキャンバス操作との競合で「意図した要素に届かない」ことがあります。まずは最小の要素(単純な
<div>)で同じ現象が起きるかを確認し、原因が構造にあるのか実装にあるのかを分離します。一部だけ反応する(ズームはできるがドラッグできない等):入力の種類ごとに反応が分かれる場合、CSSやDOMの問題ではなく、特定の操作だけを無効化する設定・状態(例:ドラッグ/接続関連のフラグ、イベントハンドラでの条件分岐)を疑うと効率的です。
ライブラリ側の挙動を追うデバッグの進め方
React Flowのトラブルは「ライブラリは正しく動いているが、周辺のUIや状態の持ち方が原因」ということが多いです。そこで、まずはReact Flowの外乱を減らし、ライブラリの期待通りに入力が届いているかを確認します。
最小再現に落とす:問題の画面から、影響しそうな要素(モーダル、ヘッダーの固定レイヤー、独自のラッパーdiv、カスタムCSS)を一つずつ外し、React Flow単体に近い状態にします。ここで現象が消えるなら「外側のDOM/CSS」が原因です。
開発者ツールでイベントを観測する:Chrome DevToolsのEvent Listenersや、要素のハイライトを使い、クリック位置でどの要素がヒットしているかを確認します。透明なレイヤーがクリックを奪っている場合、見た目では分からず、ここで初めて気づけます。
React Flowコンテナのサイズ/重なりを確認する:キャンバスが0サイズ、もしくは想定外の領域に縮んでいると、操作できているようで実際は別領域を触っていることがあります。レイアウト崩れ(親要素の高さ未設定など)があるときは、見た目とDOM上の当たり判定がズレます。
React Flowへの入力がブロックされていないかを見る:周辺コンポーネントで
pointer-events: noneや逆にpointer-events: autoのオーバーレイが設定されていないか、z-index競合がないかを点検します。特にツールチップ、選択用の矩形、ドラッグ用ガイドなど自作レイヤーがあると衝突しやすいです。
自作コードの確認ポイント(イベントハンドラ/状態管理)
React Flowが受け取った操作は、最終的に「nodes/edgesの更新」や「イベントコールバックの実行」として現れます。つまり、イベント自体は発火しているのにUIが変わらない場合、状態更新が正しく反映されていない可能性が高いです。以下は確認優先度の高いポイントです。
イベントハンドラ内で状態を更新できているか:ドラッグや接続の結果を反映する処理で、配列を破壊的に変更していないか、更新用関数の呼び出しが条件分岐でスキップされていないかを確認します。
クロージャによる古い状態参照:ハンドラが古い
nodes/edgesを参照していると、更新が戻されたように見えることがあります。特に複数操作が連続するUIでは、関数型更新(直前状態を引数で受ける形)を徹底するのが安全です。propsの上書き競合:別の
useEffectや外部ストア同期で、React Flowに渡すnodes/edgesが操作直後に上書きされると「ドラッグできたのに戻る」「接続が一瞬で消える」現象になります。操作と同期処理の責務分離が重要です。ノード内のUIがキャンバス操作を阻害していないか:ノードコンテンツ内のボタンや入力が、意図せずドラッグ開始を奪ったり、逆にドラッグを阻害したりします。ノード内の操作領域と、ドラッグしたい領域を明確に分ける設計が必要です。
マウスイベント実装時の注意点(mouseenter等)
React Flow上で独自のホバー表示やドラッグ開始判定を実装するとき、mouseenter/mouseleaveの扱いでハマりがちです。これらはバブリングしないため、親要素に付けても期待通りに拾えないことがあります。加えて、ノード内に子要素が多いと「入った/出た」が頻繁に起き、表示がチラついたり、状態が不整合になったりします。
親でまとめて拾いたい場合は、バブリングする
mouseover/mouseoutを検討し、必要ならrelatedTargetで「同一ノード内の移動」を除外します。ホバーでツールチップ等を出す場合、ツールチップ要素がマウスを奪うと、結果としてホバーが解除され続けることがあります。ツールチップ側の
pointer-eventsや配置レイヤーを見直し、意図した当たり判定にします。キャンバス側の操作(パン/ズーム/ドラッグ)と干渉するときは、「どの領域でどの操作を許可するか」を決め、ノード内部のUIではキャンバス操作を抑制する/逆にUI操作を抑制するなど、優先順位を明文化します。
アクション/状態更新の設計ミスを防ぐ
React Flowの「動かない」は、実装が複雑になるほど「更新経路が複数ある」ことが根本原因になります。たとえば、ドラッグの結果をローカルstateで更新しつつ、別途APIレスポンスで同じデータを反映していると、タイミング次第で巻き戻りが発生します。
単一の更新経路に寄せる:ユーザー操作で変わる
nodes/edgesは、どの層(コンポーネントstate / 外部ストア / サーバ同期)を正とするか決め、他は追従にします。更新の粒度を揃える:一部だけ差分更新、別の箇所では全量置き換え、という混在は不整合の温床です。操作系の更新は差分で統一する、同期系はバージョンを見て反映する、などルールを置きます。
状態の正規化:ノード位置のような頻繁に変わるデータと、メタ情報(ラベル等)を同じ更新で雑に扱うと、パフォーマンス低下や意図しない再レンダリングが起き、結果として「イベントが途切れる」ように見えることがあります。目的別にデータの責務を切るのが有効です。
典型パターンの修正方法と再発防止
最後に、React Flowで頻出する「動かない・発火しない」問題を、原因別にどう直し、どう再発防止するかを整理します。ポイントは「入力(DOM)→イベント(ハンドラ)→状態(nodes/edges)→描画」のどこで止まっているかを固定し、チェックリスト化することです。
| 症状 | よくある原因 | 修正の方向性 | 再発防止 |
|---|---|---|---|
| ドラッグできない | 透明レイヤーが被っている/当たり判定が別要素 | z-index/配置の見直し、不要なオーバーレイ撤去、該当要素のpointer-events調整 | UIレイヤー設計を文書化し、オーバーレイ追加時に確認項目を作る |
| 接続操作が開始しない | ハンドル周辺がクリックできていない/接続系イベントが条件で止まる | ハンドル周りのDOM/CSS確認、イベント条件分岐のログ追加 | 接続許可/禁止の条件をテスト可能な関数に分離する |
| イベントは出るがUIが変わらない | 状態更新が反映されない/直後に上書きされる | 更新経路を一本化、関数型更新に寄せる、同期処理のタイミング整理 | 「操作→状態→描画」の責務を分離し、上書き箇所をレビューで検出する |
| ホバーが不安定 | mouseenter/mouseleaveの性質、ツールチップがマウスを奪う | mouseover/outへの変更、relatedTargetで除外、ツールチップのpointer-events調整 | ノード内UIのイベント設計指針を決め、同様の実装を横展開する |
これらを踏まえ、問題が起きたら「DOMで入力が届いているか」「React Flowのイベントが実行されているか」「自作コードで状態が正しく更新され、上書きされていないか」を順番に確認してください。この手順をテンプレ化しておくと、React Flowのトラブルシューティングは大幅に短縮できます。
まとめ:React Flowでインタラクティブなダイアグラムを素早く作るコツ

本記事の要点整理
React Flowは、ノードとエッジを中心に「触って理解できる」ダイアグラムをReact上で効率よく組み立てられるライブラリです。素早く形にするためには、機能を盛り込みすぎず、まずは動く最小単位を作ってから段階的に拡張するのが近道になります。
特に押さえておきたいポイントは次のとおりです。
まずは「nodes/edgesを描画して操作できる状態」を最短で作る:React Flowでは表示・移動・接続といった基本体験を早期に確認できるため、最初にMVP(最小実用)を作るほど後戻りが減ります。
状態(nodes/edges)とイベントの責務を分けて設計する:どの操作で何が更新されるのかを整理し、イベントハンドラの役割を明確にしておくと、機能追加時の不具合や複雑化を抑えられます。
カスタマイズは「見た目」→「挙動」→「補助UI」の順で進める:先に視認性(スタイル)を整え、次に独自ノード等の挙動、最後にツールチップなどの補助UIを加えると、React Flowの拡張が破綻しにくくなります。
複雑なデータは前処理してから渡す:検索・フィルタ・集約などを含むグラフは、描画前の整形で扱いやすくしておくと、表示の安定性と保守性が上がります。
自動レイアウトは「配置計算」と「反映」を分離して考える:外部レイアウト(例:ELK)を使う場合も、計算結果をReact Flowへ反映する手順を明確化すると、UIのブレや更新タイミングの問題を減らせます。
動かない時は症状の切り分けとデバッグ導線が重要:ドラッグ不可・接続不可・イベント未発火などは原因が複数あり得るため、「ライブラリ挙動」と「自作コード(状態更新/イベント)」を分けて追うのが効率的です。
これらを意識すると、React Flowでの開発が「作りながら仕様が固まる」状況でも破綻しにくく、結果的にインタラクティブなダイアグラムを素早く届けられます。
次に読むべき公式ドキュメント/実装テーマ
React Flowをさらにスムーズに使いこなすには、公式ドキュメントを「必要になった機能から逆引き」で読むのが効率的です。特に、実装が詰まりやすいポイントは公式の前提や推奨パターンにまとまっていることが多いため、早めに当たっておくと手戻りを減らせます。
公式ドキュメント(React Flow)
次に取り組む実装テーマとしては、以下が学習効率と実務インパクトの両面でおすすめです。
カスタムノードの設計:自分のUI要件(入力フォーム、ステータス表示、ボタンなど)をノードに落とし込み、再利用可能な部品として整理する。
接続ルール(接続可否・制約)の実装:不正な接続を防ぐ、特定タイプ同士のみ接続可能にする、など業務要件に直結しやすい。
データの入出力(保存・復元)を前提にした構造:nodes/edgesを永続化し、再読み込みで同じ状態を復元できるようにして運用に耐える形へ近づける。
自動レイアウト連携:ノード数が増えた時の可読性を担保し、手動配置の負担を減らす。
トラブルシューティング手順のテンプレ化:イベント・状態更新・描画のどこで止まっているかを素早く特定できるようにし、開発速度を落とさない。
React Flowは「基本が動けば、拡張で差がつく」タイプのライブラリです。公式ドキュメントを軸に、必要なテーマから段階的に深掘りすることで、短期間でも実用的なダイアグラムへ到達できます。




