JavaScriptの非同期処理を扱うasync/awaitの基本から実践的な使い方まで解説。Promiseのコールバック地獄を解決し、同期処理のように読みやすいコードを書く方法、エラー処理、並列処理、Promise.all()との使い分けなど、実務で必要な知識を習得できます。基本構文からthenを使わない複数の非同期処理の実行方法まで、具体的なコード例で理解を深められます。
目次
async/awaitとは?基本概念の理解
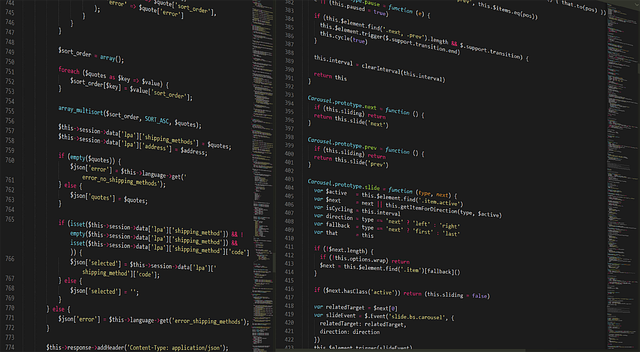
async/awaitは、JavaScriptにおける非同期処理をより直感的に記述できる構文機能です。従来のコールバック関数やPromiseを使った非同期処理と比較して、まるで同期処理のように読みやすいコードを書けるのが大きな特徴といえます。ES2017(ES8)で正式に導入されたこの機能は、現在では多くの開発現場で標準的に利用されており、JavaScriptプログラミングにおける非同期処理の扱いを大きく変革しました。
JavaScriptにおけるasync/awaitの役割
async/awaitは、非同期処理を同期処理のように記述できる構文糖衣(シンタックスシュガー)として機能します。asyncキーワードを関数の前に付けることで、その関数は自動的にPromiseを返す非同期関数となり、関数内でawaitキーワードを使用できるようになります。
具体的には、async/awaitは以下のような役割を果たします。
- コードの可読性向上:非同期処理を上から下へと順番に読めるコードとして記述できるため、処理の流れを理解しやすくなります
- エラーハンドリングの簡潔化:try-catch構文を使って同期処理と同じ方法でエラー処理を記述できます
- デバッグの容易性:スタックトレースが追いやすく、問題の特定が簡単になります
- メンテナンス性の向上:コードが直線的に記述されるため、修正や機能追加がしやすくなります
awaitキーワードは、Promiseの結果が解決されるまで関数の実行を一時停止し、結果が得られた時点で処理を再開します。この仕組みにより、非同期処理を扱う際の複雑さが大幅に軽減され、プログラマーは処理のロジックそのものに集中できるようになりました。
async/awaitが導入された背景と目的
async/awaitが導入された背景には、JavaScriptにおける非同期処理の複雑化という課題がありました。Webアプリケーションの高度化に伴い、APIからのデータ取得、データベースへのアクセス、ファイル操作など、非同期処理を扱う場面が急増していました。
従来の非同期処理の記述方法には、いくつかの問題点がありました。コールバック関数を使った実装では、処理が入れ子になる「コールバック地獄」と呼ばれる状態が発生し、コードの可読性が著しく低下していました。その後、Promiseが導入されて状況は改善されましたが、それでもthenメソッドのチェーンが続くと、コードの複雑さは残りました。
async/awaitの導入目的は以下の通りです。
- コードの直感性向上:非同期処理を同期処理のように記述することで、プログラムの流れを直感的に理解できるようにする
- 学習コストの削減:JavaScript初心者でも非同期処理を扱いやすくする
- エラー処理の統一:同期処理と同じtry-catch構文でエラーハンドリングができるようにする
- 開発効率の向上:コードの記述量を減らし、開発とメンテナンスの効率を高める
これらの目的により、async/awaitは非同期処理の「書きやすさ」と「読みやすさ」を同時に実現することを目指して設計されました。
非同期処理における位置づけ
JavaScriptの非同期処理の進化において、async/awaitは現時点での到達点といえる位置づけにあります。非同期処理の手法は、コールバック関数からPromise、そしてasync/awaitへと発展してきました。
非同期処理における各手法の位置づけを整理すると、以下のようになります。
| 手法 | 特徴 | 位置づけ |
|---|---|---|
| コールバック関数 | 最も基本的な非同期処理の実装方法 | 基礎技術として理解が必要 |
| Promise | 非同期処理をオブジェクトとして扱う | async/awaitの基盤技術 |
| async/await | Promiseを簡潔に記述するための構文 | 現代的な標準手法 |
重要なのは、async/awaitはPromiseを置き換えるものではなく、Promiseの上に構築された便利な記述方法であるという点です。async関数は内部的にPromiseを返しており、awaitキーワードもPromiseオブジェクトに対して動作します。つまり、async/awaitを効果的に使うには、Promiseの基本的な理解が不可欠です。
現在の開発現場では、新規プロジェクトにおいてはasync/awaitが第一選択となることが多く、コードレビューやスタイルガイドでも推奨されています。ただし、Promise.allやPromise.raceなど、Promiseのメソッドは依然として重要であり、async/awaitと組み合わせて使用されます。
async/awaitは単なる構文の糖衣ではなく、JavaScriptにおける非同期プログラミングのパラダイムを変えた画期的な機能として、現代のWebアプリケーション開発に欠かせない存在となっています。
“`html
非同期処理の基礎知識

JavaScriptでasync/awaitを理解するためには、まず非同期処理の基礎知識を押さえておく必要があります。非同期処理はモダンなWeb開発において欠かせない概念であり、その発展の歴史を知ることで、async/awaitがなぜ重要なのかが明確になります。ここでは、同期処理と非同期処理の違いから、コールバック関数、そしてPromiseまで、段階的に解説していきます。
同期処理と非同期処理の違い
JavaScriptにおける処理方式には、大きく分けて同期処理と非同期処理の2種類があります。これらの違いを理解することは、非同期処理を扱う上での基本中の基本となります。
同期処理は、コードが記述された順番に、上から下へと1つずつ順番に実行される処理方式です。1つの処理が完了するまで、次の処理は待機状態となり、前の処理が終わるまで実行されません。例えば、時間のかかる計算処理があった場合、その処理が完了するまでプログラム全体が停止してしまいます。
// 同期処理の例
console.log('処理1');
console.log('処理2');
console.log('処理3');
// 出力: 処理1 → 処理2 → 処理3(順番通り)一方、非同期処理は、処理の完了を待たずに次の処理を実行できる方式です。時間のかかる処理(API通信、ファイル読み込み、タイマー処理など)を実行する際に、その処理の完了を待たずに後続のコードを実行し、処理が完了したタイミングで結果を受け取ります。これにより、ユーザーインターフェースがフリーズすることなく、スムーズな操作性を保つことができます。
// 非同期処理の例
console.log('処理1');
setTimeout(() => {
console.log('処理2(2秒後)');
}, 2000);
console.log('処理3');
// 出力: 処理1 → 処理3 → 処理2(2秒後)非同期処理が必要となる主なケースには以下のようなものがあります。
- 外部APIからのデータ取得
- データベースへのクエリ実行
- ファイルの読み書き
- 画像などのリソースの読み込み
- タイマーや遅延実行
コールバック関数による非同期処理
非同期処理を実現する最も基本的な方法がコールバック関数です。JavaScriptの初期から使われてきた手法であり、非同期処理の歴史を理解する上で重要な概念となります。
コールバック関数の基本的な仕組み
コールバック関数とは、他の関数に引数として渡される関数のことで、特定の処理が完了した後に実行される関数を指します。非同期処理では、処理が完了したタイミングでコールバック関数を呼び出すことで、結果を受け取ったり次の処理を実行したりします。
// コールバック関数の基本例
function fetchData(callback) {
setTimeout(() => {
const data = { id: 1, name: 'ユーザー1' };
callback(data);
}, 1000);
}
fetchData((result) => {
console.log('データ取得完了:', result);
});
// 1秒後に「データ取得完了: { id: 1, name: 'ユーザー1' }」と表示この仕組みにより、時間のかかる処理の完了を待ってから、その結果を使った次の処理を実行することが可能になります。コールバック関数は、イベントハンドラーやsetTimeout、setIntervalなど、JavaScriptの様々な場面で使用されています。
コールバック地獄とその問題点
コールバック関数は便利な仕組みですが、非同期処理を連続して実行する必要がある場合に、コールバック地獄(Callback Hell)と呼ばれる問題が発生します。これは、コールバック関数の中でさらにコールバック関数を呼び出し、それが何重にもネストすることで、コードの可読性が著しく低下する状態を指します。
// コールバック地獄の例
fetchUser(userId, (user) => {
fetchUserPosts(user.id, (posts) => {
fetchPostComments(posts[0].id, (comments) => {
fetchCommentAuthor(comments[0].authorId, (author) => {
console.log('著者情報:', author);
// さらに深くネストしていく...
});
});
});
});コールバック地獄には以下のような問題点があります。
- 可読性の低下:コードが右方向にどんどんインデントされ、処理の流れが追いにくくなる
- 保守性の悪化:修正や機能追加が困難になり、バグが発生しやすくなる
- エラーハンドリングの複雑化:各コールバックごとにエラー処理を記述する必要があり、コードが冗長になる
- デバッグの困難さ:エラーが発生した際に、どこで問題が起きているのか特定しにくい
この問題を解決するために、Promiseという新しい仕組みが導入されました。
Promiseの基本と仕組み
Promiseは、ES2015(ES6)で正式に導入された、非同期処理をより扱いやすくするためのオブジェクトです。コールバック地獄の問題を解決し、非同期処理をより直感的に記述できるようになります。Promiseは「将来的に値が得られることを約束するオブジェクト」として機能します。
Promiseの3つの状態
Promiseオブジェクトは、常に以下の3つの状態のいずれかを持ちます。この状態管理の仕組みが、Promiseによる非同期処理制御の核心となっています。
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| Pending(保留) | 初期状態。非同期処理が実行中で、まだ完了も失敗もしていない状態 |
| Fulfilled(成功) | 非同期処理が正常に完了し、結果の値が利用可能な状態 |
| Rejected(失敗) | 非同期処理が失敗し、エラー理由が利用可能な状態 |
Promiseは一度FulfilledまたはRejected状態になると、その状態は変更されません。この特性により、非同期処理の結果が確定した後は、何度でも同じ結果を参照できるという信頼性が保証されます。
resolveとrejectの使い方
Promiseを作成する際には、Promiseコンストラクタに関数を渡します。この関数は、resolve(成功時に呼ぶ関数)とreject(失敗時に呼ぶ関数)の2つの引数を受け取ります。
// Promiseの基本的な作成方法
const myPromise = new Promise((resolve, reject) => {
// 非同期処理を実行
setTimeout(() => {
const success = true;
if (success) {
resolve('処理成功!'); // 成功時
} else {
reject('処理失敗...'); // 失敗時
}
}, 1000);
});resolve関数を呼び出すと、Promiseの状態がFulfilledに変わり、渡した値が成功結果として扱われます。一方、reject関数を呼び出すと、Promiseの状態がRejectedに変わり、渡した値がエラー理由として扱われます。
// 実践的なPromiseの例(データ取得)
function fetchUserData(userId) {
return new Promise((resolve, reject) => {
// API呼び出しを模擬
setTimeout(() => {
if (userId > 0) {
resolve({ id: userId, name: 'ユーザー' + userId });
} else {
reject(new Error('無効なユーザーIDです'));
}
}, 1000);
});
}thenとcatchによる処理の記述
Promiseの結果を処理するには、thenメソッドとcatchメソッドを使用します。これらのメソッドにより、成功時と失敗時の処理を明確に分離できます。
thenメソッドは、Promiseが成功(Fulfilled)した際に実行される処理を定義します。thenメソッドには、resolve関数に渡された値が引数として渡されます。
// thenを使った成功時の処理
fetchUserData(1)
.then((user) => {
console.log('ユーザー情報:', user);
// 出力: ユーザー情報: { id: 1, name: 'ユーザー1' }
});catchメソッドは、Promiseが失敗(Rejected)した際に実行される処理を定義します。catchメソッドには、reject関数に渡された値が引数として渡されます。
// catchを使ったエラー処理
fetchUserData(-1)
.then((user) => {
console.log('ユーザー情報:', user);
})
.catch((error) => {
console.error('エラーが発生しました:', error.message);
// 出力: エラーが発生しました: 無効なユーザーIDです
});また、thenメソッドは第2引数としてエラーハンドラーを受け取ることもできます。
// thenの第2引数でエラー処理
fetchUserData(1).then(
(user) => {
console.log('成功:', user);
},
(error) => {
console.error('失敗:', error);
}
);finallyメソッドを使用すると、成功・失敗に関わらず実行される処理を定義できます。
fetchUserData(1)
.then((user) => console.log('成功:', user))
.catch((error) => console.error('失敗:', error))
.finally(() => console.log('処理完了'));thenチェーンの活用方法
Promiseの最も強力な機能の1つが、thenチェーン(メソッドチェーン)です。thenメソッドは新しいPromiseを返すため、複数のthenを連結して、非同期処理を順次実行することができます。これにより、コールバック地獄の問題が解決され、コードの可読性が大幅に向上します。
// thenチェーンの基本例
fetchUserData(1)
.then((user) => {
console.log('ユーザー取得:', user);
return fetchUserPosts(user.id); // 次のPromiseを返す
})
.then((posts) => {
console.log('投稿取得:', posts);
return fetchPostComments(posts[0].id); // さらに次のPromiseを返す
})
.then((comments) => {
console.log('コメント取得:', comments);
})
.catch((error) => {
console.error('いずれかの処理でエラー:', error);
});thenチェーンでは、各thenメソッドで返された値が次のthenメソッドに渡されます。Promiseを返した場合は、そのPromiseが解決されるまで待機してから次のthenが実行されます。
// 値の変換を伴うthenチェーン
Promise.resolve(5)
.then((num) => {
return num * 2; // 10
})
.then((num) => {
return num + 3; // 13
})
.then((result) => {
console.log('最終結果:', result); // 13
});エラーハンドリングもthenチェーンの中で柔軟に行えます。catchメソッドは、それより前のどのthenメソッドでエラーが発生しても捕捉できます。
// チェーン内でのエラーハンドリング
fetchUserData(1)
.then((user) => {
if (!user.name) {
throw new Error('ユーザー名がありません');
}
return user;
})
.then((user) => {
console.log('処理継続:', user);
})
.catch((error) => {
console.error('エラー捕捉:', error.message);
});このように、Promiseはコールバック関数の問題を解決し、非同期処理をより直感的に記述できるようにしました。しかし、複雑な非同期処理では、thenチェーンも長くなり可読性が低下することがあります。この問題を最終的に解決するのが、async/awaitという構文です。
“`
“`html
async関数の使い方
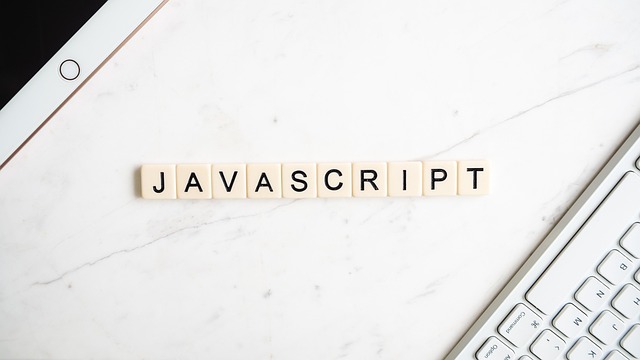
JavaScriptでasync/awaitを利用するには、まずasync関数を理解することが不可欠です。async関数は非同期処理を扱うための特別な関数で、内部でawait式を使用できるようになります。ここでは、async関数の基本的な使い方から、戻り値の処理、Promiseとの関係、エラーハンドリングまで、実践的な記述方法を詳しく解説します。
async関数の基本構文と記述方法
async関数は、関数宣言の前にasyncキーワードを付けることで定義します。このキーワードを付けるだけで、通常の関数が非同期関数に変わり、内部でawaitを使用できるようになります。
async関数の基本的な記述方法は以下の通りです:
// 関数宣言
async function myFunction() {
// 非同期処理
}
// 関数式
const myFunction = async function() {
// 非同期処理
};
// アロー関数
const myFunction = async () => {
// 非同期処理
};
// メソッド定義
const obj = {
async myMethod() {
// 非同期処理
}
};async関数は、どのような関数定義方法でも使用できます。関数宣言、関数式、アロー関数、オブジェクトのメソッドなど、あらゆる場面でasyncキーワードを付与することが可能です。コーディングスタイルやプロジェクトの規約に合わせて、適切な記述方法を選択してください。
実際の使用例を見てみましょう:
async function fetchUserData() {
const response = await fetch('https://api.example.com/user');
const data = await response.json();
return data;
}
// アロー関数での記述
const fetchUserData = async () => {
const response = await fetch('https://api.example.com/user');
const data = await response.json();
return data;
};このように、async関数内ではawait式を使って非同期処理を同期的な記述で表現できます。関数宣言の前にasyncを付けるだけというシンプルな構文が、async/awaitの大きな特徴です。
async関数内でのreturn処理
async関数の重要な特徴として、関数の戻り値は常にPromiseオブジェクトになるという点があります。これはasync関数内でどのような値を返しても、自動的にPromiseでラップされるということを意味します。
async関数内でのreturn処理には以下のような特徴があります:
- 通常の値をreturnすると、その値で解決されるPromiseが返される
- Promiseをreturnすると、そのPromiseがそのまま返される
- return文がない場合、undefinedで解決されるPromiseが返される
- エラーをthrowすると、そのエラーで拒否されるPromiseが返される
具体的なコード例で確認しましょう:
// 文字列を返すasync関数
async function getString() {
return 'Hello';
}
// 実行すると、Promiseが返される
getString().then(value => {
console.log(value); // 'Hello'
});
// 数値を返すasync関数
async function getNumber() {
return 42;
}
// Promise.resolve()と同等の動作
getNumber().then(value => {
console.log(value); // 42
});
// return文がない場合
async function noReturn() {
console.log('処理実行');
}
noReturn().then(value => {
console.log(value); // undefined
});この自動的なPromise化により、async関数の呼び出し側では、通常のPromiseと同様に.then()や.catch()を使って結果を処理できます。また、別のasync関数内からはawaitを使って結果を直接取得することも可能です:
async function processData() {
const result = await getString();
console.log(result); // 'Hello'
return result.toUpperCase();
}
processData().then(value => {
console.log(value); // 'HELLO'
});async関数内でPromiseを返す方法
async関数内で明示的にPromiseを返すことも可能です。この場合、返されたPromiseは追加でラップされることなく、そのPromiseの状態がasync関数の戻り値となります。
Promiseを返す主なパターンは以下の通りです:
// Promise.resolve()を返す
async function resolveValue() {
return Promise.resolve('成功');
}
// Promise.reject()を返す
async function rejectValue() {
return Promise.reject('失敗');
}
// 既存のPromiseを返す
async function fetchData() {
return fetch('https://api.example.com/data');
}
// 条件分岐でPromiseを返す
async function conditionalPromise(condition) {
if (condition) {
return Promise.resolve('条件を満たしました');
} else {
return Promise.reject('条件を満たしていません');
}
}async関数内でPromiseを返す場合と、awaitを使って結果を待つ場合の違いを理解することが重要です:
// Promiseをそのまま返す(awaitしない)
async function returnPromise() {
return fetch('https://api.example.com/data');
// fetchが返すPromiseがそのまま返される
}
// awaitで結果を待ってから返す
async function awaitAndReturn() {
const response = await fetch('https://api.example.com/data');
return response;
// fetchの結果を待ってからResponseオブジェクトを返す
}awaitを使わずにPromiseを返す場合、そのPromiseの解決を待たずに即座に関数が終了します。一方、awaitを使うとPromiseの解決を待ってから次の処理に進みます。パフォーマンスや処理の流れを考慮して、適切な方法を選択することが大切です。
複数のPromiseを組み合わせる例も見てみましょう:
async function getMultipleData() {
const promise1 = fetch('https://api.example.com/data1');
const promise2 = fetch('https://api.example.com/data2');
// Promise.allを使って複数のPromiseをまとめて返す
return Promise.all([promise1, promise2]);
}
// 使用例
getMultipleData().then(([response1, response2]) => {
console.log('両方のデータを取得しました');
});async関数内でのエラーハンドリング
async関数内でのエラーハンドリングは、従来の同期処理と同様にtry-catch構文を使用できます。これはasync/awaitの大きなメリットの一つで、非同期処理のエラーを直感的に扱えるようになります。
async関数内でエラーが発生した場合、またはthrow文が実行された場合、その関数は拒否されたPromiseを返します:
// エラーをthrowするasync関数
async function throwError() {
throw new Error('エラーが発生しました');
}
// 関数を呼び出すと、拒否されたPromiseが返される
throwError().catch(error => {
console.error(error.message); // 'エラーが発生しました'
});
// try-catchでエラーをキャッチする
async function handleError() {
try {
await throwError();
} catch (error) {
console.error('エラーをキャッチしました:', error.message);
}
}await式でエラーが発生した場合も、try-catchでキャッチできます:
async function fetchWithErrorHandling() {
try {
const response = await fetch('https://api.example.com/data');
if (!response.ok) {
throw new Error(`HTTPエラー: ${response.status}`);
}
const data = await response.json();
return data;
} catch (error) {
console.error('データ取得に失敗しました:', error.message);
// エラー時のデフォルト値を返す
return null;
}
}複数のawait式がある場合のエラーハンドリングのパターンも確認しましょう:
// 個別にエラーハンドリングする
async function individualErrorHandling() {
try {
const user = await fetchUser();
console.log('ユーザー取得成功');
} catch (error) {
console.error('ユーザー取得失敗:', error);
}
try {
const posts = await fetchPosts();
console.log('投稿取得成功');
} catch (error) {
console.error('投稿取得失敗:', error);
}
}
// まとめてエラーハンドリングする
async function combinedErrorHandling() {
try {
const user = await fetchUser();
const posts = await fetchPosts();
return { user, posts };
} catch (error) {
console.error('データ取得中にエラー:', error);
throw error; // エラーを再スローする
}
}エラーハンドリングにおける実践的なテクニックとして、以下のようなパターンがあります:
- エラーメッセージを分かりやすくカスタマイズする
- エラー時のフォールバック値を用意する
- エラーログを記録する
- 必要に応じてエラーを再スローする
async function robustFetchData(url) {
try {
const response = await fetch(url);
if (!response.ok) {
throw new Error(
`データ取得失敗: ${response.status} ${response.statusText}`
);
}
const data = await response.json();
return { success: true, data };
} catch (error) {
// エラーログの記録
console.error('fetchData error:', {
url,
error: error.message,
timestamp: new Date().toISOString()
});
// エラー情報を含むオブジェクトを返す
return {
success: false,
error: error.message,
data: null
};
}
}async関数内でエラーをキャッチしない場合、そのエラーは呼び出し元に伝播します。適切なエラーハンドリングを実装しないと、予期しないエラーでアプリケーションが停止する可能性があるため、注意が必要です。エラーハンドリングの実装は、堅牢なアプリケーション開発において非常に重要な要素となります。
“`
await式の使い方
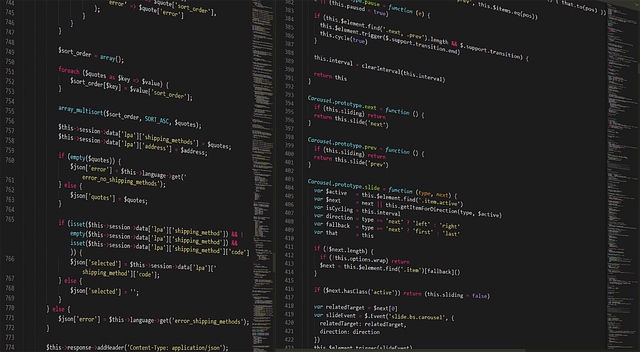
await式は、async関数内でPromiseの結果を待機し、非同期処理を同期的な記述スタイルで扱うための重要な構文です。このセクションでは、await式の具体的な使い方から、実践的なエラー処理の方法まで詳しく解説していきます。
await式の基本構文と記述ルール
await式は、Promiseが解決されるまで処理を一時停止し、解決された値を返す演算子です。基本的な構文は非常にシンプルで、awaitキーワードの後にPromiseを返す式を記述します。
async function fetchData() {
const result = await fetch('https://api.example.com/data');
const data = await result.json();
return data;
}await式を使用する際には、以下の重要なルールを守る必要があります。まず第一に、awaitはasync関数の内部でのみ使用可能という制約があります。通常の関数やグローバルスコープでawaitを使用するとSyntaxErrorが発生します。
await式の後には、Promise、または任意の値を置くことができます。Promiseではない値を指定した場合、その値はPromise.resolve()でラップされて即座に解決されます。
async function example() {
const value1 = await 42; // 即座に42が返される
const value2 = await Promise.resolve('hello'); // Promiseの解決を待つ
console.log(value1, value2); // 42 hello
}また、await式はPromiseがfulfilledになった際の値を直接返すため、thenメソッドを使った場合と比べてコードが大幅に簡潔になります。複数の非同期処理を連続して実行する場合も、await式を複数記述するだけで順次実行が可能です。
await式を使うメリットと利点
await式を活用することで、非同期処理のコードが劇的に読みやすく保守しやすくなります。ここでは、await式がもたらす具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
最大のメリットは、コードの可読性が大幅に向上する点です。Promise chaining(thenの連鎖)と比較すると、その差は一目瞭然です。
// Promiseチェーンの場合
function getUserData() {
return fetch('/api/user')
.then(response => response.json())
.then(user => fetch(`/api/posts/${user.id}`))
.then(response => response.json())
.then(posts => {
return { user, posts }; // userにアクセスできない問題
});
}
// await式を使った場合
async function getUserData() {
const response = await fetch('/api/user');
const user = await response.json();
const postsResponse = await fetch(`/api/posts/${user.id}`);
const posts = await postsResponse.json();
return { user, posts }; // 変数に自然にアクセス可能
}第二のメリットとして、変数のスコープ管理が容易になります。thenチェーンでは、前の処理の結果を後続の処理で使いたい場合にスコープの問題が発生しますが、await式を使えば通常の変数として扱えます。
第三に、デバッグが非常に簡単になります。await式を使ったコードは、通常の同期的なコードと同じようにステップ実行やブレークポイントの設定が直感的に行えます。
- コードが上から下へと読める自然な流れになる
- 変数の宣言と使用が近い位置に配置できる
- ネストが深くならず、フラットな構造を保てる
- try-catchを使った統一的なエラー処理が可能
- 開発者ツールでのデバッグがしやすい
さらに、await式は複雑な条件分岐やループ処理との相性も良好です。if文やfor文の中で自然にawaitを使用でき、同期処理と同じ感覚でロジックを組み立てられます。
await式でのエラー処理と例外の扱い方
await式を使った非同期処理では、Promiseがrejectedになった場合に例外がスローされます。この特性を活かして、try-catchブロックを使った直感的なエラー処理が可能になります。
基本的なエラー処理の構文は以下の通りです。
async function fetchUserData(userId) {
try {
const response = await fetch(`/api/users/${userId}`);
if (!response.ok) {
throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
}
const data = await response.json();
return data;
} catch (error) {
console.error('ユーザーデータの取得に失敗しました:', error);
throw error; // 必要に応じて再スロー
}
}try-catchブロックを使用することで、複数のawait式で発生する可能性のあるエラーを一箇所でまとめて処理できるのが大きな利点です。これはPromiseのcatchメソッドでは実現しにくい柔軟性を提供します。
async function processMultipleRequests() {
try {
const user = await fetchUser();
const posts = await fetchPosts(user.id);
const comments = await fetchComments(posts[0].id);
return { user, posts, comments };
} catch (error) {
// どの処理で失敗してもここでキャッチされる
if (error.name === 'NetworkError') {
console.error('ネットワークエラーが発生しました');
} else if (error.status === 404) {
console.error('リソースが見つかりませんでした');
} else {
console.error('予期しないエラー:', error);
}
return null;
}
}エラー処理をより細かく制御したい場合は、複数のtry-catchブロックを使い分けることも可能です。特定の処理のエラーだけを個別に処理し、他の処理は継続させたい場合に有効です。
async function robustDataFetch() {
let user = null;
let posts = [];
try {
user = await fetchUser();
} catch (error) {
console.error('ユーザー取得失敗:', error);
return null; // ユーザーが取得できない場合は処理を中断
}
try {
posts = await fetchPosts(user.id);
} catch (error) {
console.error('投稿取得失敗:', error);
// 投稿が取得できなくても処理を続行
}
return { user, posts };
}また、finally句を組み合わせることで、エラーの有無に関わらず実行したい処理(ローディング表示の終了など)を記述できます。
async function fetchWithLoading(url) {
showLoadingSpinner();
try {
const response = await fetch(url);
const data = await response.json();
return data;
} catch (error) {
console.error('データ取得エラー:', error);
showErrorMessage(error.message);
return null;
} finally {
hideLoadingSpinner(); // 成功・失敗に関わらず実行される
}
}注意点として、awaitを使わずにPromiseを返すだけの場合、そのPromiseのエラーはtry-catchでキャッチされません。必ずawaitを付けることで、例外としてキャッチ可能になります。
| 記述方法 | エラー捕捉 | 説明 |
|---|---|---|
await promise | ◯ catchで捕捉可能 | 推奨される方法 |
promise(awaitなし) | × catchで捕捉不可 | 未処理のPromise拒否が発生 |
promise.catch() | ◯ catchメソッドで処理 | Promiseチェーンの場合 |
適切なエラーハンドリングを実装することで、予期しない動作を防ぎ、ユーザーに対して適切なフィードバックを提供できる堅牢なアプリケーションを構築できます。
“`html
async/awaitとPromiseの関係性
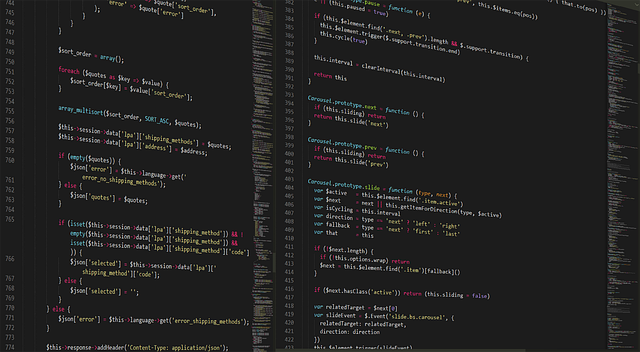
JavaScriptにおけるasync/awaitは、Promiseの上に構築された構文糖衣(シンタックスシュガー)です。つまり、async/awaitは内部的にPromiseを使用しており、両者は対立する概念ではなく相互補完的な関係にあります。async関数は必ずPromiseオブジェクトを返し、await式はPromiseの解決を待つという仕組みで動作しています。この関係性を正しく理解することで、より効果的に非同期処理を実装できるようになります。
async/awaitとPromiseの使い分け
async/awaitとPromiseは、どちらも非同期処理を扱うための手段ですが、それぞれに適した利用シーンがあります。適切な使い分けを行うことで、コードの可読性と保守性を向上させることができます。
async/awaitが適している場面は、複数の非同期処理を順次実行する場合や、処理の流れが複雑でネストが深くなりがちな場合です。同期的なコードのように見えるため、処理の流れを追いやすく、デバッグも容易になります。特に、前の処理結果を次の処理で使用するような連続した非同期処理において、その真価を発揮します。
// async/awaitが適した例
async function fetchUserData(userId) {
const user = await fetch(`/api/users/${userId}`);
const userData = await user.json();
const posts = await fetch(`/api/users/${userId}/posts`);
const postsData = await posts.json();
return { user: userData, posts: postsData };
}一方、Promiseが適している場面は、複数の非同期処理を並列実行したい場合や、動的にPromiseチェーンを構築する必要がある場合です。Promise.all()やPromise.race()などのユーティリティメソッドを使用する際には、Promiseの直接的な記述が有効です。
// Promiseが適した例
function fetchAllData() {
return Promise.all([
fetch('/api/users'),
fetch('/api/posts'),
fetch('/api/comments')
]).then(responses => Promise.all(responses.map(r => r.json())));
}実際のプロジェクトでは、両者を組み合わせて使用することが最も効果的です。async/await内でPromise.all()を使用するなど、状況に応じて柔軟に使い分けることが推奨されます。
async/awaitによる同期的な記述方法
async/awaitの最大の利点は、非同期処理を同期処理のように記述できることです。これにより、コードの可読性が大幅に向上し、処理の流れを直感的に理解できるようになります。
従来のPromiseチェーンでは、then()メソッドを連鎖させることで非同期処理を記述していましたが、これは処理が複雑になるにつれてネストが深くなり、コードが読みづらくなる傾向がありました。async/awaitを使用すると、非同期処理を上から下へと順序立てて記述できるため、まるで同期的なコードを書いているかのような自然な記述が可能になります。
// 同期的な記述スタイルの例
async function processOrder(orderId) {
// 注文情報の取得
const order = await fetchOrder(orderId);
// 在庫確認
const stockAvailable = await checkStock(order.productId);
// 決済処理
const payment = await processPayment(order.amount);
// 配送手配
const shipping = await arrangeShipping(order.address);
return {
orderId: orderId,
status: 'completed',
trackingNumber: shipping.trackingNumber
};
}このコードは上から下へと順番に実行され、各処理は前の処理が完了してから実行されます。変数の代入やエラーハンドリングも、同期的なコードと同じように記述できるため、プログラマーの認知的負担を大幅に軽減できます。
ただし、同期的な記述が可能だからといって、全ての処理を順次実行する必要はありません。依存関係のない処理については、並列実行を検討することでパフォーマンスを向上させることができます。
Promiseからasync/awaitへの書き換え方
既存のPromiseベースのコードをasync/awaitに書き換えることで、コードの可読性と保守性を向上させることができます。基本的な変換パターンを理解することで、スムーズな移行が可能になります。
最も基本的な変換パターンは、then()メソッドをawait式に置き換えることです。関数定義にasyncキーワードを追加し、Promiseを返す処理の前にawaitを記述します。
// Promiseを使った記述
function getUserInfo(userId) {
return fetch(`/api/users/${userId}`)
.then(response => response.json())
.then(user => {
return fetch(`/api/users/${userId}/profile`);
})
.then(response => response.json())
.then(profile => {
return { user, profile };
});
}
// async/awaitに書き換え
async function getUserInfo(userId) {
const response = await fetch(`/api/users/${userId}`);
const user = await response.json();
const profileResponse = await fetch(`/api/users/${userId}/profile`);
const profile = await profileResponse.json();
return { user, profile };
}エラーハンドリングについては、catch()メソッドをtry-catch構文に置き換えることで対応できます。この変換により、エラー処理も同期的なコードと同様の記述が可能になります。
// Promiseのcatch()を使った記述
function fetchData(url) {
return fetch(url)
.then(response => response.json())
.then(data => processData(data))
.catch(error => {
console.error('エラーが発生しました:', error);
throw error;
});
}
// try-catchに書き換え
async function fetchData(url) {
try {
const response = await fetch(url);
const data = await response.json();
return processData(data);
} catch (error) {
console.error('エラーが発生しました:', error);
throw error;
}
}Promise.all()を使用した並列処理も、async/await内で使用できます。await Promise.all()という形で記述することで、複数の非同期処理を並列実行しつつ、同期的な記述スタイルを維持できます。
// Promiseの並列処理
function fetchAllResources() {
return Promise.all([
fetch('/api/users'),
fetch('/api/posts'),
fetch('/api/comments')
]).then(responses => {
return Promise.all(responses.map(r => r.json()));
});
}
// async/awaitで書き換え
async function fetchAllResources() {
const responses = await Promise.all([
fetch('/api/users'),
fetch('/api/posts'),
fetch('/api/comments')
]);
const data = await Promise.all(responses.map(r => r.json()));
return data;
}書き換えの際には、不要なawaitを追加しないよう注意が必要です。関数の最後でPromiseを返すだけの場合は、awaitを省略することでパフォーマンスを向上させることができます。
“`
“`html
async/awaitの実践的な使い方
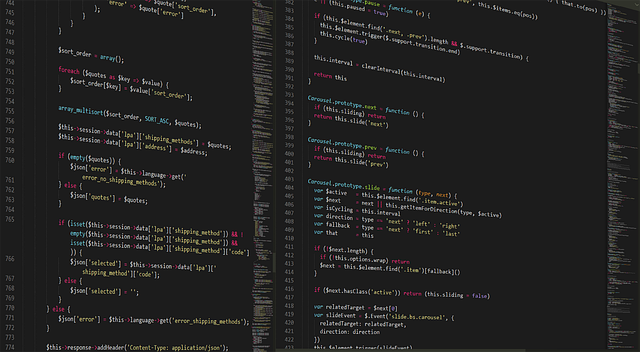
async/awaitの基本文法を理解したら、実際の開発現場で活用できる実践的なパターンを習得することが重要です。このセクションでは、複数の非同期処理の順次実行やAPI通信など、実務でよく使われるasync/awaitの活用方法について、具体的なコード例を交えて解説していきます。
複数の非同期処理を順次実行する方法
実際の開発では、複数の非同期処理を特定の順序で実行したい場面が頻繁に発生します。async/awaitを使えば、複雑な非同期処理を同期処理のように直感的に記述できます。
例えば、ユーザー情報を取得してから、そのユーザーの購入履歴を取得し、さらに関連商品を取得するような段階的な処理を実装する場合、以下のように記述します。
async function fetchUserData(userId) {
// ユーザー情報を取得
const user = await getUserInfo(userId);
console.log('ユーザー情報取得:', user.name);
// 取得したユーザーIDで購入履歴を取得
const orders = await getOrderHistory(user.id);
console.log('購入履歴件数:', orders.length);
// 購入履歴から関連商品を取得
const recommendations = await getRecommendations(orders);
console.log('おすすめ商品数:', recommendations.length);
return {
user,
orders,
recommendations
};
}このように、await式を使うことで各処理が完了するまで待機し、前の処理結果を次の処理で利用できます。処理の流れが上から下へと読めるため、コードの可読性が大幅に向上します。
thenを使わない非同期処理の連続実行
従来のPromiseチェーン(thenメソッドの連続使用)と比較すると、async/awaitの利点がより明確になります。thenを使った記述方法とasync/awaitを使った記述方法を比較してみましょう。
まず、thenチェーンを使った従来の記述方法は以下のようになります。
// thenチェーンでの記述
function processDataWithThen(userId) {
return fetchUser(userId)
.then(user => {
console.log('取得ユーザー:', user.name);
return fetchPosts(user.id);
})
.then(posts => {
console.log('投稿数:', posts.length);
return fetchComments(posts[0].id);
})
.then(comments => {
console.log('コメント数:', comments.length);
return comments;
})
.catch(error => {
console.error('エラー発生:', error);
throw error;
});
}同じ処理をasync/awaitで書き換えると、以下のようにネストが浅く、見通しの良いコードになります。
// async/awaitでの記述
async function processDataWithAsync(userId) {
try {
const user = await fetchUser(userId);
console.log('取得ユーザー:', user.name);
const posts = await fetchPosts(user.id);
console.log('投稿数:', posts.length);
const comments = await fetchComments(posts[0].id);
console.log('コメント数:', comments.length);
return comments;
} catch (error) {
console.error('エラー発生:', error);
throw error;
}
}async/await版では、変数の扱いが容易で、中間結果を自由に参照できるため、複雑なロジックでも管理しやすくなります。また、try-catchによるエラーハンドリングも直感的です。
データ取得処理での具体的な活用例
実際のWeb開発で最も頻繁に使用される場面として、APIからのデータ取得があります。ここでは、Fetch APIとasync/awaitを組み合わせた実践的なコード例を紹介します。
GETリクエストでのデータ取得
GETリクエストは、サーバーからデータを取得する際の基本的なHTTPメソッドです。async/awaitを使うことで、Fetch APIによるGETリクエストを非常にシンプルに記述できます。
async function fetchArticles() {
try {
// APIエンドポイントへGETリクエスト
const response = await fetch('https://api.example.com/articles');
// レスポンスステータスの確認
if (!response.ok) {
throw new Error(`HTTPエラー: ${response.status}`);
}
// JSONデータへの変換
const articles = await response.json();
console.log('取得記事数:', articles.length);
return articles;
} catch (error) {
console.error('データ取得エラー:', error.message);
throw error;
}
}より実践的な例として、クエリパラメータを含むGETリクエストを実装してみます。
async function searchProducts(keyword, page = 1, limit = 20) {
try {
// URLSearchParamsでクエリパラメータを構築
const params = new URLSearchParams({
q: keyword,
page: page,
limit: limit
});
const url = `https://api.example.com/products?${params}`;
const response = await fetch(url);
if (!response.ok) {
throw new Error(`検索失敗: ${response.status}`);
}
const data = await response.json();
return {
products: data.items,
totalCount: data.total,
currentPage: page
};
} catch (error) {
console.error('商品検索エラー:', error.message);
return { products: [], totalCount: 0, currentPage: 1 };
}
}この実装では、エラーが発生しても空の結果を返すことでアプリケーションが停止しないようにしています。実務では、このようなフォールバック処理が重要です。
POSTリクエストでのデータ送信
POSTリクエストは、サーバーへデータを送信する際に使用します。フォームの送信やデータの作成・更新など、様々な場面で活用されます。async/awaitを使ったPOSTリクエストの実装例を見ていきましょう。
async function createUser(userData) {
try {
const response = await fetch('https://api.example.com/users', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
},
body: JSON.stringify(userData)
});
if (!response.ok) {
throw new Error(`ユーザー作成失敗: ${response.status}`);
}
const createdUser = await response.json();
console.log('作成成功:', createdUser.id);
return createdUser;
} catch (error) {
console.error('ユーザー作成エラー:', error.message);
throw error;
}
}実際の利用例として、フォームデータの送信処理を実装してみます。
async function submitContactForm(formData) {
try {
// バリデーション
if (!formData.email || !formData.message) {
throw new Error('必須項目が入力されていません');
}
// API送信
const response = await fetch('https://api.example.com/contact', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'Accept': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
email: formData.email,
name: formData.name,
message: formData.message,
timestamp: new Date().toISOString()
})
});
if (!response.ok) {
const errorData = await response.json();
throw new Error(errorData.message || '送信に失敗しました');
}
const result = await response.json();
return {
success: true,
messageId: result.id,
message: '送信が完了しました'
};
} catch (error) {
console.error('フォーム送信エラー:', error.message);
return {
success: false,
message: error.message
};
}
}
// 使用例
async function handleFormSubmit(event) {
event.preventDefault();
const formData = {
email: document.getElementById('email').value,
name: document.getElementById('name').value,
message: document.getElementById('message').value
};
const result = await submitContactForm(formData);
if (result.success) {
alert(result.message);
} else {
alert('エラー: ' + result.message);
}
}POSTリクエストでは、認証トークンの設定やCORSの考慮など、セキュリティ面での注意が必要です。本番環境では、適切なエラーハンドリングとセキュリティ対策を実装することを忘れないでください。
また、複数のPOSTリクエストを連続して送信する場合も、async/awaitを使えば順序を制御しやすくなります。
async function bulkCreateItems(items) {
const results = [];
for (const item of items) {
try {
const result = await createItem(item);
results.push({ success: true, data: result });
} catch (error) {
results.push({ success: false, error: error.message });
}
}
return results;
}このように、async/awaitを活用することで、データ取得やデータ送信といった実践的な非同期処理を、可読性高く確実に実装できます。
“`
async/awaitにおける並列処理
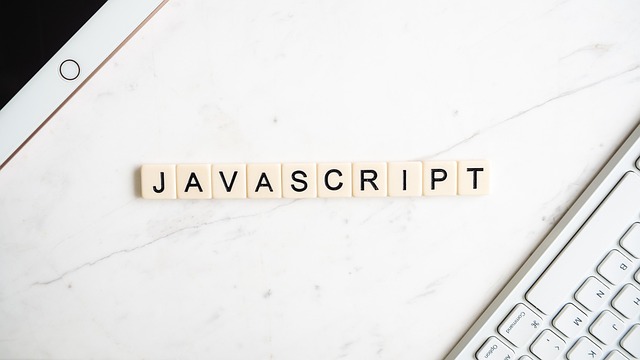
JavaScriptのasync/awaitを使った非同期処理では、複数の処理を同時に実行する並列処理が重要な役割を果たします。順次処理では各処理を待ってから次の処理に進むため、複数の独立した非同期処理がある場合、全体の実行時間が長くなってしまいます。並列処理を適切に活用することで、パフォーマンスを大幅に向上させることが可能です。本セクションでは、async/awaitにおける並列処理の実装方法と、効率的な処理の組み立て方について解説します。
Promise.allを使った並列処理の実装
複数の非同期処理を並列に実行する最も一般的な方法は、Promise.allを使用することです。Promise.allは複数のPromiseを配列で受け取り、すべてのPromiseが完了するまで待機してから結果を配列で返します。この方法により、各処理が独立して同時に実行されるため、処理時間を大幅に短縮できます。
async function fetchMultipleData() {
const promise1 = fetch('https://api.example.com/data1');
const promise2 = fetch('https://api.example.com/data2');
const promise3 = fetch('https://api.example.com/data3');
// 3つのリクエストを並列に実行
const [result1, result2, result3] = await Promise.all([
promise1,
promise2,
promise3
]);
const data1 = await result1.json();
const data2 = await result2.json();
const data3 = await result3.json();
return { data1, data2, data3 };
}上記のコードでは、3つのfetchリクエストを同時に開始し、Promise.allですべての応答を待ちます。順次処理で実装した場合と比較すると、各リクエストに1秒かかる場合、順次処理では3秒かかるところを、並列処理では約1秒で完了できます。
Promise.allには重要な特性があります。それは、渡されたPromiseのいずれか1つでもrejectされると、全体がrejectされるという点です。この動作により、一部の処理が失敗した場合に全体をエラーとして扱うことができます。
async function fetchDataWithErrorHandling() {
try {
const results = await Promise.all([
fetch('https://api.example.com/data1'),
fetch('https://api.example.com/data2'),
fetch('https://api.example.com/data3')
]);
return results;
} catch (error) {
console.error('いずれかのリクエストが失敗しました:', error);
throw error;
}
}一部の処理が失敗しても他の処理を続行したい場合は、Promise.allSettledを使用します。Promise.allSettledはすべてのPromiseが完了するまで待機し、成功・失敗に関わらず全ての結果を返します。
async function fetchDataAllSettled() {
const results = await Promise.allSettled([
fetch('https://api.example.com/data1'),
fetch('https://api.example.com/data2'),
fetch('https://api.example.com/data3')
]);
results.forEach((result, index) => {
if (result.status === 'fulfilled') {
console.log(`リクエスト${index + 1}成功:`, result.value);
} else {
console.log(`リクエスト${index + 1}失敗:`, result.reason);
}
});
return results;
}複数の非同期処理をまとめて実行する方法
実務では、データベースへの複数のクエリ、複数のAPIへのリクエスト、ファイルの読み込みなど、様々な非同期処理をまとめて実行するケースが頻繁に発生します。これらを効率的に処理するための方法を理解することが重要です。
動的な数の非同期処理を並列実行する場合、配列のmapメソッドとPromise.allを組み合わせる方法が効果的です。
async function fetchUserData(userIds) {
// ユーザーIDの配列から各ユーザーのデータを並列取得
const userPromises = userIds.map(userId =>
fetch(`https://api.example.com/users/${userId}`)
.then(response => response.json())
);
const users = await Promise.all(userPromises);
return users;
}
// 使用例
const userIds = [1, 2, 3, 4, 5];
const usersData = await fetchUserData(userIds);より複雑な処理では、関数を配列にまとめてから実行することもできます。
async function executeMultipleTasks() {
const tasks = [
async () => {
const data = await fetch('https://api.example.com/data1');
return data.json();
},
async () => {
const data = await fetch('https://api.example.com/data2');
return data.json();
},
async () => {
// データベース操作などの別の非同期処理
return performDatabaseQuery();
}
];
// すべてのタスクを並列実行
const results = await Promise.all(tasks.map(task => task()));
return results;
}Promise.raceを使用すると、複数のPromiseのうち最初に完了したものの結果を取得できます。タイムアウト処理の実装や、複数のデータソースから最も早く応答したものを使用する場合に便利です。
async function fetchWithTimeout(url, timeout = 5000) {
const fetchPromise = fetch(url);
const timeoutPromise = new Promise((_, reject) =>
setTimeout(() => reject(new Error('タイムアウトしました')), timeout)
);
try {
const response = await Promise.race([fetchPromise, timeoutPromise]);
return await response.json();
} catch (error) {
console.error('取得エラー:', error);
throw error;
}
}並列処理と順次処理の使い分け
async/awaitを使った非同期処理では、並列処理と順次処理のどちらを選択するかが、アプリケーションのパフォーマンスと正確性に大きく影響します。適切な使い分けを理解することで、効率的で保守性の高いコードを書くことができます。
並列処理が適している場合は、以下のような状況です。
- 複数の処理が互いに独立しており、依存関係がない場合
- 複数のAPIから同時にデータを取得する場合
- 複数のファイルを同時に読み込む・書き込む場合
- 実行時間を短縮したい場合
// 並列処理の例:各処理が独立している
async function loadDashboardData() {
// これらの処理は互いに依存していないため並列実行が効率的
const [userInfo, statistics, notifications] = await Promise.all([
fetchUserInfo(),
fetchStatistics(),
fetchNotifications()
]);
return { userInfo, statistics, notifications };
}順次処理が適している場合は、次のような状況です。
- 前の処理の結果を次の処理で使用する必要がある場合
- 処理の順序が重要な場合
- 一度に実行すると負荷が高すぎる場合
- トランザクション処理など、実行順序が保証される必要がある場合
// 順次処理の例:前の結果を次の処理で使用
async function processOrderSequentially(orderId) {
// 注文情報を取得
const order = await fetchOrder(orderId);
// 注文情報を基に在庫を確認(orderの結果が必要)
const inventory = await checkInventory(order.productId);
// 在庫確認後に支払い処理(inventoryの結果が必要)
const payment = await processPayment(order, inventory);
return payment;
}実際のアプリケーションでは、並列処理と順次処理を組み合わせることも多くあります。
async function complexProcessing() {
// 最初に必要な基本データを取得(順次)
const config = await fetchConfiguration();
// configを使って複数の処理を並列実行
const [userData, productData, settingsData] = await Promise.all([
fetchUserData(config.userId),
fetchProductData(config.productIds),
fetchSettings(config.settingsId)
]);
// 取得したデータを使って最終処理(順次)
const result = await finalizeProcessing(userData, productData, settingsData);
return result;
}並列処理の数が多すぎる場合、サーバーへの負荷が高くなりすぎる可能性があります。そのような場合は、バッチ処理を実装して処理を分割することが推奨されます。
async function processBatch(items, batchSize = 5) {
const results = [];
// itemsを指定サイズのバッチに分割して順次処理
for (let i = 0; i items.length; i += batchSize) {
const batch = items.slice(i, i + batchSize);
// 各バッチ内では並列処理
const batchResults = await Promise.all(
batch.map(item => processItem(item))
);
results.push(...batchResults);
}
return results;
}以下の表は、並列処理と順次処理の使い分けの判断基準をまとめたものです。
| 判断基準 | 並列処理 | 順次処理 |
|---|---|---|
| 処理の依存関係 | 独立している | 前の結果が必要 |
| 実行速度 | 高速(同時実行) | 低速(順番に実行) |
| サーバー負荷 | 高い(同時接続数増加) | 低い(順番に接続) |
| エラーハンドリング | 複雑になりやすい | シンプル |
| 適用場面 | 複数API取得、複数ファイル操作 | トランザクション、依存処理 |
最適な選択をするには、処理の性質、パフォーマンス要件、システムの制約を総合的に考慮する必要があります。処理が独立していて速度が重要な場合は並列処理を、処理に依存関係がある場合や順序が重要な場合は順次処理を選択することが基本的な指針となります。
ループ処理とasync/await
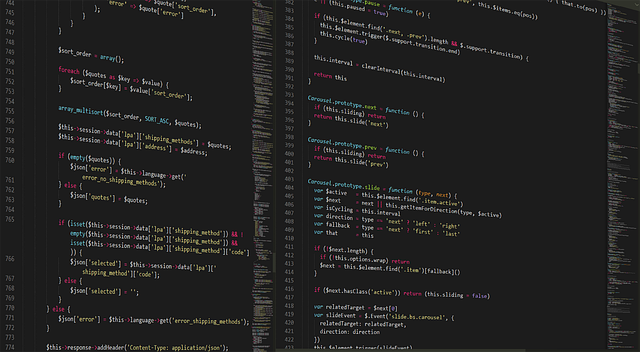
JavaScriptで配列やデータの集合に対して非同期処理を実行する場合、ループ処理とasync/awaitを組み合わせる必要があります。しかし、この組み合わせは予期しない動作を引き起こす可能性があるため、適切な使い方を理解しておくことが重要です。ここでは、ループ内でawaitを使用する際の具体的な注意点と、配列操作における非同期処理の扱い方について解説します。
ループ内でawaitを使用する際の注意点
ループ処理の中でawaitを使用する場合、使用するループの種類によって動作が大きく異なります。for文やfor…of文では期待通りの順次実行が行われますが、forEachメソッドでは非同期処理が正しく待機されません。これはforEachの内部実装がコールバック関数を同期的に呼び出すためです。
以下は、for…of文を使用した正しい実装例です。
async function processItems(items) {
for (const item of items) {
await fetchData(item);
console.log(`処理完了: ${item}`);
}
console.log('全ての処理が完了しました');
}
const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
processItems(items);この例では、各itemに対してfetchData関数が順番に実行され、一つの処理が完了してから次の処理に進みます。
一方、forEachメソッド内でawaitを使用すると、全ての非同期処理が並列に開始されてしまいます。以下は避けるべきアンチパターンです。
// 推奨されない書き方
async function processItemsWrong(items) {
items.forEach(async (item) => {
await fetchData(item);
console.log(`処理完了: ${item}`);
});
console.log('この行は非同期処理の完了を待たずに実行される');
}従来のfor文を使用した場合も、for…of文と同様に順次実行が可能です。
async function processWithForLoop(items) {
for (let i = 0; i items.length; i++) {
await fetchData(items[i]);
console.log(`処理完了: ${items[i]}`);
}
}while文やdo…while文でも同様に、ループ内でawaitを使用することで順次実行が実現できます。ただし、無限ループに陥らないよう、適切な終了条件を設定することが重要です。
配列操作における非同期処理の扱い方
配列に対して非同期処理を実行する場合、map、filter、reduceなどの配列メソッドとasync/awaitを組み合わせる方法を理解する必要があります。これらのメソッドは元々同期的な処理を前提としているため、非同期処理を扱う際には工夫が必要です。
mapメソッドで非同期処理を実行する場合、Promiseの配列を生成し、Promise.allで全ての処理を待機するパターンが一般的です。
async function fetchAllData(urls) {
const promises = urls.map(async (url) => {
const response = await fetch(url);
return response.json();
});
const results = await Promise.all(promises);
return results;
}
// 使用例
const urls = [
'https://api.example.com/data1',
'https://api.example.com/data2',
'https://api.example.com/data3'
];
fetchAllData(urls).then(data => {
console.log('取得したデータ:', data);
});この方法では、全てのリクエストが並列に実行されるため、パフォーマンスが向上します。ただし、処理の順序を保証したい場合や、一つずつ確実に処理したい場合は、前述のfor…of文を使用する方が適切です。
filterメソッドで非同期処理を行う場合も、同様のアプローチが必要です。
async function filterAsync(array, asyncPredicate) {
const results = await Promise.all(
array.map(async (item) => {
const shouldInclude = await asyncPredicate(item);
return { item, shouldInclude };
})
);
return results
.filter(result => result.shouldInclude)
.map(result => result.item);
}
// 使用例
async function isValid(item) {
// 何らかの非同期チェック
const response = await fetch(`https://api.example.com/validate/${item}`);
return response.ok;
}
const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
filterAsync(items, isValid).then(validItems => {
console.log('有効なアイテム:', validItems);
});reduceメソッドで非同期処理を扱う場合は、アキュムレータ自体をPromiseとして扱う必要があります。
async function reduceAsync(array, asyncReducer, initialValue) {
let accumulator = initialValue;
for (const item of array) {
accumulator = await asyncReducer(accumulator, item);
}
return accumulator;
}
// 使用例
async function fetchAndSum(total, url) {
const response = await fetch(url);
const data = await response.json();
return total + data.value;
}
const urls = [
'https://api.example.com/value1',
'https://api.example.com/value2'
];
reduceAsync(urls, fetchAndSum, 0).then(sum => {
console.log('合計値:', sum);
});配列の一部のみを非同期処理したい場合や、エラーハンドリングを個別に行いたい場合は、for…of文を使用した明示的なループ処理の方が制御しやすくなります。
async function processWithErrorHandling(items) {
const results = [];
const errors = [];
for (const item of items) {
try {
const result = await fetchData(item);
results.push({ item, result, status: 'success' });
} catch (error) {
errors.push({ item, error, status: 'failed' });
}
}
return { results, errors };
}パフォーマンスと処理の確実性のバランスを考慮して、並列処理(Promise.all)と順次処理(for…of)を使い分けることが、効率的な非同期処理の実装につながります。
async/awaitのエラーハンドリング
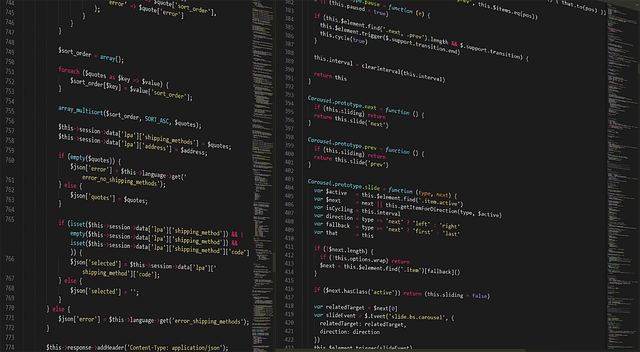
async/awaitを使った非同期処理では、エラーハンドリングが非常に重要です。非同期処理中に発生するエラーを適切に捕捉し処理しなければ、アプリケーションの予期しない動作やクラッシュを引き起こす可能性があります。このセクションでは、async/awaitにおけるエラー処理の基本から実践的なテクニックまでを詳しく解説します。
try-catchによるエラー処理の基本
async/awaitでは、従来の同期処理と同様にtry-catchブロックを使ってエラーを捕捉できます。これはPromiseのcatchメソッドよりも直感的で読みやすいコードを実現できる大きなメリットです。
基本的な構文は以下のようになります。
async function fetchUserData() {
try {
const response = await fetch('https://api.example.com/user');
const data = await response.json();
return data;
} catch (error) {
console.error('エラーが発生しました:', error);
}
}この例では、fetchリクエストやJSONのパース処理で発生する可能性のあるエラーをtry-catchで捕捉しています。awaitキーワードを付けた処理でエラーが発生すると、即座にcatchブロックに制御が移ります。
複数のawait式がある場合でも、一つのtry-catchブロックで全体をカバーできます。
async function processMultipleRequests() {
try {
const user = await fetchUser();
const posts = await fetchPosts(user.id);
const comments = await fetchComments(posts[0].id);
return { user, posts, comments };
} catch (error) {
console.error('データ取得中にエラーが発生:', error);
throw error; // 必要に応じて再スロー
}
}ただし、この方法ではどの処理でエラーが発生したのか特定しにくいという欠点があります。エラーの発生箇所を特定する必要がある場合は、複数のtry-catchブロックに分けることも検討しましょう。
async function processWithDetailedErrorHandling() {
let user, posts;
try {
user = await fetchUser();
} catch (error) {
console.error('ユーザー情報の取得に失敗:', error);
return null;
}
try {
posts = await fetchPosts(user.id);
} catch (error) {
console.error('投稿情報の取得に失敗:', error);
// ユーザー情報だけでも返す
return { user, posts: [] };
}
return { user, posts };
}例外発生時の適切な対処方法
エラーを捕捉した後、どのように対処するかは状況によって異なります。適切なエラーハンドリングを行うことで、ユーザー体験を向上させ、デバッグも容易になります。
エラーのログ記録と通知
エラーが発生した際は、まず適切にログを記録することが重要です。本番環境では、エラー監視サービスに通知を送ることも検討しましょう。
async function fetchDataWithLogging() {
try {
const data = await fetch('https://api.example.com/data');
return await data.json();
} catch (error) {
// エラーの詳細情報をログに記録
console.error('API呼び出しエラー:', {
message: error.message,
stack: error.stack,
timestamp: new Date().toISOString()
});
// エラー監視サービスへの送信(例)
// errorMonitor.report(error);
throw error;
}
}フォールバック値の返却
エラーが発生した場合にデフォルト値やキャッシュされたデータを返すことで、アプリケーションの動作を継続させることができます。
async function getUserProfile(userId) {
try {
const response = await fetch(`/api/users/${userId}`);
return await response.json();
} catch (error) {
console.warn('プロフィール取得失敗、デフォルト値を返します');
// フォールバック値を返す
return {
id: userId,
name: 'Unknown User',
avatar: '/images/default-avatar.png'
};
}
}エラーの再スロー
一部のエラーは現在の関数で処理せず、呼び出し元に委譲したい場合があります。その際は、エラーを再スローします。
async function validateAndFetchData(id) {
if (!id) {
throw new Error('IDが指定されていません');
}
try {
const data = await fetchData(id);
return data;
} catch (error) {
// ネットワークエラーは再スロー
if (error.name === 'NetworkError') {
throw error;
}
// その他のエラーは処理
console.warn('データ取得エラー:', error);
return null;
}
}カスタムエラーの作成
より明確なエラーハンドリングのために、カスタムエラークラスを定義することも有効です。
class APIError extends Error {
constructor(message, statusCode) {
super(message);
this.name = 'APIError';
this.statusCode = statusCode;
}
}
async function fetchWithCustomError() {
try {
const response = await fetch('https://api.example.com/data');
if (!response.ok) {
throw new APIError(
`API呼び出しに失敗しました: ${response.statusText}`,
response.status
);
}
return await response.json();
} catch (error) {
if (error instanceof APIError) {
console.error(`APIエラー (${error.statusCode}):`, error.message);
} else {
console.error('予期しないエラー:', error);
}
throw error;
}
}エラー処理のベストプラクティス
async/awaitを使用する際のエラーハンドリングには、いくつかの重要なベストプラクティスがあります。これらを守ることで、保守性が高く堅牢なコードを書くことができます。
1. 必ずtry-catchで囲む
await式を使用する場合は必ずtry-catchで囲むことを習慣化しましょう。これを怠ると、未処理の例外がアプリケーション全体に波及する可能性があります。
// 良い例
async function goodExample() {
try {
const result = await someAsyncOperation();
return result;
} catch (error) {
handleError(error);
}
}
// 悪い例
async function badExample() {
const result = await someAsyncOperation(); // エラーハンドリングなし
return result;
}2. エラーの詳細情報を保持する
エラーオブジェクトには有用な情報が含まれているため、適切に保持して活用しましょう。
async function fetchWithDetailedError() {
try {
const response = await fetch('https://api.example.com/data');
const data = await response.json();
return data;
} catch (error) {
// エラーの詳細を保持した新しいエラーを作成
const detailedError = new Error(`データ取得失敗: ${error.message}`);
detailedError.originalError = error;
detailedError.timestamp = Date.now();
throw detailedError;
}
}3. エラーの種類に応じた処理
エラーの種類によって適切な対処方法は異なります。エラーの種類を判別して処理を分岐させることで、より適切なエラーハンドリングが可能になります。
async function handleDifferentErrors() {
try {
const response = await fetch('https://api.example.com/data');
if (response.status === 404) {
throw new Error('NOT_FOUND');
}
if (response.status === 401) {
throw new Error('UNAUTHORIZED');
}
if (!response.ok) {
throw new Error('SERVER_ERROR');
}
return await response.json();
} catch (error) {
switch (error.message) {
case 'NOT_FOUND':
console.warn('リソースが見つかりません');
return null;
case 'UNAUTHORIZED':
console.error('認証が必要です');
// ログイン画面へリダイレクトなど
redirectToLogin();
break;
case 'SERVER_ERROR':
console.error('サーバーエラーが発生しました');
showErrorNotification('サーバーエラー');
break;
default:
console.error('予期しないエラー:', error);
throw error;
}
}
}4. finally句の活用
エラーの有無にかかわらず実行したい処理(クリーンアップ処理など)は、finally句に記述します。
async function fetchWithCleanup() {
let isLoading = true;
try {
showLoadingIndicator();
const data = await fetchData();
return data;
} catch (error) {
console.error('データ取得エラー:', error);
showErrorMessage('データの取得に失敗しました');
} finally {
// 成功・失敗に関わらず実行される
hideLoadingIndicator();
isLoading = false;
}
}5. トップレベルでのエラーハンドリング
async関数を呼び出す際は、呼び出し側でもエラーハンドリングを行うことを忘れないでください。
// async関数の呼び出し
fetchUserData()
.then(data => {
console.log('データ取得成功:', data);
})
.catch(error => {
console.error('トップレベルでのエラー捕捉:', error);
});
// または
(async () => {
try {
const data = await fetchUserData();
console.log('データ取得成功:', data);
} catch (error) {
console.error('トップレベルでのエラー捕捉:', error);
}
})();これらのベストプラクティスを実践することで、エラーに強く、デバッグしやすいasync/awaitコードを書くことができます。特に本番環境では、適切なエラーハンドリングがアプリケーションの安定性を大きく左右するため、十分な注意を払って実装しましょう。
“`html
async/awaitを使う際の注意点とアンチパターン
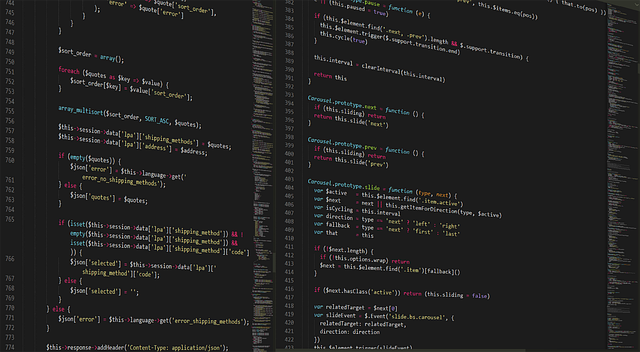
async/awaitは非同期処理を直感的に記述できる強力な機能ですが、適切に使わないとパフォーマンスの低下やコードの可読性を損なう結果となります。実務においては、単に動作するコードを書くだけでなく、効率的で保守性の高い実装を心がける必要があります。ここでは、async/awaitを使用する際によく見られる問題点と、それらを回避するための具体的な方法について解説します。
不要なawaitを避ける書き方
async/await初心者が陥りやすいアンチパターンとして、不要なawaitを多用してしまう問題があります。特に関数の最後でPromiseを返す場合、awaitを使う必要がないケースが多く存在します。
以下は不要なawaitを使用している典型的な例です。
// ❌ 不要なawaitの例
async function fetchUserData(userId) {
return await fetch(`/api/users/${userId}`);
}
この場合、関数の最後でreturnするだけなので、awaitは不要です。awaitを削除することでPromiseのラップを一つ減らし、わずかながらパフォーマンスの向上が見込めます。
// ✅ 改善版
async function fetchUserData(userId) {
return fetch(`/api/users/${userId}`);
}
ただし、try-catchでエラーハンドリングを行う場合は、awaitが必要になります。
// ✅ エラーハンドリングが必要な場合はawaitを使用
async function fetchUserData(userId) {
try {
return await fetch(`/api/users/${userId}`);
} catch (error) {
console.error('データ取得エラー:', error);
throw error;
}
}
また、中間変数に代入した後すぐにawaitするパターンも不要です。
// ❌ 不要な中間変数
async function processData() {
const promise = fetchData();
const result = await promise; // 直接awaitすべき
return result;
}
// ✅ 改善版
async function processData() {
return await fetchData();
}
パフォーマンスを考慮した実装方法
async/awaitを使用する際、最も注意すべきパフォーマンス上の問題は、本来並列実行できる処理を逐次実行してしまうことです。awaitを使うと処理はその場で待機するため、独立した複数の非同期処理を順番に実行してしまうと、無駄な待ち時間が発生します。
// ❌ 逐次実行してしまう悪い例(遅い)
async function fetchAllData() {
const user = await fetchUser(); // 1秒かかる
const posts = await fetchPosts(); // 1秒かかる
const comments = await fetchComments(); // 1秒かかる
// 合計3秒かかる
return { user, posts, comments };
}
上記のコードでは、各データ取得が独立しているにも関わらず、順番に実行されるため合計3秒かかってしまいます。Promise.allを使用することで、並列実行が可能になり、大幅な時間短縮が実現できます。
// ✅ 並列実行する改善版(速い)
async function fetchAllData() {
const [user, posts, comments] = await Promise.all([
fetchUser(),
fetchPosts(),
fetchComments()
]);
// 最も遅い処理の時間(約1秒)で完了
return { user, posts, comments };
}
ただし、処理間に依存関係がある場合は順次実行が必要です。適切に見極めることが重要です。
// ✅ 依存関係がある場合は順次実行が正しい
async function fetchUserPosts(userId) {
const user = await fetchUser(userId); // まずユーザー情報を取得
const posts = await fetchPosts(user.id); // ユーザーIDが必要
return { user, posts };
}
また、部分的に並列化できるケースもあります。
// ✅ 部分的な並列化
async function complexFetch(userId) {
const user = await fetchUser(userId); // 最初は依存関係があるので待つ
// user情報取得後、独立した処理は並列実行
const [posts, friends, settings] = await Promise.all([
fetchPosts(user.id),
fetchFriends(user.id),
fetchSettings(user.id)
]);
return { user, posts, friends, settings };
}
よくある間違いと改善方法
async/awaitを使用する際に発生しやすい間違いとその対処法を具体的に見ていきましょう。これらのパターンを理解することで、より堅牢なコードを書くことができます。
間違い1: forEach内でawaitを使用する
配列のforEachメソッド内でawaitを使用しても、期待通りに動作しません。これはforEachのコールバック関数がasync関数であっても、forEach自体は各Promiseの完了を待たないためです。
// ❌ 動作しない例
async function processItems(items) {
items.forEach(async (item) => {
await processItem(item); // 待機されない
});
console.log('完了'); // 全処理完了前に実行される
}
改善方法として、for…ofループやPromise.allを使用します。
// ✅ 順次処理する場合
async function processItems(items) {
for (const item of items) {
await processItem(item);
}
console.log('完了'); // 全処理完了後に実行
}
// ✅ 並列処理する場合
async function processItems(items) {
await Promise.all(items.map(item => processItem(item)));
console.log('完了');
}
間違い2: async関数を適切にawaitしない
async関数の戻り値は常にPromiseですが、これをawaitせずに使用してしまうケースがあります。
// ❌ awaitを忘れた例
async function saveData() {
const data = getData(); // Promiseオブジェクトが返る
console.log(data); // Promise { } と表示される
return data.value; // undefinedエラー
}
// ✅ 正しい実装
async function saveData() {
const data = await getData();
console.log(data); // 実際のデータが表示される
return data.value;
}
間違い3: トップレベルでawaitを使用する
JavaScriptでは、モジュール以外の通常のスクリプトではトップレベルでawaitを使用できません(Top-level awaitはES2022でモジュールに限り対応)。
// ❌ 通常のスクリプトでは使えない
const data = await fetchData(); // SyntaxError
// ✅ 即時実行async関数でラップ
(async () => {
const data = await fetchData();
console.log(data);
})();
間違い4: エラーハンドリングの欠如
async/awaitでもエラーハンドリングは必須です。try-catchで適切に処理しないと、予期せぬエラーでアプリケーションが停止する可能性があります。
// ❌ エラーハンドリングなし
async function riskyOperation() {
const result = await dangerousApiCall(); // エラーで停止
return result;
}
// ✅ 適切なエラーハンドリング
async function riskyOperation() {
try {
const result = await dangerousApiCall();
return result;
} catch (error) {
console.error('API呼び出しエラー:', error);
return null; // デフォルト値を返す
}
}
間違い5: Promiseチェーンとasync/awaitの混在
コードの一貫性を保つため、同じ処理内でPromiseのthenとasync/awaitを混在させるのは避けるべきです。
// ❌ 混在して読みにくい
async function mixedStyle() {
const user = await fetchUser();
return fetchPosts(user.id)
.then(posts => processPosts(posts))
.catch(error => console.error(error));
}
// ✅ async/awaitに統一
async function consistentStyle() {
try {
const user = await fetchUser();
const posts = await fetchPosts(user.id);
return await processPosts(posts);
} catch (error) {
console.error(error);
}
}
これらのアンチパターンを理解し避けることで、より効率的で保守性の高いasync/awaitコードを書くことができます。特にパフォーマンスに関わる並列処理と逐次処理の使い分けは、実務において重要なスキルとなります。
“`
ブラウザとNode.jsでの対応状況
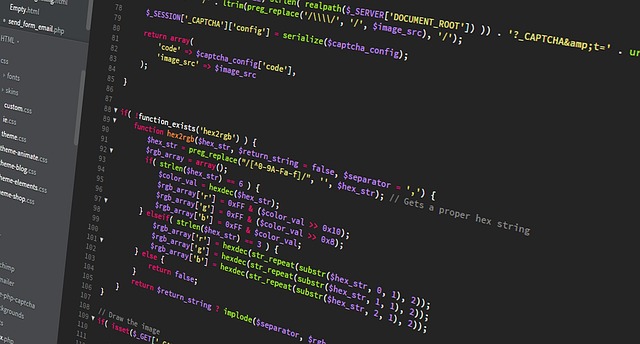
JavaScriptのasync/awaitは、ES2017(ES8)で正式に言語仕様に追加された比較的新しい機能です。実務でこの構文を活用する際には、開発対象となる実行環境でasync/awaitが適切にサポートされているかを把握しておく必要があります。ここでは、主要なブラウザやNode.js環境における対応状況と、実際のプロジェクトで考慮すべき互換性の問題について詳しく解説します。
各環境でのasync/await対応状況
async/awaitは、2017年の仕様策定以降、主要なJavaScript実行環境で広くサポートされるようになりました。現在では、ほとんどのモダンブラウザと最新のNode.jsバージョンで完全にサポートされています。
モダンブラウザでは、Chrome 55以降、Firefox 52以降、Safari 10.1以降、Edge 15以降でasync/awaitが利用可能です。これらのバージョンは2017年から2018年にかけてリリースされたもので、現在では非常に高い普及率を誇っています。Internet Explorer 11については、残念ながらasync/awaitのネイティブサポートはありません。
各ブラウザの対応状況を以下の表にまとめました。
| ブラウザ | 対応バージョン | リリース時期 |
|---|---|---|
| Google Chrome | 55以降 | 2016年12月 |
| Firefox | 52以降 | 2017年3月 |
| Safari | 10.1以降 | 2017年3月 |
| Microsoft Edge | 15以降 | 2017年4月 |
| Opera | 42以降 | 2017年1月 |
| Internet Explorer | 非対応 | – |
Node.jsの環境では、バージョン7.6以降でasync/awaitが正式にサポートされています。Node.js 7.6は2017年2月にリリースされ、それ以前のバージョンでは–harmony-async-awaitフラグを使用することで試験的に利用することができました。Node.js 8以降ではLTS(長期サポート)版でも完全にサポートされており、安定した実務利用が可能です。
モバイルブラウザについても、iOS Safari 10.3以降、Android Chrome 55以降で対応しており、現在のモバイル環境でもほぼ問題なく使用できます。
実務での利用における互換性
実際の開発プロジェクトでasync/awaitを採用する際には、対象ユーザーの利用環境を考慮した互換性の検討が重要です。現代の多くのWebアプリケーションでは、モダンブラウザのみをサポート対象とすることが一般的になってきていますが、企業向けシステムなど特定の環境では古いブラウザへの対応が求められる場合もあります。
Internet Explorer 11や古いバージョンのブラウザをサポートする必要がある場合、async/awaitの構文をそのまま使用することはできません。このような場合の解決策として、以下のようなアプローチが考えられます。
- BabelなどのトランスパイラでES5にコンパイル: async/awaitを含むモダンなJavaScriptコードを、古いブラウザでも動作するES5コードに変換する方法です。この手法により、開発時にはasync/awaitを使用しながら、本番環境では互換性の高いコードを配信できます。
- regenerator-runtimeの使用: Babelでasync/awaitをトランスパイルする際に必要となるランタイムライブラリです。これにより、古いブラウザでもasync/await相当の非同期処理を実現できます。
- Polyfillの適用: Promiseなどの基本的な機能についてはPolyfillを使用して互換性を確保します。
webpack、Rollup、Viteなどのモダンなビルドツールを使用している場合、Babelの設定を適切に行うことで、async/awaitを含むコードの自動トランスパイルが可能です。@babel/preset-envを使用すれば、ターゲットとするブラウザのバージョンを指定するだけで、必要な変換が自動的に適用されます。
// .babelrc設定例
{
"presets": [
["@babel/preset-env", {
"targets": {
"browsers": ["last 2 versions", "ie >= 11"]
}
}]
]
}Node.js環境での開発では、Node.js 10以降のバージョンを使用していれば、トランスパイルなしでasync/awaitを直接使用できます。現在のLTS版であるNode.js 18やNode.js 20では、完全に安定した実装となっているため、サーバーサイドの開発では特に互換性を気にする必要はありません。
TypeScriptを使用したプロジェクトでは、tsconfig.jsonの「target」オプションでコンパイル対象のECMAScriptバージョンを指定できます。”target”: “es5″を指定すれば、async/await構文が自動的に古いブラウザでも動作する形式に変換されます。
実務での判断としては、2024年現在、モダンブラウザのみをサポート対象とする場合は、トランスパイルなしでasync/awaitを使用することが推奨されます。これにより、バンドルサイズの削減とパフォーマンスの向上が期待できます。一方、幅広いユーザー環境への対応が必要な場合は、適切なビルドプロセスを構築し、トランスパイルを行うことで互換性を確保しましょう。
まとめ

この記事では、JavaScriptにおけるasync/awaitの基本概念から実践的な活用方法まで、幅広く解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返りながら、async/awaitを効果的に使用するためのエッセンスをまとめます。
async/awaitは、非同期処理をより直感的で読みやすいコードとして記述できる強力な機能です。従来のコールバック関数やPromiseのthenチェーンと比較して、同期処理のような自然な流れでコードを書けるため、コードの可読性と保守性が大幅に向上します。
async/awaitを使用する際に押さえておくべき核心的なポイントは以下の通りです。
- async関数は必ずPromiseを返す – async宣言された関数は、自動的にPromiseでラップされた値を返します
- awaitはasync関数内でのみ使用可能 – await式はasync関数の中でしか使えないという制約があります
- try-catchによるエラーハンドリングが基本 – 例外処理は同期処理と同じように記述できます
- 並列処理と順次処理を使い分ける – Promise.allを活用することで、パフォーマンスを最適化できます
- 不要なawaitは避ける – すべての非同期処理にawaitを付ける必要はなく、適切な場所で使用することが重要です
実務でasync/awaitを活用する場合、特に以下の点に注意を払うことで、より効率的で保守性の高いコードを実現できます。
| 観点 | ポイント |
|---|---|
| パフォーマンス | 独立した非同期処理は並列実行し、依存関係がある処理のみ順次実行する |
| エラー処理 | 適切な粒度でtry-catchを配置し、エラーの伝播を制御する |
| 可読性 | 複雑な処理は関数に分割し、async/awaitの利点を最大限に活かす |
| 互換性 | 対象環境のブラウザやNode.jsバージョンを確認し、必要に応じてトランスパイルを行う |
async/awaitは、Promiseの上に構築されたシンタックスシュガーであり、Promiseの仕組みを完全に置き換えるものではありません。両者の特性を理解した上で、状況に応じて適切に使い分けることが、JavaScriptにおける非同期処理のマスターへの近道となります。
現代のJavaScript開発において、async/awaitは必須のスキルとなっています。API通信、ファイル操作、データベースアクセスなど、あらゆる場面で非同期処理が必要となる中で、async/awaitを適切に使いこなすことで、より堅牢で読みやすいアプリケーションを構築できるでしょう。
この記事で解説した基礎知識から実践的なテクニックまでを参考に、ぜひ実際のプロジェクトでasync/awaitを活用してみてください。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、使い続けることで自然と身につき、非同期処理に対する理解も深まっていくはずです。




