この記事では、Pythonのdef文による関数の定義と呼び出し方、引数や戻り値の扱い、ローカル・グローバル変数の違いなどを基礎から解説します。関数の書き方や命名ルール、複数戻り値や可変長引数の使い方もわかるため、効率的で再利用可能なコードを作りたい初心者の悩みを解決できます。
目次
Pythonのdef文とは何か

def文の基本的な役割と特徴
Pythonにおいてdef文は、関数を定義するためのキーワードです。プログラムの中で繰り返し利用する処理を一つにまとめ、名前を付けて呼び出せるようにすることで、コードの再利用性や可読性を高めます。例えば、同じ計算や文字列操作を複数箇所で行う場合、def文で関数化することで冗長な記述を避けられます。
def文の主な特徴として以下が挙げられます。
- 任意の名前で関数を定義できる
- 0個以上の引数を受け取れる
return文を使うことで値を呼び出し元に返せる- インデントで関数の実行ブロックを明確にする
例えば、次の例は二つの数値を足し合わせる関数を定義しています。
def add_numbers(a, b):
return a + b
result = add_numbers(5, 3)
print(result) # 出力: 8
このようにpython defを使うことで、処理のまとまりを簡潔に表現できます。
関数とスクリプトの違い
Pythonでは、単独で動作するファイル全体を「スクリプト」と呼び、関数はその中の一部を構成する処理単位です。スクリプトは上から順にコードを実行しますが、関数は呼び出されたときに初めて実行されます。この違いを理解しておくと、用途に応じた柔軟なプログラム設計が可能になります。
- スクリプト:ファイル全体が一連の手続きとして実行される。小規模な自動化や一度きりの処理に適している。
- 関数:名前を持ち、複数回呼び出しが可能。処理を部品化し、再利用性と保守性を高められる。
# スクリプト的な記述
print("Hello World")
print("Hello World")
# 関数化した記述
def greet():
print("Hello World")
greet()
greet()
上記の例のように、スクリプト的な書き方では同じ処理を繰り返し記述する必要がありますが、関数化すればdef文でまとめ、一行で呼び出すだけで済みます。この構造化の違いが、大規模開発やチームでの共同作業において大きな効果を発揮します。
defを使った関数の定義方法

関数の基本構文と書き方
Pythonで関数を定義する際には、defキーワードを使います。関数は処理をひとまとめにして再利用可能にするための重要な仕組みであり、コードの可読性や保守性を高める役割があります。
基本構文は以下の通りです。
def 関数名(引数1, 引数2, ...):
実行する処理
return 戻り値
このように、defの後に関数名と括弧付きの引数リストを記述し、コロン:で終えます。その下には必ずインデントを付けて関数内部の処理内容を書きます。
関数名の命名ルール
関数名はPythonの識別子としてのルールに従い、半角英数字とアンダースコア_のみを使用します。また、先頭に数字を使うことはできず、予約語(例: def, classなど)は使用できません。可読性を高めるためには、PEP8というPythonのコーディング規約に従い、スネークケース(例: calculate_total_price)で命名することが推奨されます。
- 意味のある名前を付ける(例:
get_user_dataは何をする関数かわかる) - 動詞+名詞の組み合わせを心がける
- 短すぎず長すぎないバランス
インデントの重要性
Pythonではブロック構造をインデントで表します。関数の内部処理は必ず同じ幅のインデント(通常はスペース4つ)で揃える必要があります。インデントのずれはIndentationErrorの原因となるため注意が必要です。
def greet(name):
print(f"Hello, {name}!") # インデント4スペース
タブとスペースの混在は避け、チームで統一ルールを決めることが推奨されます。特に共同開発では、エディタの設定で自動的にスペースを挿入するようにしておくとよいでしょう。
引数の指定方法
関数にデータを渡すためには引数を使います。Pythonでは多様な引数の指定方法があり、柔軟な関数設計が可能です。
位置引数
もっとも基本的な引数の渡し方が位置引数です。呼び出し時の引数の順番が重要で、定義された順に値が渡されます。
def add(a, b):
return a + b
result = add(3, 5) # a=3, b=5
デフォルト引数
引数に初期値(デフォルト値)を設定すると、呼び出し時にその引数を省略できます。よく使うパターンやオプションの設定などに便利です。
def greet(name="Guest"):
print(f"Hello, {name}!")
greet() # Hello, Guest!
greet("Alice") # Hello, Alice!
デフォルト引数は必ず位置引数の後に記述します。また、ミュータブルな値(リストや辞書)をデフォルトに指定すると予期せぬ動きになることがあるため、注意が必要です。
可変長引数(*args, **kwargs)
引数の数が不定の場合、*argsや**kwargsを使うと柔軟な関数が書けます。
- *args: 位置引数をタプルとして受け取る
- **kwargs: キーワード引数を辞書として受け取る
def sample(*args, **kwargs):
print("args:", args)
print("kwargs:", kwargs)
sample(1, 2, 3, key1="value1", key2="value2")
# args: (1, 2, 3)
# kwargs: {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}
これを使うことで、将来的に引数の仕様が変わっても既存コードとの互換性を保ちやすくなります。
関数の呼び出し方
定義した関数は、関数名に括弧を付けて呼び出します。括弧内に必要な引数を指定して実行します。
def multiply(a, b):
return a * b
result = multiply(4, 5)
print(result) # 20
引数には位置引数だけでなく、名前を指定して渡すキーワード引数も使用できます。キーワード引数を使うと引数の順番を気にせず渡せるため、可読性と安全性が向上します。
multiply(b=5, a=4) # 20
このように、python defを活用した関数定義と呼び出しの基本を押さえることで、効率的かつ読みやすいプログラムを書くことができます。
関数の戻り値の扱い方

return文の基本
Pythonのdef文で定義した関数は、return文を用いることで処理結果を呼び出し元へ返すことができます。return文が実行されると、その時点で関数の処理は終了し、指定した値が戻り値となります。戻り値は変数に代入したり、他の関数の引数として渡したりすることが可能です。
例えば、2つの数値を加算して結果を返す関数は以下のように定義します。
def add_numbers(a, b):
return a + b
result = add_numbers(3, 5)
print(result) # 出力: 8
このように、returnを使うことで関数は値を外部に渡し、柔軟なプログラム構築が可能になります。
戻り値なし(Noneを返す場合)
関数でreturn文を省略した場合、またはreturnだけを記述した場合は、Pythonでは自動的にNoneが戻り値として返されます。Noneは「何もない」という特別な値で、戻り値を利用しない処理(ログ出力やファイル保存など)を行う関数によく使われます。
def greet(name):
print(f"Hello, {name}!")
result = greet("Alice") # "Hello, Alice!"と出力
print(result) # 出力: None
このように、処理の結果を返す必要がない場合は、戻り値としてNoneを返すのが一般的です。
複数の戻り値を返す方法
Pythonでは、1つのreturn文で複数の値を同時に返すことができます。この場合、値はタプル形式で返され、呼び出し元では複数の変数に一度に代入することも可能です。
def get_person_info():
name = "Bob"
age = 30
return name, age
person_name, person_age = get_person_info()
print(person_name) # 出力: Bob
print(person_age) # 出力: 30
複数の処理結果をまとめて返すことで、関数間で効率的にデータをやり取りできます。必要に応じてリストや辞書を返す方法もありますが、タプルの複数代入は非常にシンプルで便利です。
関数内の変数スコープ

ローカル変数とグローバル変数
Pythonでは、defを用いて定義された関数の中と外で、変数の扱われ方が異なります。これを「変数スコープ」と呼び、コードの可読性やバグの防止において極めて重要な概念です。
スコープには主に「ローカル変数」と「グローバル変数」が存在します。
- ローカル変数:関数の内部で定義され、その関数内でのみ利用可能な変数。関数が終了すると自動的に破棄されます。
- グローバル変数:関数の外部で定義され、同一モジュール全体から参照可能な変数。
例えば、以下のコードでは x はグローバル変数、y はローカル変数として扱われます。
x = 10 # グローバル変数
def sample():
y = 5 # ローカル変数
print("関数内 x:", x) # グローバル変数を参照
print("関数内 y:", y) # ローカル変数を参照
sample()
print("関数外 x:", x)
# print("関数外 y:", y) # エラー: yは関数外からは参照できない
上記のように、同じ変数名でも定義場所によって影響範囲が異なるため、意図しない上書きや参照エラーを防ぐためにスコープを意識することが重要です。
グローバル変数の宣言方法(global)
通常、関数内で代入を行うとPythonは自動的にローカル変数とみなします。しかし、関数内から既存のグローバル変数を書き換えたい場合は、global キーワードを使用して明示的に「これはグローバル変数です」と宣言する必要があります。
count = 0 # グローバル変数
def increment():
global count # グローバル変数を使用する宣言
count += 1
increment()
print(count) # 1
注意:グローバル変数の多用は可読性を下げ、予期せぬバグを招く可能性があります。なるべく関数間のデータ受け渡しには引数や戻り値を使うことを推奨します。
nonlocalの使い方
nonlocal は、関数がネスト(入れ子)されている場合に、外側の関数スコープ(ローカルスコープだがグローバルではない)にある変数を参照・変更したいときに使います。
def outer():
x = 0
def inner():
nonlocal x # 外側関数のローカル変数を参照
x += 1
print(x)
inner()
inner()
outer()
# 実行結果: 1, 2
このようにnonlocalを使うと、外側の関数スコープにある変数の状態を保持しながら処理できます。特にクロージャ(関数を返す関数)パターンで有効に活用されます。
総じて、python def における変数スコープの理解は、バグの削減、パフォーマンス改善、読みやすいコードの実現に直結します。
関連する関数定義の発展的な構文
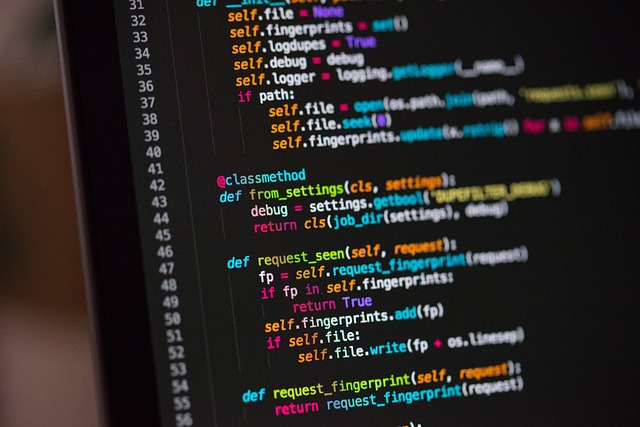
ラムダ式(lambda)
Pythonでは、def文による通常の関数定義のほかに、簡潔な関数を即座に定義できる「ラムダ式(lambda)」が用意されています。ラムダ式は、1行で短い処理を記述する際に便利で、特にmap()やfilter()、sorted()のkey引数など、関数を引数として渡す場面でよく利用されます。
# 通常の関数定義
def add(x, y):
return x + y
# ラムダ式での定義
add_lambda = lambda x, y: x + y
print(add_lambda(3, 5)) # 出力: 8
ラムダ式の特徴は以下の通りです。
- 一度きりの関数定義に適している
- 式しか書けず、複数の文を書くことはできない
- 名前を付けずに即座に関数オブジェクトとして利用可能
ジェネレーター(yield)
ジェネレーターは、yieldキーワードを使うことで、関数の実行を一時停止し、値を順次返す仕組みです。大量データの逐次処理や無限シーケンスの生成など、メモリ効率を優先する場合に効果的です。
def number_generator():
n = 1
while True:
yield n
n += 1
gen = number_generator()
print(next(gen)) # 出力: 1
print(next(gen)) # 出力: 2
ジェネレーターを使うメリットは、すべての値を一度にメモリへ保持せずに処理を進められるため、特に大規模データやストリーム処理と相性が良い点です。
デコレーター(@)
デコレーターは、関数の前に@デコレーター名と記述することで、その関数に追加の機能を付与できる構文です。ログ出力、実行時間の計測、認証チェックなど、横断的な機能を簡潔に実装できます。
def logging_decorator(func):
def wrapper(*args, **kwargs):
print(f"Calling {func.__name__}")
return func(*args, **kwargs)
return wrapper
@logging_decorator
def greet(name):
print(f"Hello, {name}!")
greet("Python")
# 出力:
# Calling greet
# Hello, Python!
デコレーターは関数やクラスに対して適用でき、コードの再利用性と可読性の向上に大きく貢献します。
イテレーター(iterator)
イテレーターは、__iter__()と__next__()メソッドを実装したオブジェクトで、要素を順番に取り出す仕組みを提供します。Pythonのforループは内部的にイテレーターを利用しており、ユーザー定義のクラスでもこれらのメソッドを実装すれば独自の反復処理が可能です。
class CountUp:
def __init__(self, limit):
self.limit = limit
self.current = 0
def __iter__(self):
return self
def __next__(self):
if self.current < self.limit:
self.current += 1
return self.current
else:
raise StopIteration
for num in CountUp(3):
print(num) # 出力: 1, 2, 3
イテレーターを理解すると、Pythonのシーケンス処理やジェネレーターとの組み合わせがより効果的に活用でき、defによる関数設計の幅も広がります。
関数の可読性向上のための記述方法

ドキュメンテーション文字列(docstring)の使い方
Pythonで関数を定義する際、def文と合わせて使うことで可読性を大きく向上させるのが「ドキュメンテーション文字列(docstring)」です。docstringは関数の目的や使用方法、引数・戻り値の情報をコード内に直接記述できるため、利用者や将来の自分が関数の意図を素早く理解する助けになります。
docstringは、関数の定義直後に三重引用符 """ または ''' を用いて記述します。Pythonのビルトイン関数help()や、モジュール内の.__doc__属性を参照することで、この説明文をプログラム内や対話的シェルで確認できます。
def greet(name):
"""
指定した名前のユーザーに挨拶をする関数。
Args:
name (str): 挨拶をする相手の名前。
Returns:
str: 挨拶メッセージ。
"""
return f"こんにちは、{name}さん!"
上記のように、docstringには以下の情報を含めると効果的です。
- 関数の概要:関数の目的や機能を一文で明示
- 引数(Args):名前、型、意味の説明
- 戻り値(Returns):戻り値の型と説明
- 注意点や例外:発生する可能性のあるエラーや制約条件
- 使用例(Examples):具体的な呼び出し例
def divide(a, b):
"""
2つの数値を割り算する関数。
Args:
a (float): 被除数。
b (float): 除数(ゼロは不可)。
Returns:
float: 割り算の結果。
Raises:
ValueError: b が 0 の場合に発生。
Example:
>>> divide(10, 2)
5.0
"""
if b == 0:
raise ValueError("除数 b はゼロにできません。")
return a / b
特にチーム開発や長期運用されるコードでは、docstringによる明確な関数説明が品質を大きく左右します。読みやすく維持管理しやすいコードは、機能だけでなく説明文も充実しているのが共通点です。Pythonのdef文とdocstringを組み合わせて、誰が読んでも意図が伝わる関数設計を心がけましょう。
まとめと実践的な活用例

def文を使った効率的なコード設計のポイント
Pythonのdef文は、コードの再利用性と可読性を高めるための基本的な構文です。効率的なコード設計を行うためには、関数の役割を明確に定義し、単一責任の原則(SRP)を意識することが重要です。具体的には、1つの関数が複数の責務を持たないように分割し、処理内容を端的に表す命名を行うことで、後からコードを読む人や修正する人にとっても理解しやすくなります。
- 関数の粒度を小さくする:長大な処理を一つの関数にまとめず、適切に分割しモジュール化します。
- 引数と戻り値の設計:必要最小限の引数にし、戻り値もシンプルに保つことでバグの発生を減らします。
- ドキュメンテーションの活用:
docstringを使い、関数の目的や引数、戻り値を明確に記述します。 - 再利用性の確保:特定の用途だけでなく、汎用的に使えるように関数設計を心がけましょう。
例えば、業務システムでのデータ検証処理やWebアプリケーションでの共通フォーマット変換処理などは、def文で適切に切り出すことでメンテナンス性が向上します。
よくあるエラーとその対処方法
def文を使う際には、初心者から上級者まで注意すべき典型的なエラーがいくつか存在します。それぞれのエラーは原因を理解すれば簡単に回避できます。
- IndentationError(インデントエラー):
Pythonはインデントでブロックを判別するため、スペースやタブの混在により発生します。
対処法: エディタの設定でインデントを統一し、スペース4つやタブだけを使用します。 - NameError(名前が未定義):
関数内や呼び出し時に変数名や関数名が誤っている場合に発生します。
対処法: 関数定義より前で関数を呼び出していないか、スペルミスがないかを確認します。 - TypeError(型エラー):
関数が想定する型とは異なるデータ型を引数に渡すと発生します。
対処法: 引数の型をisinstance()等でチェックするか、型ヒント(type hints)を利用します。 - UnboundLocalError(ローカル変数の参照エラー):
関数内で変数を宣言する前に参照してしまった場合に発生します。
対処法: 変数のスコープを正しく理解し、globalやnonlocalを適切に使う必要があります。
これらのエラーは、開発初期から静的解析ツール(例えばflake8やpylint)を導入することで、早期に発見し修正することが可能です。また、ユニットテストを併用すれば、関数単位での挙動を保証でき、def文を使った開発がより安全で効率的になります。




